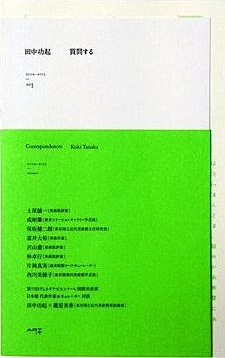ヴェネツィアと京都の田中功起
小崎 哲哉
2013.08.04
某月某日
京都国際現代芸術祭「オープンリサーチプログラム」に行く。今年のヴェネツィア・ビエンナーレで特別表彰を受賞した日本館の、アーティスト田中功起とキュレーター蔵屋美香による報告会だ。会場となった同志社大学(今出川)の教室は、ほぼ満員の盛況。300人近く入っていたんじゃないだろうか。ビエンナーレ自体の説明、日本館の歴史と性格、田中+蔵屋組が代表に選出された経緯などから始まり、実際の展示の説明、背景や意図の解説など、予定を大幅に超えて2時間半ほどのトークとなったが、選考の際のプレゼンで用いた映像やマケットの写真なども映写され、非常にわかりやすかった。
田中功起のアートは、広い意味で、リアム・ギリック、フェリックス・ゴンザレス=トレス、ピエール・ユイグ、フィリップ・パレーノ、リクリット・ティラヴァニらに代表される「リレーショナルアート」に属していると言えるだろう。蔵屋によれば田中は、初期には「もの」への関心があり、次に「もの」と「人」との関係に重点が移行し、現在は「人」と「人」との関係性を扱っているという。今回のヴェネツィアでは、「3・11の後で、それに触れない作品というのは考えられなかった」と蔵屋が語るように、極めて間接的な形でだが「震災」も主題のひとつとなっていた。
例えば、前年の建築ビエンナーレで用いられた木材がリサイクルされている。コミッショナー伊東豊雄や参加作家の声明文もそのまま残されている。もちろん、大部分は田中の写真や映像作品で、それらはすべて「複数の人々が一緒に何かを行う」ことの記録である。「9人の美容師が1人の髪をカットする」「5人のピアニストが1つの曲を合作する」「5人の詩人が1編の詩を合作する」「大勢で都会のビルの非常階段を上り下りする」「懐中電灯を振りながら夜の街を歩く」「非常食を食べながら名前について話す」などなど。
「階段」「夜の街」「非常食」は震災の記憶を直接に呼び起こすが、震災前に作られた「ヘアカット」や、同じコンセプトで震災後に作られた「ピアノ」「詩」はそうでもない。とはいえ、これらも震災を、それが言い過ぎなら「非常時」を無意識の内に予知した作品だと言えるかもしれない。「複数の人々が一緒に何かを行う」ことはもちろん平時にもありうるが、非常時にこそそれが求められるからだ。アーティストは非常時が訪れることを「坑道のカナリア」的に予見していたのだろうか。あるいは我々は、実は震災以前から長いこと非常時に生きていて、カナリアはそのことをこそ察知していたのだろうか。いずれにせよ、大災害が再び起こるのはほぼ確実だと言われているのだから、今後はまさしく非常時が続いてゆく。多くの人がそれを忘れたいと思い、事実忘れているとしても。
一方、「非常時」というよりは「非日常」と呼ぶべきだろうが、アート展の制作も「複数の人々が一緒に何かを行う」例にほかならない。田中と蔵屋がそのことに意識的だったのは当然だろうが、田中の展示の記録映像を撮った藤井光も、それを敏感に感じ取っていたらしい。藤井は、アーティスト及びキュレーターという「主役」ばかりでなく、設営に携わったスタッフやボランティア、開場前に会場を掃除する人々、警備に当たる警官らにもレンズを向けていた。「ヘアカット」や「ピアノ」のように、田中の展覧会も協働によって成り立っている。その事実を可視化した映像であり、そのことは蔵屋も強調していた。
「ヘアカット」や「ピアノ」や「詩」は、上映時間が長いこともあって、当初はヴェネツィアに展示するつもりはなかったという。その思いを変えさせたのは、京都国際現代芸術祭2015のアーティスティックディレクターで、日本館の選考委員でもある河本信治の「あれはじっくり見せるほうがいい」というひとことだったそうだ。また、ふたりが震災という重い主題をどう扱うべきか考えあぐねていたときには、前年の建築ビエンナーレに参加した写真家・畠山直哉が「アートは遠回りすることに意味があるのでは?」と言ってくれたという。蔵屋は「その言葉に背中を押されたように思いました」と語っていた。多くのスタッフらに加え、河本と畠山も、田中の展示の協働者ということになるだろう。
ところで、僕が日本館で感心したのは、夥しいテキストが映像とともに展示されていたことだ。会場で販売されていたカタログも、通常の図録とは違って画像は少なく、作家のインタビューなど、大量のテキストが詰め込まれていた。そこには「日本(東洋/自国)のことは外人(西洋/他国)にはわからない」という偏狭な思い込みや、「以心伝心の美学」のような自己満足的な韜晦はかけらもない。「伝えるべきことを、できうる限り言葉をもって説明する」という、潔いまでの確信に裏づけられているように思えた。
同じことはこの日のトークでも、『ART iT』の連載をまとめた田中の書籍『質問する』でも感じられた。武蔵美の出版編集室での勤務経験があり、一時は批評家を志していたという田中の中には、(全幅の、とまではいかないものの)言語と論理への大きな信頼があるのだろう。今回ヴェネツィアで展示した映像は、すべて特設サイトで観ることができるが、そこにも、「蔵屋さんとのスカイプミーティング後メモ書き」から「田中功起によって書き換えられたキュレーター・ステートメント」まで多数のテキストが収録・公開されている。選考委員のコメントなど、今後もテキストは追加されていくらしい。
そういえば前回のブログで、河本監督について「氏の企画展には他のキュレーターには見られない『狂気』を感じることがある」と記したけれど、あれは舌っ足らずだった。該博な知識をもとに思考を重ね、論理を組み立ててゆくタイプの企画者なのだから、正しくは「論理・思考の果ての狂気」と書くべきだった。キュレーターとアーティストを比較するのはおかしいかもしれないが、田中の作品もきわめて知的・論理的に構築されているものの、河本にときおり見られる極端さは感じられない。だから狂気とは無縁だと思っていたけれど、論理を突き詰めようとする態度の中に、狂気に通ずる強度があるのかもしれない。田中作品をずっと観続けてきて、最近はそんなふうに考えるようになってきた。
京都国際現代芸術祭「オープンリサーチプログラム」に行く。今年のヴェネツィア・ビエンナーレで特別表彰を受賞した日本館の、アーティスト田中功起とキュレーター蔵屋美香による報告会だ。会場となった同志社大学(今出川)の教室は、ほぼ満員の盛況。300人近く入っていたんじゃないだろうか。ビエンナーレ自体の説明、日本館の歴史と性格、田中+蔵屋組が代表に選出された経緯などから始まり、実際の展示の説明、背景や意図の解説など、予定を大幅に超えて2時間半ほどのトークとなったが、選考の際のプレゼンで用いた映像やマケットの写真なども映写され、非常にわかりやすかった。
田中功起のアートは、広い意味で、リアム・ギリック、フェリックス・ゴンザレス=トレス、ピエール・ユイグ、フィリップ・パレーノ、リクリット・ティラヴァニらに代表される「リレーショナルアート」に属していると言えるだろう。蔵屋によれば田中は、初期には「もの」への関心があり、次に「もの」と「人」との関係に重点が移行し、現在は「人」と「人」との関係性を扱っているという。今回のヴェネツィアでは、「3・11の後で、それに触れない作品というのは考えられなかった」と蔵屋が語るように、極めて間接的な形でだが「震災」も主題のひとつとなっていた。
例えば、前年の建築ビエンナーレで用いられた木材がリサイクルされている。コミッショナー伊東豊雄や参加作家の声明文もそのまま残されている。もちろん、大部分は田中の写真や映像作品で、それらはすべて「複数の人々が一緒に何かを行う」ことの記録である。「9人の美容師が1人の髪をカットする」「5人のピアニストが1つの曲を合作する」「5人の詩人が1編の詩を合作する」「大勢で都会のビルの非常階段を上り下りする」「懐中電灯を振りながら夜の街を歩く」「非常食を食べながら名前について話す」などなど。
「階段」「夜の街」「非常食」は震災の記憶を直接に呼び起こすが、震災前に作られた「ヘアカット」や、同じコンセプトで震災後に作られた「ピアノ」「詩」はそうでもない。とはいえ、これらも震災を、それが言い過ぎなら「非常時」を無意識の内に予知した作品だと言えるかもしれない。「複数の人々が一緒に何かを行う」ことはもちろん平時にもありうるが、非常時にこそそれが求められるからだ。アーティストは非常時が訪れることを「坑道のカナリア」的に予見していたのだろうか。あるいは我々は、実は震災以前から長いこと非常時に生きていて、カナリアはそのことをこそ察知していたのだろうか。いずれにせよ、大災害が再び起こるのはほぼ確実だと言われているのだから、今後はまさしく非常時が続いてゆく。多くの人がそれを忘れたいと思い、事実忘れているとしても。
一方、「非常時」というよりは「非日常」と呼ぶべきだろうが、アート展の制作も「複数の人々が一緒に何かを行う」例にほかならない。田中と蔵屋がそのことに意識的だったのは当然だろうが、田中の展示の記録映像を撮った藤井光も、それを敏感に感じ取っていたらしい。藤井は、アーティスト及びキュレーターという「主役」ばかりでなく、設営に携わったスタッフやボランティア、開場前に会場を掃除する人々、警備に当たる警官らにもレンズを向けていた。「ヘアカット」や「ピアノ」のように、田中の展覧会も協働によって成り立っている。その事実を可視化した映像であり、そのことは蔵屋も強調していた。
「ヘアカット」や「ピアノ」や「詩」は、上映時間が長いこともあって、当初はヴェネツィアに展示するつもりはなかったという。その思いを変えさせたのは、京都国際現代芸術祭2015のアーティスティックディレクターで、日本館の選考委員でもある河本信治の「あれはじっくり見せるほうがいい」というひとことだったそうだ。また、ふたりが震災という重い主題をどう扱うべきか考えあぐねていたときには、前年の建築ビエンナーレに参加した写真家・畠山直哉が「アートは遠回りすることに意味があるのでは?」と言ってくれたという。蔵屋は「その言葉に背中を押されたように思いました」と語っていた。多くのスタッフらに加え、河本と畠山も、田中の展示の協働者ということになるだろう。
ところで、僕が日本館で感心したのは、夥しいテキストが映像とともに展示されていたことだ。会場で販売されていたカタログも、通常の図録とは違って画像は少なく、作家のインタビューなど、大量のテキストが詰め込まれていた。そこには「日本(東洋/自国)のことは外人(西洋/他国)にはわからない」という偏狭な思い込みや、「以心伝心の美学」のような自己満足的な韜晦はかけらもない。「伝えるべきことを、できうる限り言葉をもって説明する」という、潔いまでの確信に裏づけられているように思えた。
同じことはこの日のトークでも、『ART iT』の連載をまとめた田中の書籍『質問する』でも感じられた。武蔵美の出版編集室での勤務経験があり、一時は批評家を志していたという田中の中には、(全幅の、とまではいかないものの)言語と論理への大きな信頼があるのだろう。今回ヴェネツィアで展示した映像は、すべて特設サイトで観ることができるが、そこにも、「蔵屋さんとのスカイプミーティング後メモ書き」から「田中功起によって書き換えられたキュレーター・ステートメント」まで多数のテキストが収録・公開されている。選考委員のコメントなど、今後もテキストは追加されていくらしい。
そういえば前回のブログで、河本監督について「氏の企画展には他のキュレーターには見られない『狂気』を感じることがある」と記したけれど、あれは舌っ足らずだった。該博な知識をもとに思考を重ね、論理を組み立ててゆくタイプの企画者なのだから、正しくは「論理・思考の果ての狂気」と書くべきだった。キュレーターとアーティストを比較するのはおかしいかもしれないが、田中の作品もきわめて知的・論理的に構築されているものの、河本にときおり見られる極端さは感じられない。だから狂気とは無縁だと思っていたけれど、論理を突き詰めようとする態度の中に、狂気に通ずる強度があるのかもしれない。田中作品をずっと観続けてきて、最近はそんなふうに考えるようになってきた。