GAT 045 荒木悠
グローカル・アート・トーク

幼少期に日本とアメリカを行き来しながら過ごした経験をもつ荒木悠は、文化の伝播や異文化間に生じる誤解や誤訳、オリジナルと複製の関係性をテーマとした作品を国内外で発表している。今日において、グローバルな活動とは一体何を意味するのか。以下は、2024年4月26日に行われたオンライントークからの抜粋である。
構成: 奥田奈々子
私は自己形成期である幼少期を英語圏のアメリカで過ごしました。2種類以上の言語体系ないしは、言語編集の切り替えを行うことをコード・スウィッチングというのですが、「言語圏によってペルソナが変わる」という感覚を小さい頃から自覚しながら育ちました。私の作品はこうした感覚の狭間から生まれるとも言えます。
グローバルとグローカルの重なるところ
まず、「グローカル」という言葉の定義なのですが、これは日本で生まれた造語です。土着化を意味する「グローバル」と「ローカル」を掛け合わせた言葉で、80年代初頭から中盤、日本経済が好調だった時代に生まれました。私は1985年生まれなのですが、こうした社会背景に生まれたことを改めて意識するとともに、最近の作品も極めてグローカル的であるのではないかと改めて感じるようになりました。この講演では、グローバルに成りきれない、むしろ「グローカル」ともいえる私自身の実践を軸に、その両義的な可能性についてお話ししたいと思います。
2023年に展示をしたもののなかから作品を紹介します。
まず1つ目は、《複製神殿》(2016)という映像インスタレーションです。2つの建築物の間を私がただひたすら走り続ける、という作品です。建築物の1つはアメリカのテネシー州にあるナッシュビルという、パルテノン神殿の複製(レプリカ)です。1897年の博覧会のために建てられたパビリオンで、私はこの街で幼少期から高校までを過ごしました。小さい頃からこの建物に親しんでいたので、これが本物のパルテノン神殿だと思っていたんですが、後に複製だと知り、大きな衝撃を受けました。
もう1つは、スコットランドのエジンバラにあるナショナル・モニュメントです。これもパルテノン神殿を模しています。予算がなくなった関係でファサードしか造られなかったという歴史があり、元はナポレオン戦争で亡くなった兵士のためのモニュメントとして建てられました。
どちらも同じギリシャのパルテノン神殿を模しているのですが、建てられた場所と文脈によって、その意味や機能が変わってしまう。その2つの複製建築の周りを、adidas Originalsのジャージを着て、「オリジナルとは何か」を問いながら堂々巡りする、という作品です。また、我々が慣れ親しんでいるモニターのアスペクト比もパルテノン神殿も黄金比を用いている点もからめています。《複製神殿》は、横浜美術館で公開したのちに、New Balanceのお店でインスタレーションとして展示したのですが、その際に会場にあわせて再構成しました。空間にあわせて展示を改変するということは、ある種の土着化(ローカリゼーション)とも言えるのではないかなと思っています。

Temple of the Templet (Short Track)
2023, 2-channel video installation, synched, loop.
Installation view at T-HOUSE New Balance
Tokyo, Japan
《仮面の正体(海賊盤)》(2023)は、KISSのコピーバンドとして活動するWISSを追ったドキュメンタリー作品です。WISSのメンバーは60代半ばなのですが、車の整備士、畳職人、美容師など、それぞれ異なる職業を持っています。作品タイトルは、KISSのアルバム名に由来しています。KISSが初来日した1977年、当時中学生だった彼らの熱い思いを複製しつつ、彼らの仮面の正体に迫るという作品です。世界中にKISSのコピーバンドは存在しますが、KISSの白いメイクも一説によると日本の歌舞伎に由来すると言われているように、「日本版KISS」であることに必然性を感じています。この作品もまた、かなりダイレクトにグローカルな視点を持っていると言えるでしょう。
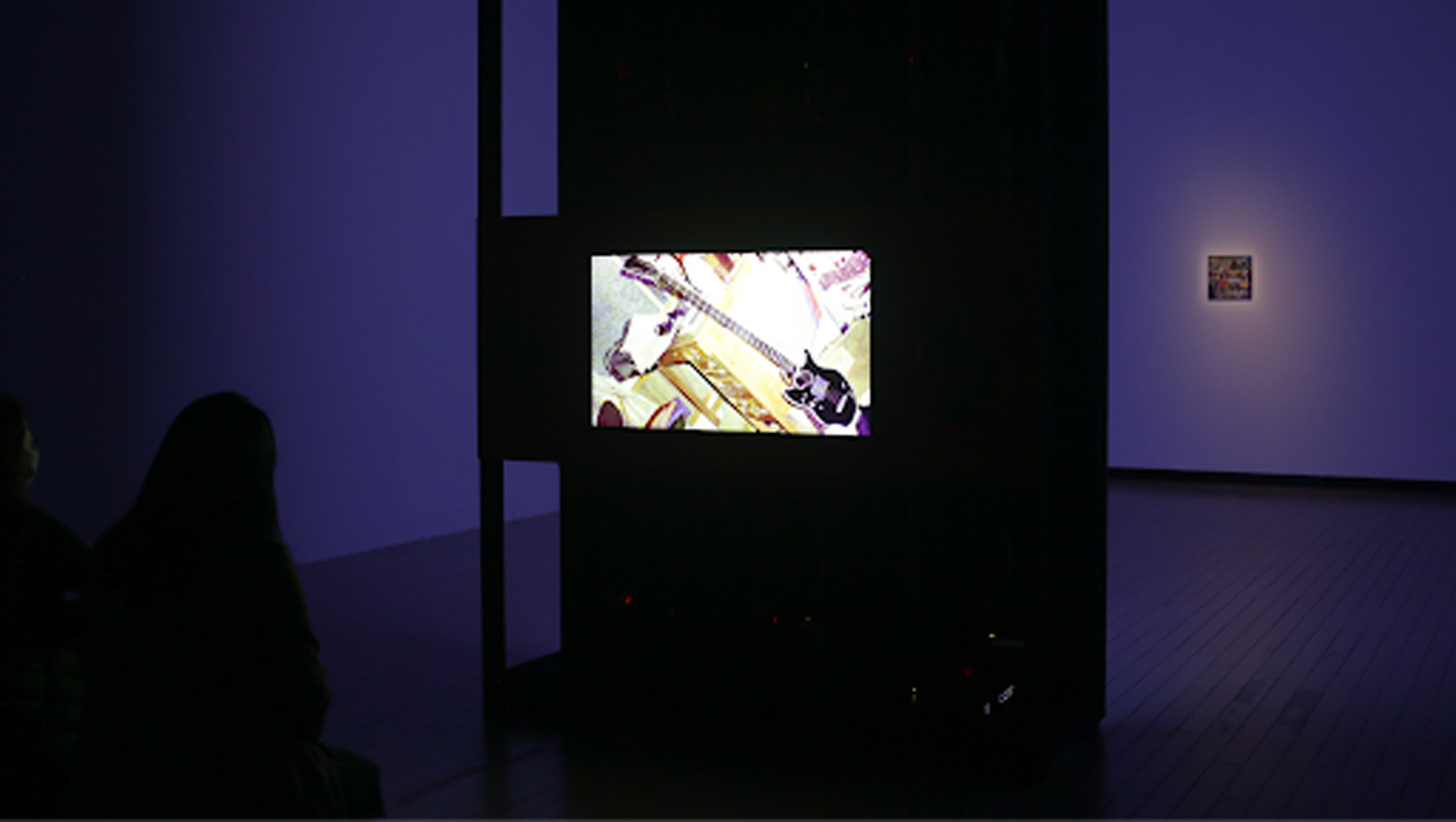
UNMASKED (BOOTLEG)
Installation view at Tokyo Photographic Art Museum
オリジナルと複製のあわい
《Ólafur》(2014)はアイスランドの小さな村で制作した作品です。現在、国立国際美術館のコレクションとして収蔵されています。映画を一本作るというプログラムで赴いたアイスランド滞在の最後に、成果物を地元の人々に映画祭という形でお披露目することが決まっていました。そこで、私は現地で知り合った彫刻家にアカデミー賞で授与される、オスカー像の作成を依頼し、その一部始終を映像に記録することにしました。出来上がったものはなんともアイスランドらしさが滲み出た逸品。この、オリジナルとの差異にこそその土地らしさや風土が組み込まれているのではないかと強く感じたんです。

Ólafur, production still, 2014
普段あまりシリーズものを作ることはないのですが、《Ólafur》に続いて《JB》(2022)、《SOUTH》(2023)、そして《OOPARTS》(2023)を制作しました。《JB》は、2019年に南イタリアのマテーラという街にレジデンスで滞在した際に制作しました。この街は、その年にジェームス・ボンドの最新作のロケ地として使われたそうで、至る所にサインや写真といった痕跡がありました。地元の方が興奮気味に色々な話を伝えてくれ、ロケ地巡りをしたのですが、それほどこの街に強く印象に残っている出来事なのだと感じました。また、マテーラはかつて貧しい地域であり、多くの家族が同じ窯で手作りのパンを焼くという伝統があったそうなのですが、その際に、パンに印をつけるための「ブレッド・スタンプ」という道具が使われていたことを知りました。
私は、パンに押すスタンプの印、とハリウッド資本のスパイ映画が町中に残していった足跡、これらの共通点を掛け合わせ、地元の工芸職人に依頼してオスカー像型のブレッド・スタンプを作ってもらうことにしたのです。

Oscar Project
2023, Installation view at Towada Art Center,
Photo: Oyamada Kuniya
続いて、青森県の十和田市現代美術での個展にあわせて制作したのが《SOUTH》と《OOPARTS》です。
《SOUTH》は南部地方に伝わる、南部系のこけし職人にお願いして作っていただきました。タイトルですが、現在の十和田市が位置する場所は江戸時代には南部氏が統べていた南部藩の北東にあたり、その「南」と、英語で「ものごとが良くない状態」や「グラフで下降を示す状態」を「SOUTH」といいますが、まさに伝統技術の継承が難しくなっているこけし業界の現状を重ねています。

SOUTH
2023, Installation view at Towada Art Center,
In collaboration with Kazufumi Tayama
Photo: Oyamada Kuniya
《OOPARTS》は、縄文時代の土偶を模したオスカー像です。タイトルは、「Out of Place Artifact(場違いな工芸品)」の略に由来しています。青森では、縄文土器や土偶がよく出土することで知られており、その土地ならではの特徴として着想源となりました。映画芸術科学アカデミーのシンボルとして世界的に有名なオスカー像ですが、なぜそもそも「オスカー」という愛称で親しまれているのかの由来には実は諸説あって、誰にもわからない状態なのだそうです。同様に、縄文時代の土偶もその用途や目的が解明されていません。こうした「由来の謎」も本作を作る上での重要な要素でした。

OOPARTS
2023, Installation view at Towada Art Center,
In collaboration with Hiroomi Ichinohe
Photo: Oyamada Kuniya
NEW HORIZON
まず、《NEW HORIZON》(2023)のタイトルですが、東京書籍が出版する英語の教科書に由来します。十和田市は人口6万人ほどの地方都市です。展覧会の話以外では、それまでゆかりがなかった十和田という場所で、県外から呼ばれてきた異邦人としての私は一体何ができるのか、それを考えるのが最大のチャレンジでした。そこで、同じく越境した人物たちに焦点をあてようと思ったのが本作です。まず、この街や近隣に住む6名の外国語指導助手(ALT)にインタビューを行いました。現代を生きるALTの先生たちのインタビューを通じて、時代は一気に175年前の1848年にまで遡ります。日本がまだ鎖国をしていた時代に、「最初の英語教師」として日本に密入国してやってきた人物ラナルド・マクドナルドの滞在記と現代の異文化体験の話が交互に展開します。語られている内容は、2つの言語圏の間にある絶対的な隔たりや異文化間で生じる差異が、時空を超えてシンクロします。奇しくも、ラナルド・マクドナルドの名前が、アメリカの某ハンバーガー・チェーンのマスコットと似ているという奇妙な接点を軸にしています。シンクロといえば、インタビュー収録中にひとりのALTの方が、「日本のテレビ番組は外国人をピエロのように描いていてちょっとムカつく」と話すシーンがあるのですが、これは偶然紡ぎ出された言葉だったのですね。
こちらのスナップ写真は、十和田市の中心街の様子なのですが、何度か通っているうちに街の中心にマクドナルドの新店舗がいつの間にかできていることに気がつきました。《NEW HORIZON》本編の最後のシーンですが、三沢基地の近くにある、淋代(さびしろ)海岸という場所で撮影しました。この場所から初めてアメリカに向けて環太平洋無着陸飛行に成功した飛行機が飛び立ったりと、第二次世界大戦前のアメリカと日本を考える上では重要なロケーションなのですね。そこに、ピエロのキャラクターが太平洋のアメリカの方角を向いて夜明けを見ている、というシーンで終わります。資本主義から生まれたビジネスモデルとしてのチェーン展開、いわゆるグローカリゼーションと植民地主義の問題にも繋がるような、アンビバレントな関係を示唆しています。


NEW HORIZON
2023, Installation view at Towada Art Center,
Photo: Oyamada Kuniya
最後になりますが、グローバル・ゼミで教える機会をいただいたものの、自分自身がグローバルな視点を提供できているかについては正直疑問を感じており、そのためにこのトークを設定しました。たまたま親の仕事の都合でアメリカに渡り、英語を習得したわけですけれども、それがすなわちグローバルであるかというとまったく違うわけですね。自分の活動は極めてグローカルであるという自覚が芽生えつつあり、さらには今後どのような視野で進んでいくべきか、考えているところです。今日はこのような機会をいただき、ありがとうございました。
荒木悠(あらき・ゆう)
アーティスト・映画監督。1985年生まれ。2007年ワシントン大学サム・フォックス視覚芸術学部美術学科彫刻専攻卒業。2010年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修士課程修了。文化の伝播や異文化同士の出会い、またその過程で生じる誤訳や誤解の持つ可能性に強い関心を寄せている。特に、近年の映像インスタレーションでは、歴史上の出来事と空想との狭間に差異を見出し、再現・再演・再生といった表現手法で探究している。主な展覧会と映画祭に、「LONELY PLANETS」(十和田市現代美術館、青森、2023)、「Memory Palace in Ruins」(台湾現代文化実験場、台北、2023)、「恵比寿映像祭2023コミッション・プロジェクト」 (東京都写真美術館)、ホームビデオ・プロジェクト「テールズアウト」(大阪中之島美術館、2022)、第31回マルセイユ国際映画祭(フランス、2021)、「Connections―海を越える憧れ、日本とフランスの150年」(ポーラ美術館、神奈川、2020 )、「 LE SOUVENIR DU JAPON ニッポンノミヤゲ」(資生堂ギャラリー、東京、2019)、「The Island of the Colorblind」 (アートソンジェ・センター、ソウル、韓国、2019)、第47回ロッテルダム国際映画祭(オランダ、2018)など。
※ このトークは2024年4月26日にに京都芸術大学で開催された。