Review
平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989-2019
文:福永 信

1999年/平成11年、椹木野衣は『日本ゼロ年』展をキュレーションした。この展覧会が画期的だったのは、長編評論『日本・現代・美術』(1998)の実践/応用編だったことだ。評論と展覧会(実作)との断絶を、アクロバティックに接続する、このような誰も思いつかない斬新なアイデアは、彼の特徴である。
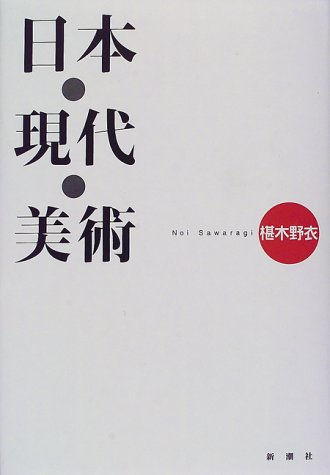
椹木野衣『日本・現代・美術』(新潮社)
美術批評家としてのデビュー評論集『シミュレーショニズム ハウス・ミュージックと盗用芸術』(1991)から始まる初期の数々の著作で椹木は、一貫して、西洋、特にアメリカ文化の受容に翻弄され続ける日本の現代の美術(と批評)の姿をその都度、分析してきた。見えてくるのはいつも、相対化しようとしてもどこかへ消え去ってしまう蜃気楼のような「現代美術」の姿だった。崩壊と堂々巡りの悪循環を繰り返す、日本の「現代美術」の正体とは一体何か?
本展では、平成の30年間余りを振り返るにあたり、個人の作家ではなく集団、集合、人の複数性に注目した。平成のアートの特徴を「集合」に見るなんて聞いたことがないし、珍説と言ってもいいくらいだが、こういうのが椹木の本領である。彼の文章を読んでいると、どんなに奇妙なことでも、「最初からおれもそう思ってた」くらいな気持ちになる。魔の説得力の持ち主というべきであり、非常にクリエイティヴな批評家なのだ(多くの批評家が言葉に対して消極的・遠慮がち・忖度傾向の持ち主なのに対し、椹木は言葉を大胆に使い、飛躍をし、時に笑われながらも、思いがけない発見を読者に体験させることをやめない。遠慮しない)。
本展はまず冒頭に巨大な平成年表「平成の壁」が屹立しており[いちばん上の写真の左側]、主にその裏側が展示空間となっている。年表的にいったん、その集団、複数性を三期に分けた上、展示構成の上では、それらの分割を無効化し「渾然一体」にしているのだ。その三期とは①平成の初期、1990年/平成2年前後の、バンド的なアーティスト集団の生成(Complesso Plasticoなど)から始まり、バブルが弾け、経済が長期的な混迷に突入し、経済的なものとは無縁だった集団的な活動が見えにくくなると、②その空白期を埋めるように、美術のシステムの外へと自ら侵食していくような新たな運動が2005年/平成17年あたりから見られ始める(Chim↑Pomなど)。さらに流れに合流するようにして、平成の終わりまでの数年のうちに、③個人と個人の集まりによって美術の場を見つけていく「作家なき作品」とも呼ぶべき動きが見えてくる(突然、目の前がひらけてなど)というものである。
これらの集団、集合的なアートの傾向は、アーティスト・コレクティヴ、リレーショナル・アート、ソーシャリー・エンゲイジド・アートといった同時代の海外の動向とは必ずしも重なるものではなく、国内の過酷な社会状況がむしろ強く影響しているというのが、椹木のアイデアの独特なところだ。阪神淡路大震災で注目されたヴォランティアやオウム真理教事件といった平成の初期の、個の力を超えた人間の「集合」のパワーを見せつけられた経験、そして、2011年/平成23年の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の大事故による地域の共同体の分断(集団移転など)を目の当たりにした経験が、「集団、集合の作家の集合」という本展のアイデアに繋がったのだろう。繰り返すが、非常に面白いアイデアであって、研究の末に見えてくるというよりも、個人の批評家の直感から出てくるものだと思う。そんな「個人」のアイデアを、人々がどう受け止めるのか興味深いところである。
しかしながら、人は、彼のアイデアに、あまり驚いてない様子だ。展示構成が良すぎるからだろうか。退屈に思うヒマがない。我々観客は作品から作品へと渡り歩き、何も考えず(適度に考える程度で)、楽しんで見てしまい、疲れない。展示作品は、ほんとは別々の場所にあったものなのに、全然反発し合うことがない。例えばChim↑Pomと突然、目の前がひらけては前者がビル解体の「実物」を持ち込み、展示するのに対し、後者は「セット」として橋を再現展示する。一見、真逆に思えるが、どちらも「持ち込めない現実」を扱っており、その扱い方が、両者とも極めて繊細なことが「実物」と再現展示、そのドキュメンテーションよって、端的に伝わってくる。また、両者とも小さなユーモアを忘れない(後者は、「橋」に隣接する大学の壁まで再現しており、ほとんどコントのセットのようであり、そんなところも素晴らしい)。個展ではまず見えてこない、集団、集合が「集合」した時の共鳴が、会場のあちこちでハーモニーを醸し出している。人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)のブースから流れる壮大な交響曲と、DIVINA COMMEDIAのブースから時折響く爆音電子ドローン音楽が、これまた奇妙に会場空間に調和を与えていることに思わず私は微笑してしまったほどである。我々観客は、その緻密な展示構成によって、面白さを味わって(自分の好きなところだけ、気に入った部分だけを見て/読んで)外へ出てしまう。悪いわけでは全然ないが、うまくいきすぎというか、椹木のいう「渾然一体」は、こういうエンタメ的な調和のことではないはずだ。そう、退屈さが欠けているのだ、この『平成美術』展の展示構成には。そして、平成とは、極めて「退屈」な時代ではなかったか。

Chim↑Pom 展示風景(Photo: Kioku Keizo)

突然、目の前がひらけて 灰原千晶、李晶玉 《区画壁を跨ぐ橋のドローイング》 2015年

人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)《S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら》 展示風景(Photo: Kioku Keizo)

DIVINA COMMEDIA (the council of divina commedia) 展示風景(Photo: Kioku Keizo)
その中で、Complesso Plasticoとパープルームには不思議な退屈さが確保されていて、人の流れがスムーズな本展で、人々の足を引っ張る役目を担っていた。私はもっとも好きな展示だった。若い男性裸体を特権的に展示し、バブル(CP)や不況(パープルーム)という時代的な影響を丸出しにした果敢なインスタレーションでまとめ、「NEW」(CP)や「ぱぁ〜にゃ〜」(パープルーム)といった無意味な、しかし、妙な自信を感じさせる行き場のないメッセージを頭上に掲げるといった、世代を超えた類似点は、ミステリアスに会場を(地味に)活気付けていた。

Complesso Plastico《C+P 2020》 2020年 展示風景(Photo: Kioku Keizo)

パープルーム 展示風景(Photo: Kioku Keizo)
物理的に人の流れをせき止めていたのは、資料展示のカオス*ラウンジだ。文字どおり袋小路のような展示スペースだったからだ。カオス*ラウンジの試みは、その演劇的な展開、美術業界の制度への反抗という点でテクノクラートと共通点があると私は思うが(テクノクラート/飴屋法水の1991年/平成3年のソロ作品《ジャパニーズソング》(部分)は黒電話の受話器から、電話回線によって収集された台詞がテンポよく漏れ聞こえ続ける傑作で、カオス*ラウンジにそのまま繋がる)、今回のテクノクラートの方がカオスなラウンジを作り上げていた。

カオス*ラウンジ 展示風景(Photo: Kioku Keizo)

テクノクラート 展示風景(Photo: Kioku Keizo)
会場配布の全作解説ハンドアウトに美術館側の執筆として言い訳「本展では当初、東日本大震災前後のかれらの活動を回顧する展示を計画していた。しかし、カオス*ラウンジの組織内のトラブルにより実現が困難となったため、ここに『カオス*ラウンジ宣言2010』を資料として展示する」と書いてあったが、そんなの認められない。というか、足りないっつーーーの(怒)。「資料展示」というのなら、我々観客のために、もっとちゃんと展示しろ。カオス*ラウンジを模倣して椹木チームでゲリラ的に、そして過剰に情報を投げ込み、アクロバティックにやればよかった。この「資料展示」は、ギリギリの折衝の中で実現したことに意義があるとしても、椹木野衣らしくないと私は思う。アイデアが足りないからだ。そして資料が足りない。「悪い場所」を自分らで作ってどうする。ガンバ!
ともあれ、本展は国内でも巡回がない。この場所に見に来るしかない。あと数日しかない。図録で満足しようと思わず、見逃すべきではない。
付記:
「図録で満足しようとせず」と本文の最後に書いたが、松本弦人の装幀は素晴らしい。旧態依然な図録を無視し、書籍の存在感がちゃんとある。「ブックカバーが消える」工夫はやられたと思った。うらやましい。

展覧会図録 編集:水野良美(京都市京セラ美術館)+望月幸治(世界思想社) デザイン:松本弦人
ふくなが・しん(小説家。京都造形芸術大学芸術学科中退)
※『平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989-2019』展は、2021年1月23日~4月11日まで京都市京セラ美術館 東山キューブで開催された。