文壇の末期的状況を批判する
文:福嶋亮大
2018.08.18
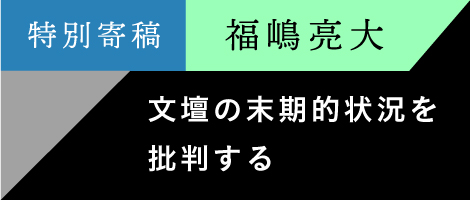
福嶋亮大
どいつもこいつもナメとんのか――、少々下品だが、これがここ数ヶ月の文壇の醜態を目の当たりにした、私の偽らざる感想である。言うまでもなく、早稲田大学教授の文芸批評家・渡部直己のセクハラ事件を端緒にした一連の騒動、および芥川賞候補作になった群像新人賞受賞作である北条裕子「美しい顔」をめぐる盗用疑惑を指してのことである。それぞれについて私見を述べる。
私はほかならぬこのRealkyotoで渡部直己とは対談したことがあり、今回の騒動の直前には彼に代打を頼まれて、福永信とのトークショー@芦屋市立美術博物館に急遽出演したくらいで、以前からかなり親しい間柄である。彼の女性遍歴についても知らないわけではないけれども(近年はそちらの方面は「卒業」したのだろうと思い込んでいた私の認識は甘かったのだが)、そこはプライヴェートな領域に関わるので触れるべきではないだろう。一般論として、男女の問題は外野にはうかがい知れないところがあるし(この曖昧さがハラスメントの温床になることも重々承知しているが、かといって曖昧さを抹消することもできない)、部外者の私には確かなことは言えない。明らかなのは、渡部がこの一件で早稲田の教授としての地位も批評家としての名声も失ったということであり、類似の案件と比べても、十分に大きな社会的制裁を受けたと私は考えている。
もとより、騒動後も渡部と数度メールをやりとりした私は、一連の報道をすべて鵜呑みにするつもりはない(ちなみにインターネットで「疑惑」が報道された直後に、某文学賞の授賞式でさっそくMe Tooをかざして報道に便乗した作家がいるとも伝え聞く――これが事実だとしたら一般論として軽率であるばかりか、後述するように文学者の振る舞いとしても大きな問題だろう)。もちろん、女性を性的に侮辱することは許されないが、その一方で報道された側にも反撃する権利はある。この「セクハラ疑惑」を最初に報道したプレジデントオンラインも、渡部のせいで女性大学院生が退学に追い込まれたとセンセーショナルに報じ、結果的に彼の首をとるまで事態を追い詰めたわけだから、仮に歪曲的な報道があったとしたらタダでは済まない。

2018年6月20日付プレジデントオンライン
ただ、ここでより問題なのは早稲田側の対応だろう。プレジデントオンラインの記事を読むと、まるで渡部の属する早稲田の当該コースが、組織ぐるみで被害者の女性大学院生を口止めし、問題をもみ消そうとしたかのような印象を受ける。そして、そのコースに文芸誌『早稲田文学』の編集委員や名の知れた作家がいることは、文芸業界では周知の事実である。こうなってくると、読者は渡部個人の問題を超えて、大学ひいては文壇の体質にこそ大きな問題があるという考えに誘導されざるを得ないだろう。
したがって、問題はもはやセクハラがあったかなかったかというだけに留まらない。大学さらには文壇の中枢にこそ、悪しき政治的な「隠蔽体質」があるというアングルが報道によって形作られてしまったのだから。とりわけ文学は、そのような自己保身や隠蔽体質に対抗する存在として長らく自己規定してきたのだから(文学史的に言えば、世界を覆う幻想のヴェールを切り裂き、ときには社会的な虚偽や不正をも暴こうとする「リアリズム」がその一つの対抗原理である)、これは大打撃――というより存在理由の否定に近いだろう。もし報道通りに組織的にもみ消そうとしたのであれば、責任者は被害者の女性に苦痛と損害を与えたその非を公的に認めるべきだし、もし報道がデタラメないし部分的にでも事実を歪曲しているのならば、毅然として反論するべきである。そもそも、当該コースのスタッフは学部の「文芸・ジャーナリズム論系」にも関わっているのだから、ここで範を示さずしてどうするのか? 逆に、今の曖昧さを漫然と維持する限り、大学や文学への信頼がめちゃくちゃになった、そのむざんな焼け野原が残り続けるだけだろう。事実を伝えると称する報道とは別のアングルで、文学者や大学人としての責任のもとで所見を提示するべきではないのか。
それに、この種の大学のセクハラ事件は当事者にとってはきわめて深刻である反面、第三者には往々にしてコメディかカーニヴァルのように面白おかしく観察されがちである(南アフリカを舞台に大学教師のセクハラ事件の顛末を描いたクッツェーの小説『恥辱』は、このコメディ的な一面を正確に捉えており一読に値する)。今回も恐らくその例外ではない。しかし、このコメディ的/カーニヴァル的な「価値の暴落」は、誰かが食い止めなければどうしようもない。ちょうど、娘を殺された母親の怒りがあらぬ方向に文字通り「飛び火」し逸走していく映画『スリー・ビルボード』――『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の批評的なカウンターパートとして見ても面白い――さながら、昨今では火元以上に、延焼地帯のほうに深刻な問題の生じることが多い。そして、この「スリー・ビルボード的逸走」のなかで、延焼したジャンルの信頼や価値はめちゃくちゃになってしまうのだ。
とりわけ、今回のプレジデントオンラインの報道は『早稲田文学』に関わる男性教員も強く非難しているため、この雑誌そのものが事件の当事者たちと限りなく同一視されつつある。実際、疑惑が出た直後に『早稲田文学』編集委員の藤井光はその職を辞し、以前『早稲田文学』で女性特集号を企画した川上未映子も声明を出すに到った。しかし、問題なのは、この『早稲田文学』および当該コースの中心的存在であった市川真人である。もし市川が一連の報道は(全面的であれ部分的であれ)デタラメないし誇張であり、真相は別のところにあると考えているのであれば、細部の検証はさておき、その旨をいち早く公式的に表明するべきだっただろう。それだけでも印象はずいぶん違ったはずだ。渦中の渡部が声明を出すのは難しかっただろうが、市川にはそれをやる責任も能力も場所も情報もあった(それは一方的なマスコミ報道にさらされた渡部を守ることにもなっただろう)。しかし、彼は「大学の調査が入るから」という建前のもとで、報道を認めるでも否定するでもなくノラリクラリとしているだけだ。それは結果的に「無責任の体系」を助長することにしかならないだろう。
さらに、今回いち早く『早稲田文学』の編集委員を辞任したアメリカ文学者の藤井光の対応にも、大きな問題がある。抗議のためにやめるというのは結構だが、まず彼のなすべきことは、その理由をきちんとステートメントとして示すことではないのか。伝統ある文芸誌の編集委員ともなれば、文学およびその読者に対して相応の責務がある。だというのに、藤井はツイッター上で♯WeTooというハッシュタグをつけて辞任を表明しただけだ(私はだいぶ前からツイッターを見ていないので信頼の置ける編集者に教わり調べてもらった――それにしてもWe Tooって何ですか?)。これではすべての責任を投げ捨てて、泥舟から逃げただけだろう。こんなふざけた話があるだろうか?
これは全体から見れば些細な事例ではあるし、いずれ藤井はしかるべき場所で何らかのステートメントを出すと私は信じているが、今の文学の体質を象徴していると思われるので、あえてもう少し掘り下げておく。そもそも、Me TooといいWe Tooといい、それらは他者の苦痛の物語に対して私(たち)の苦痛の物語を重ねようとする言明である。しかし、エドワード・サイードや柄谷行人を参照するまでもなく、一昔前の人文知の世界では、他者を代表=表象することには強い警戒が発せられていた。他者を「私」の名のもとに安易に我有化してはならない――それが人文知の基本的な倫理であったはずである。あるいは一九九五年のオウム事件の折には、他者の作った物語に自分を委ねることに対して、やはり強い抵抗があったことを思い出してもよい。もし今の日本でオウム事件が起こっていたら、We Too はもちろんMe Tooという言い方もこれほど流行らず、どこかで抑制が働いたはずだ。
しかし、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」の喩えよろしく、今やそのような基本的な問題設定は雲散霧消し、文学者が見も知らない他者の人生に自分を重ねあわせ、自己の出処進退すらハッシュタグに代弁させるという恐るべき時代がやってきたわけだ。「一般大衆や社会運動家ならいざしらず、文学者のくせにハッシュタグなど使うな!」と言いたくもなるが、これはもはや時代錯誤の考え方なのだろうか? だとしたら、それはしかし、時代のほうが間違っていると言うべきだろう。
もちろん、私は時と場合に応じてMe Tooあるいは「個人的なことが政治的なことである」というラディカル・フェミニズムのテーゼが有効であることを認める。これまで忍従を強いられてきた被害者がネットによって声をあげ、似た被害を受けた女性からの支援を集め、無作法なエロオヤジをあらかじめ牽制できるようになったのは、大前提として歓迎すべきことだろう(恥ずべきことに、日本における女性の地位はいまだに後進国レベルなのだから)。だとしても、それを乱用すれば当然さまざまな弊害も生じる。そもそも、我々は近代社会に生きている以上、原理原則として「私」と「公」を短絡させることには慎重でなければならない。この原理原則を忘れると、政治家や芸能人の「私的」な不倫のようなゴシップを「公的」な問題として大騒ぎする前近代的な「世間」と変わらなくなる(この点は小林よしのりの『新・堕落論』が阿部謹也の『「世間」とは何か』を引きながら明快に語っている)。Me Tooもあくまで緊急手段であり、それが常態化すると、私的領域が告発のリスクだらけになって、がんじがらめになりかねない。さらに、被害を訴えた側が、逆に名誉毀損で反撃される可能性も懸念される。
いずれにせよ、改めて繰り返せば、文学者ともあろうものがホイホイMe Tooなどと言って、他者の人生に「私」を重ねていくのは、たとえそれがどれだけ政治的に正しかろうと、文学者としては間違っている。Me TooだろうがWe Tooだろうが、気軽に使ってよい言葉では断じてない。たとえ支援の意志があったとしても、他者の人生の苦難に対して「私(たち)も同じ」と乗りかかるのは基本的に傲慢なことである。文学は本来、そのような共感の危うさを――つまり一見して優しげな善意のもつ罠を――教えるためのものである。言い換えれば、文学とはMe Tooと言った瞬間に消えてしまう繊細なものを捉えるための表現手段である。このシンギュラー(単独的)なものの手触りを抹消したとき、文学はポリティカル・コレクトネスに――つまりわざわざ文学的な装置を使わずとも言える道徳的な言葉に――還元されるだろう。それは文学の自殺にほかならない。
以上と同根の問題が「美しい顔」をめぐる盗用問題にも言える。この小説は東日本大震災の被災地を舞台にしながら、そこでマスメディアのアイコンに祭り上げられた女性の被災者の呪詛や戸惑いをテーマとしたものである。「美しい顔」とはそのマスコミの作った虚像を指している。作品は一貫して、この主人公のきわめて感情的な語りに沿って進められる。彼女はマスコミに嫌悪を抱きつつも、その「美しい顔」という物語に誘惑されるが、母の死に直面し、年長の女性に諭されるなかで、最後にはそれとは別の地平へと出ていこうとする――およそこういう趣向の作品である。
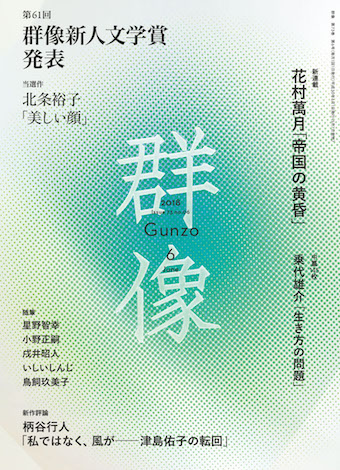
「美しい顔」を掲載した『群像』2018年6月号

この小説の後半部において、いくつかの既存のノンフィクションからの剽窃があるとしてメディアでは話題になった。それはそれでもちろん大きな問題だが、より深刻なのは、このような作品を許容した文壇の「風土」のほうである。作品の内容に関連させつつ、大きく三つの問題点をあげよう。
第一に、表象の難しさに対する謙虚さの欠落である。もとより、巨大な震災や被災体験を「表象」するのは、ほとんど不可能なことである。にもかかわらず、メディアは往々にして被災地に無遠慮なカメラを向ける。「美しい顔」もまた、マスコミの出歯亀的な視線に対して、被災者の主人公が苛立ちに満ちた呪詛を向けるシーンから始まる。むろん、このようなマスコミへの呪詛自体がきわめて凡庸なものだとしても、問題設定自体は分からなくもない。しかし、最大の問題は、作者の北条自身がセンセーショナリズムやセンチメンタリズムからほとんど距離をとれていないことである。特に、主人公が母の死骸を前にして大泣きする場面などは、その典型だろう。
表象不可能性をめぐる思想的なテーマは、私も勤務先の大学で必ずレクチャーする。ヒロシマやアウシュヴィッツは絶句せざるを得ない出来事である。かといって、ただ絶句するばかりでは、その出来事はいずれ「忘却の穴」に落ち込み、下手をすれば歴史修正主義の餌食になるだろう。したがって「表象不可能なものをいかに表象するか」という難題が原爆とホロコースト以降の表現者には課せられている……。このような講義をすると、必ずこのテーマを東日本大震災後の日本と関連づける学生がいる。例えば、毎月被災地にボランティアで通っている学生は、行けば行くほど被災を言葉にすること、つまり表象することの難しさに直面すると言っていた。これがごくふつうの良識的な反応だろう。
しかし、「美しい顔」はそのような「難しさ」に直面しているとは到底言えない。それどころか、被災者の主人公に、自らの幼稚な感情をひたすら饒舌に語らせるばかりだ。だが、震災をこのように饒舌に物語化するのであれば、いったいマスコミと何が違うというのか。あるいは、被災体験を主人公の感情によって塗りつぶしていくことは、マスコミのセンチメンタリズムと何が違うというのか。主人公が自らの「幼稚さ」を自覚しているから許される、というたぐいの問題ではない。マスコミを批判しつつ、やっていることはマスコミと大差ないのだから、いっそうタチが悪いと言うべきだろう。この作品は盗用以前のところで大きな倫理的問題がある。にもかかわらず、『群像』の選考委員も新聞の文芸時評担当者もそのような基本的な論点に触れていない。これはどういうことなのか?
第二に、社会的現実に対する謙虚さの欠落である。例えば、東京新聞の時評を担当している佐々木敦は、盗用疑惑が出る前に「美しい顔」の「脳内の饒舌」や「言葉の奔流」を手放しで大絶賛し「作者は実は被災者ではないのだ。北条裕子は東京都在住であり、あの日も、あの日からも東京に居て、これまで被災地に行ったことさえないのだという。しかし、それでも彼女はこの小説を書いたのだし、書けたのだ。書く必要があったのだ。このことはよくよく考えてみるにたることだと思う」と書いている。しかし、繰り返せば、そもそも被災体験というのは、決して饒舌やら奔流やらでべらべら語るべきことではない。それに、被災地に行ったこともないというのが、なぜ作品評価においてプラスになるのか。動機が純粋なら許されるのか。佐々木はまず、これらの当然の疑問こそを「よくよく考えてみる」べきだろう。
佐々木のいたずらにセンセーショナルな時評には、今の文壇における、社会的現実に対する謙虚さの欠落がよく示されている。作家の側に書く情熱がほとばしってさえいれば、現実を感情と言葉で塗りつぶそうと、一切お構いなしというわけだ。しかし、それは常識的に考えてもおかしいだろう。そもそも、私はこれまでも、文芸系の知り合いの編集者に会うたびに「若い作家のケツを蹴り飛ばしてどこかに取材でも行かせたらどうか」と言ってきた(もちろん編集者が真に受けた様子はなかったが)。作家たちを高い店で接待するくらいならば、アゴアシつけて社会勉強に送り出し、ルポルタージュでも書かせたほうがよほど建設的だろう。世界を知らない作家がアタマを捏ね繰り回したところで、ろくな作品が出てくるはずもない。だったら社会に謙虚に学んだらどうなのか。
といって、私は別にアメリカの若手作家のように紛争地帯を半ば命懸けで取材せよ、などと言うわけでもない。それこそ、Realkyotoの福永信のように、ジャーナリスティックな展覧会評を書き続けるのでも構わないではないか。さらに、誤解のないように言えば、私は「行けばよいものが書ける」などと言っているのではない。強いて言えば「自分が何も書けないことを知る」ために現地に行くべきなのである。しばしば饒舌になりがちなマスコミやジャーナリストに対して、文学や芸術が突きつけるべきなのはこの意味での「現実」だろう。
もとより、すべての小説がジャーナリスティックである必要はないが、小説家がジャーナリズムとの緊張関係を失うのは大きな問題である。近代小説の原点に位置するデフォーやスウィフトはジャーナリストであり、パンフレティアであった。二〇世紀においてもヘミングウェイやノーマン・メイラーやカポーティはもちろん、ガルシア=マルケスや大江健三郎や中上健次にとっても、ノンフィクションやルポルタージュはその仕事の核心部にあった。しかし、このような近代小説の伝統は、今の日本では途絶えてしまったのではないか。その結果として、今や「現地に行かずに情熱で書いたのはすごい」などという珍妙な批評が飛び出してくるのである(その一方で、日本の一部のジャーナリストには取材対象を妙に縄張り化/権益化したり、現地との近さを権威的にふりかざしたりする向きもある――これは最悪の我有化だろう。文学や芸術はこのような傲慢をうつためのものでもある)。
第三に、感情的文章に対する無防備な礼賛である。稚拙なやり方でぶちまけられた女性の感情を妙に高く評価する向きは、実は今回に始まったことではない。私はたまたま二年ほど前に『群像』の創作合評の座談会で、群像新人文学賞を高い評価とともに獲得したばかりの崔実の「ジニのパズル」を取り上げたが、そのときにも「こういう己の感情だけで世界を塗りつぶしていく作品を、女性の在日コリアンというマイノリティの文学だからといって選考委員一同で両手をあげて礼賛するのはいかがなものかと思う」と編集者には言い、座談会でもそれに近いことを言った覚えがある。言うまでもなく、文学とは作者の感情を無防備にぶちまける媒体ではない。その座談会でも言ったことだが、政治的に正しくない右翼少年の感情をいやになるほど精密に「解剖」してみせた大江健三郎の「セヴンティーン」は、今でも参照に値するだろう。
ともあれ、少なくとも二年前の段階から作品評価のタガが外れ、感情を無防備にぶちまけた作品が「文学」であると、選考委員の側も錯覚するようになっていた。その意味では、今回同じ顔ぶれの選考委員たちが「美しい顔」を大絶賛したことに驚きはない(ついでに言えば、未熟な女性主人公が年長の女性に諭されるという点でもこの二作はよく似ている)。しかも「ジニのパズル」にはまだ一応当事者性があるが(だから良いというわけではないにせよ)「美しい顔」はいわば被災者のコスプレをしながら、作者の感情的な昂ぶりがそこかしこで無防備に露出してしまっているところがいっそう問題である(ちなみに、被差別者や障害者をトリガーにして愛だの美だの救済だのを雄弁に語るのは、それこそ渡部直己が一貫して批判してきた文学上の差別のトリックである)。この二作は少なくとも、これまでの批評的な基準においては、決して評価されるタイプの作品ではない。では、どこでどう評価基準が変わったのか。旧来のパラダイムを超克するほどの何かがあるのか。作品を熱狂的に礼賛していた選考委員たちには、そのあたりをきちんと説明していただきたいと思う。
このように、「美しい顔」およびそれを評価した文壇の風土には(1)表象の難しさに対する謙虚さの欠落(2)社会的現実に対する謙虚さの欠落(3)感情的文章に対する無防備な礼賛が認められる。そして、この文壇の祭り上げた新人作家の作品に盗用疑惑がかけられたわけだから、まさに目も当てられない末期的状況と言うほかないだろう。言うまでもなく、この三つの罠を自覚していれば、そもそも盗用ないしそれに類することは起こらなかったはずである。今回の事件は外部からは突発的なものに見えるだろうが、私に言わせれば、ここまでの長年のサボタージュの累積の結果として起こるべくして起こった事件にすぎない。その意味では、盗用をめぐる講談社vs新潮社の対立もまた見せかけのものである。文壇の醸成してきた「空気」は、新潮も決して無関係ではないのだから。
もっとも、作者の名誉のために言っておけば、「美しい顔」という作品そのものは(これまでの批評的な基準では評価できないとはいえ)最近の他の新人賞受賞作と比べてとりたてて不出来ということはない。私とて、仮に自分が選考委員であり他に良い作品がなければ、「美しい顔」を留保つきで推した可能性はある。繰り返せば、問題の本質は、作者本人というよりは「選考委員絶賛!」などという色をつけて過剰に持ち上げた側、つまり文壇の風土にある。安易なプロパガンダに走る前に、良いところも悪いところも含めて、選ぶ側がきちんと分別を働かせるべきだという、至極当たり前のことを私は言っているだけである。しかし、文壇のエスタブリッシュメントの「良識」こそが今は崩壊しているのだ。
そもそも、仮にも文芸誌の選考委員であるならば、それまでの思想的な問題設定を踏まえておくべきだろう。特に、震災をテーマにした作品に相対するならば、なおさらである。しかし、それも忘れてそのつど場当たり的に新人作家を絶賛するだけならば、ただの無責任な宣伝屋と変わらない。今回の『群像』でも、総じて熱烈な選評が目立つし、本来そのような熱狂のストッパーになるべき選考委員の高橋源一郎や多和田葉子もたいして機能していない(ちなみに高橋は一九八〇年代に、それこそ「美しい顔」のような饒舌を断ち切られた失語症的状態から、小説を書き始めた作家である。むしろその当時の問題設定のほうが今は大切なのではないか)。思うに、SNSの流行以来、ネガティヴ・キャンペーンも含めて「言葉の宣伝的・広告的使用」に対するひとびとの抵抗はずいぶんと失われてしまった。それは文壇も例外ではない――文学は本来そのような使用への抵抗こそを組織するものであったはずなのに。
言うまでもなく、選考委員の仕事とは、ある程度一貫した判断基準のもとで対象作品を冷静に分析し、その結果を読者および作者に対して開示することである。作者からの反論にも開かれた理知的な分析がなければ、選考におけるフェアネスも確保できない。新人賞の選評が今やそのフェアネスを失い、プロパガンダに堕しつつあるのだとしたら、これは非常に由々しき事態だと言わねばならない。ちなみに、盗用を指摘された『群像』編集部は、なぜか逆ギレ的に開き直ってネット上で「美しい顔」をしばらく全文公開していたけれども、本当に必要なのは新人賞の審査の体制をもっと謙虚に見直すことだろう。さもなければ、今後も似たような事例は避けられまい。
それに輪をかけてひどいのが、新聞の文芸時評である。先述した佐々木敦も昔から問題が多いが、産経新聞の石原千秋に到っては「美しい顔」について「これは極めつけのフェミニズム小説なのだ。「北条裕子」は、何を言っても何をやってもその「美しい顔」によって意味づけられてきたにちがいない。たとえば、悪意さえも。「北条裕子」は、それを「美しい顔」の内側からずっと見てきた。これが、震災報道に関して言う「なにか得体の知れない不快なもの」の正体にちがいない。これは本人さえも知らないことだろう。それでいて、「北条裕子」のポートレートは「私を買ってください」と言ってはいないだろうか」として大絶賛(?)する始末である。こんなセクシズムまがいの文章が新聞で堂々とまかり通っているのだから、もはや唖然とするしかない。今回の盗用疑惑が、少しでも彼らの反省のきっかけになることを願うばかりである。
振り返ってみれば、ここ数ヶ月の日本では日大や東京医科大、さらには財務省、文部科学省、政権中枢に到るまで、エスタブリッシュメントの横暴と無責任さは目に余るものがある。それは実は文学もたいして変わらない。日頃はカネと名声のうまい汁を吸っておいて、いざとなったときに誰も責任を負わない――、こういう「無責任の体系」が常態化しているのだ。とりわけ、文学では文芸誌の編集委員、新人賞の選考委員、そして新聞の時評担当のような責任あるポジションにいるひとびとこそ、自己反省能力を欠いているのである。そして、文芸批評もまた今や業界に対する「あいさつ」にまで落ちぶれ、まともに機能しない。多くの編集者もまた「あいさつ」のうまい書き手を欲しているだけなのである。美術界とて、似たような状況にあるのではないか(例えば、東京都現代美術館における会田誠の作品撤去問題には、結局どういうオトシマエがつけられたのだろうか?)。
いずれにせよ、ここ最近の文壇の混乱は決して偶発的なものではない。反省的な自浄作用が働かなければ、早晩似たようなことは起こるだろう。私は文芸批評家を自称してはいるけれども、文芸誌では特段大きな仕事をしたことはないし、今後もその予定も意志もないが、今のように「責任ある大人たち」が文学をめちゃくちゃにし、しかもそのことをまともに自覚すらしていない現状を放置するのも無責任かと思い、この文章を記した。そもそも、こんな火中にわざわざ手を突っ込むような文章など、誰が好き好んで書くだろうか? それでも後世のためには、この状況への怒りをあえて形にしておくべきだと思ったわけだ。というわけで冒頭の言葉を繰り返そう――どいつもこいつもナメとんのか!
(2018年8月18日公開)
追記(2018年8月21日)
このエントリが案の定、ツイッターで炎上しているそうです(僕はツイッターをまったく見ていないので、実は昨日まで知らなかったのですが)。余談から入ると、昨今は何かにつけて「◯◯が炎上中!」と気安く触れて回るネットユーザーがいます。しかし、これは事実上「もし◯◯を擁護しようものならばお前も一緒に燃やすぞ」という周囲への脅しや恫喝と同じこと。スティグマ化して「村八分」にするメカニズムそのものです。こういう村社会的なアングルを作られたら、ふつうのひとはもう何も言えません。恐ろしい時代になったものです。
さて、プレジデントオンラインの報道内容については恐らくいずれ再検証の動きがあるでしょうから、読者はそれを読んで改めて判断してくださればよいでしょう(ちなみに渡部を擁護した福嶋はケシカランと言って一部で怒られているようですが、このエントリをそう読むのはさすがに曲解というものです――そもそも渡部を擁護する/しないというのは論の主眼ではありません)。僕から言えるのは、セクハラのようなデリケートな話題に対して、真偽不明のインターネット記事の情報だけを鵜呑みにして飛びつくのは極力控えたほうがよいという、ごく当たり前のことです。Me Too運動の盛り上がりも、今やメディアの歪曲的報道の作成や拡散に「利用」されかねない危険な一面がある。僕はそのことを強く懸念しています。そして、大学の査問の公平性も、今やネットの報道やネットの世論によって――さらにはそこから波及した「世間」の処罰感情のインフレによって――失われつつある。言うまでもなく、ネットは裁きの場ではありません。にもかかわらず、その圧力は現実の裁きに大きな影響を与えている。ネットがかくも強い「権力」をもっている以上、せめて言葉を扱う文学者くらいは、その力の行使に徹底して慎重になるべきでしょう。将来、冤罪でひとが自殺してからでは遅いのです。
他方、大上段から文学について語る、その態度そのものを否定する向きがあるとも聞きました。これはたぶん若い世代の反応なのでしょうが、そもそも「文壇」とは本来は「文学とは何か、何をやるべきか、何のためにあるのか、何ができて何ができないのか」等々のメタ的な問いを、実作や評論や翻訳や座談会等々によって組織していくためのコミュニケーション空間です(そして、その内実を検証するために「新聞の文壇時評」というものもある)。もちろん、これらの問いに一つの答えなど出せません。これらはむしろ、不断にアップデートしていくべき問いなのです。だからこそ、各々が自分の文学観を持ち寄り、ときにはぶつけあって、多事争論でワイワイガヤガヤ楽しくやればよい。その場を「文壇」と呼ぶのです。しかし、今はその場が機能せず、たんなるプロパガンダの集積になっているではないか――、それが僕の批判の骨子です。
もちろん、文芸誌と芥川賞を中心とした文壇のシステムそのものは、すでに明らかに賞味期限切れです。しかし、かつて文壇が担っていたはずの、そのような文学的コミュニケーションは「遺産相続」する価値がある――これが僕の物書きとしての判断です。だからこそ、僕は文芸誌とはまったく関係のないところで、香港の張彧暋氏と往復書簡を出し、PLANETSで特撮論をやり、本来は美術評論を主体としたRealkyotoに間借りして檄文を書いているわけです(ちなみにエントリでも記したように、近代初期の文学者はパンフレティアでもありました)。これらは一見して文学とは関係ありませんが、僕にとってはすべて文学の延長線上にあるものです。
今の二〇代の読者には、文学的コミュニケーションそのものがすでに無価値なものに見えているかもしれません。そのせいで、大上段から文学を語ると、それだけで暑苦しくて偉そうでウザいという反応にもなる。しかし、それは結局、ここまでの文学者の怠慢がそうさせただけです。だからこそ、文学や芸術を必要とする大人のみなさん、これを機会にもう一度初心にかえってじっくりやりませんか――、このエントリは語調こそ攻撃的ですが、本来はそういう呼びかけが根っこにある。表面の攻撃性はただの囮にすぎません。こういう言外の落ち着いたメッセージこそを、一人でも多くの読者が読み取ってくれることを願っています。
ふくしま・りょうた
1981年、京都生まれ。文芸批評家。立教大学文学部准教授。著書に『復興文化論 日本的創造の系譜』(青土社、サントリー学芸賞)、『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』(青土社、樋口一葉記念やまなし文学賞)、『辺境の思想 日本と香港から考える』(文藝春秋、張彧暋との共著)、『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』(PLANETS、近刊)等がある。