文化時評7:伊庭靖子展@イムラアートギャラリー
対峙と注視の彼方へ
文:清水 穣
2022.12.14
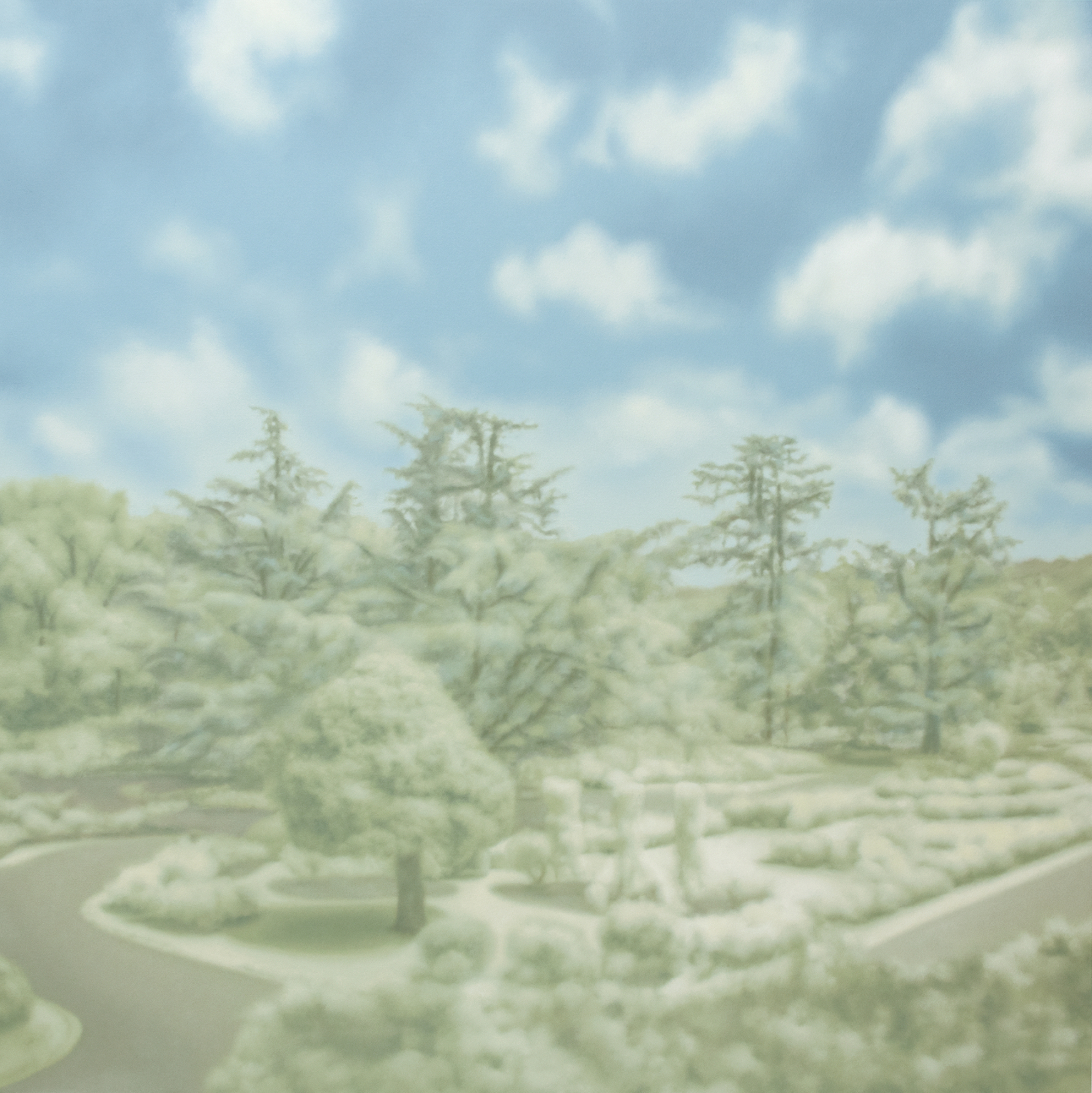
ドイツロマン派の詩人、ノヴァーリスは「すべての見えるものは見えないものに接している」という断章を遺している1 。視覚を超えた何かに「接触している」という触感こそ、伊庭靖子が探求する「質感」のことである。伊庭のこれまでの創作とは、この「質感」の変化にほかならない。
質感は、果物やクッションといった描かれた物の質感ではない。例えば、1990年代後半までの初期作品は、ゲルハルト・リヒターを参照しつつ、局所的にピントの合った、果物やジャムの接写写真を出発点に、輝くハイライトを散らして画面に瑞々しい透明感を漂わせるものだった。つまり、この時期の作品が表現する「質感」とは、映像的な透明感であった。
2000年代に入り、写真的な透明感=質感に飽き足らなくなった作家は、柔らかな間接光から生まれる質感を描き始める。光の反射とハイライトは姿を消し、間接光と落ち着いた色彩のなかで、顔をうずめたくなるようなクッションやソファのシリーズが次々と描かれた。やがて刺繍クッションを契機に、作家は、膨張色の効果によってふくらむ物を、刺繍の曲線がそっと押さえる、その二つの力の拮抗から質感が生じることを発見する。それは「布地の上、柄の下」で発生する、と。その派生形として、「生地の上、釉薬の下」に描かれる染付の磁器のシリーズが生まれた。初期作品の透明感が再導入されたように見えたが、透明な質感への没入はすぐに、次のスタイルに取って代わられた。
2010年代、作家はいわゆる視触覚的な質感から離脱し、質感が生じる場所が、見る人の内(心の中、脳内)であることを意識するようになる。人は質感を脳で「見て」いる、と。では「見る」とはどういうことなのか。白や半透明の幕の隙間からこちらを覗き見る器の絵、画面全体に及ぶガラスの乱反射によって虚像と実像が交錯する透明な空間のなかから1つの器がこちらを見返している作品、さらに一つの器が己の虚像と対峙しているような作品等々のシリーズは、われわれを美しい乱反射の中へ没入するよう誘うものではない。作家の関心は、絵画を「見る」ことにあり、その危うさ(何も見えていない)と確かさ(すべて見えている)のあいだで、作品は緊張感のあるバランスを保っていた。
2019年、それと並行してシルクスクリーンによる独創的な点描版画が開発される。点描とは、色の彩度を落とさないために、絵具を混ぜずに微細な点々にして隣り合わせると、見る人の脳内で色々が混ざって見えるという技法である。伊庭流の点描では、極小の非円形の点々を刷り並べて色彩を満遍なく混色させる結果、全体はグレーになる。実際に刷られているカラフルな描点は小さすぎて見えず、現実には存在しないグレーのほうが見えるのだ。それは、最初期の写真がもつ不思議な遠さに通じていた。
 点描版画が切り開いた「遠い」「風景」の延長線上に生まれたのが、最近作の風景画のシリーズであり、それが伊庭の現在地である。点描の風景は、眼ではなく脳内に立ち現れる風景であった。淡い緑と空色が特徴的なこれらの風景画は、赤外線カメラで撮影した風景に基づいている。つまり可視光線の外で見える世界の姿である。可視の外、つまり目を閉じて見える風景とは、夢の中、眠りの中に現れる風景であろう。この風景を「見る」視点は、この風景の外には存在しない。このシリーズがどこかシュールリアリスティックに見えても不思議ではないだろう。それは、思い出すことのなかった記憶の風景のようであり、これから眼にする風景のようでもある。そこでは絵画の質感は、記憶と予感を呼び覚ますべきものとして現れている。
点描版画が切り開いた「遠い」「風景」の延長線上に生まれたのが、最近作の風景画のシリーズであり、それが伊庭の現在地である。点描の風景は、眼ではなく脳内に立ち現れる風景であった。淡い緑と空色が特徴的なこれらの風景画は、赤外線カメラで撮影した風景に基づいている。つまり可視光線の外で見える世界の姿である。可視の外、つまり目を閉じて見える風景とは、夢の中、眠りの中に現れる風景であろう。この風景を「見る」視点は、この風景の外には存在しない。このシリーズがどこかシュールリアリスティックに見えても不思議ではないだろう。それは、思い出すことのなかった記憶の風景のようであり、これから眼にする風景のようでもある。そこでは絵画の質感は、記憶と予感を呼び覚ますべきものとして現れている。
 とはいえ、ある絵画を見るとき、われわれは不可避的にその絵画と対峙し、展示場所に応じて与えられた視点から、目と脳の両方で「見る」のである。その経験を探求するためには、目を閉じて見える風景、視点を欠いた風景が片手落ちであるのは言うまでもない。その欠落を埋めるかのように、Misa Shin Galleryでの個展から、無地の背景に小さな陶器の置物(動物)を1つ描く、一種の静物画のシリーズが始まった(本展にも3点出展)。事実上の最新シリーズであるこれら小品群(出品作2点は初めて試みられた最大サイズ)は、見るべきものが一つに限定された静物画であり、縦位置限定のフォーマットゆえに肖像画のようにも見えるが、描かれた動物たちの正体はときに曖昧で、しかも必ず背を向けている。最大の特徴は距離感、つまり絶妙な余白のとり方である。つややかな質感を帯びた陶器のオブジェは、かつてのように見る者を没入させるほどの面積を占めることはなく、反対に画面全体の中で余計な意味作用(ちっぽけ、孤立して寂しそう等々)を発生させるほど小さくもない。オブジェの足元にかすかに影がつけてあるので、最低限の空間性は表現されているが、その他の余白部分は和紙か土壁を思わせるマットなクリーム色で念入りに、一律に、塗り込められている。われわれは、魅力的な質感をたたえた動物と対峙し、彼らを後ろから注視する。それが絵を見ることの、仮初の、比喩であることは言うまでもない。
とはいえ、ある絵画を見るとき、われわれは不可避的にその絵画と対峙し、展示場所に応じて与えられた視点から、目と脳の両方で「見る」のである。その経験を探求するためには、目を閉じて見える風景、視点を欠いた風景が片手落ちであるのは言うまでもない。その欠落を埋めるかのように、Misa Shin Galleryでの個展から、無地の背景に小さな陶器の置物(動物)を1つ描く、一種の静物画のシリーズが始まった(本展にも3点出展)。事実上の最新シリーズであるこれら小品群(出品作2点は初めて試みられた最大サイズ)は、見るべきものが一つに限定された静物画であり、縦位置限定のフォーマットゆえに肖像画のようにも見えるが、描かれた動物たちの正体はときに曖昧で、しかも必ず背を向けている。最大の特徴は距離感、つまり絶妙な余白のとり方である。つややかな質感を帯びた陶器のオブジェは、かつてのように見る者を没入させるほどの面積を占めることはなく、反対に画面全体の中で余計な意味作用(ちっぽけ、孤立して寂しそう等々)を発生させるほど小さくもない。オブジェの足元にかすかに影がつけてあるので、最低限の空間性は表現されているが、その他の余白部分は和紙か土壁を思わせるマットなクリーム色で念入りに、一律に、塗り込められている。われわれは、魅力的な質感をたたえた動物と対峙し、彼らを後ろから注視する。それが絵を見ることの、仮初の、比喩であることは言うまでもない。

 基本的に同じような風景の同じような色調での変奏である風景画と、モチーフ1つに限定された静物=肖像画 ― 作家の現在地は、条件をミニマルに絞った実験室のようである。冒頭で述べたように、伊庭の絵画は首尾一貫して「質感」を探求し、それを帯びているものの存在と非在のあわいで、それを知覚することの可能性(見える)と不可能性(見えない)のあわいで、制作されてきた。もともと版画出身で、後に油絵に転向した伊庭の油絵は、伝統的な油画とはほぼ無縁の自己流である。絵画と版画、絵画と写真のあいだで独自の油絵を目指すその探求の歩みを登山に例えれば、作家はなだらかな中間地点にいて、次の移行を準備しているようである。
基本的に同じような風景の同じような色調での変奏である風景画と、モチーフ1つに限定された静物=肖像画 ― 作家の現在地は、条件をミニマルに絞った実験室のようである。冒頭で述べたように、伊庭の絵画は首尾一貫して「質感」を探求し、それを帯びているものの存在と非在のあわいで、それを知覚することの可能性(見える)と不可能性(見えない)のあわいで、制作されてきた。もともと版画出身で、後に油絵に転向した伊庭の油絵は、伝統的な油画とはほぼ無縁の自己流である。絵画と版画、絵画と写真のあいだで独自の油絵を目指すその探求の歩みを登山に例えれば、作家はなだらかな中間地点にいて、次の移行を準備しているようである。
——————————–
(注)
1 “Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren.” in Traktat vom Licht, 断章2120。
しみず・みのる
批評家。同志社大学教授
『伊庭靖子展』は、イムラアートギャラリーで2022年12月23日まで開催中。
質感は、果物やクッションといった描かれた物の質感ではない。例えば、1990年代後半までの初期作品は、ゲルハルト・リヒターを参照しつつ、局所的にピントの合った、果物やジャムの接写写真を出発点に、輝くハイライトを散らして画面に瑞々しい透明感を漂わせるものだった。つまり、この時期の作品が表現する「質感」とは、映像的な透明感であった。
2000年代に入り、写真的な透明感=質感に飽き足らなくなった作家は、柔らかな間接光から生まれる質感を描き始める。光の反射とハイライトは姿を消し、間接光と落ち着いた色彩のなかで、顔をうずめたくなるようなクッションやソファのシリーズが次々と描かれた。やがて刺繍クッションを契機に、作家は、膨張色の効果によってふくらむ物を、刺繍の曲線がそっと押さえる、その二つの力の拮抗から質感が生じることを発見する。それは「布地の上、柄の下」で発生する、と。その派生形として、「生地の上、釉薬の下」に描かれる染付の磁器のシリーズが生まれた。初期作品の透明感が再導入されたように見えたが、透明な質感への没入はすぐに、次のスタイルに取って代わられた。
2010年代、作家はいわゆる視触覚的な質感から離脱し、質感が生じる場所が、見る人の内(心の中、脳内)であることを意識するようになる。人は質感を脳で「見て」いる、と。では「見る」とはどういうことなのか。白や半透明の幕の隙間からこちらを覗き見る器の絵、画面全体に及ぶガラスの乱反射によって虚像と実像が交錯する透明な空間のなかから1つの器がこちらを見返している作品、さらに一つの器が己の虚像と対峙しているような作品等々のシリーズは、われわれを美しい乱反射の中へ没入するよう誘うものではない。作家の関心は、絵画を「見る」ことにあり、その危うさ(何も見えていない)と確かさ(すべて見えている)のあいだで、作品は緊張感のあるバランスを保っていた。
2019年、それと並行してシルクスクリーンによる独創的な点描版画が開発される。点描とは、色の彩度を落とさないために、絵具を混ぜずに微細な点々にして隣り合わせると、見る人の脳内で色々が混ざって見えるという技法である。伊庭流の点描では、極小の非円形の点々を刷り並べて色彩を満遍なく混色させる結果、全体はグレーになる。実際に刷られているカラフルな描点は小さすぎて見えず、現実には存在しないグレーのほうが見えるのだ。それは、最初期の写真がもつ不思議な遠さに通じていた。

Untitiled 2022-08, oil on canvas, 194x162cm

Untitiled 2022-09, oil on canvas, 80.3×65.2cm

Untitiled 2022-10, oil on canvas, 80.3×65.2cm

Untitiled 2022-11, oil on canvas, 45.5×33.3cm
——————————–
(注)
1 “Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren.” in Traktat vom Licht, 断章2120。
しみず・みのる
批評家。同志社大学教授
『伊庭靖子展』は、イムラアートギャラリーで2022年12月23日まで開催中。