芸術論の新たな転回 03 平芳幸浩(2)デュシャンはどのように受容された(される)か――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって2(Interview series by 池田剛介)
2017.12.21
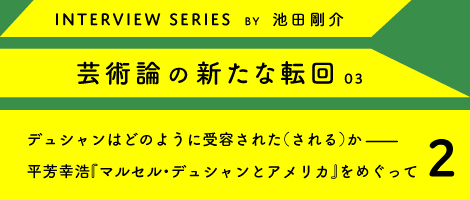
インタビュー:平芳幸浩
聞き手:池田剛介
モダニズムのリミットとそこからの裏切り
池田 ポップ・アートの場合は、様々な立場の人たちを巻き込んでの議論が展開される様がよく見えてきますが、その後のコンセプチュアル・アートの章ではジョセフ・コスースが書いたテクストにフォーカスされています。
平芳 それまでの章では、あまり作家の言葉は取り扱わずに、その周りの批評言語をベースに分析をしていました。コスースの章で彼自身のテクストを扱ったひとつの理由ですが、例えばデュシャンのノートのように、いわゆるコンセプチュアル・アートでは、言語がひとつの芸術表現ないし媒体として用いられます。ですから、コスース自身のテクストをテクストとして読むことと、作品として見ることというアポリアについても考えなければならず、これを正面切って分析しようと思ったわけです。
もうひとつの理由は、50年代から60年代にかけて、ずっとデュシャンの対極にグリーンバーグ的なモダニズム/フォーマリズムの価値観があり、そこからの距離の取り方によってゲームをするように美術が展開していました。しかしコスースのテクストの中には、フォーマリズム的価値観に対して、表向きは正面切って対立軸として措定し、裏側では完全な調停を目指すという、当時のコンセプチュアル・アートにおけるひとつの戦略的な方向性が凝縮されている。そこを読み込んでいくと、戦後の言説とデュシャンの関係を凝縮した形で抽出できる、と考えました。

『マルセル・デュシャンとアメリカ: 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』平芳幸浩=著 2016年 ナカニシヤ出版
池田 グリーンバーグ的な、自己批判を通じた自己純化が絵画や彫刻といったそれぞれのジャンルの内部で発展するモダニズムに対してコスースが言うのは、結局のところそれは美的判断、趣味判断に過ぎないのではないか、そんなジャンル的区分は恣意的に立てられているに過ぎないので、むしろそれを取っ払った上で、芸術において「芸術とは何か」という問いを自己言及的に問わねばならない、と。そういう仕方で、コスースは表向きグリーンバーグを批判するけれど、実際のところ「芸術とは何か」をメタに問うていくという意味では、いわばグリーンバーグ的な自己批判を通じた自己純化というプログラムの延長線上にあるわけで、ここでグリーンバーグとコスースが一致してしまう。
平芳 だからコンセプチュアル・アートとグリーンバーグは別の方向を向いていたわけではなくて、グリーンバーグによる自分なりの理論修正の中でも、コンセプチュアルな部分をどうやって容認していくか、つまり手が問題ではなくて、コンセプションの問題であるという言い方をしたりしていて、これはそのままコスースに焼き直されていると思います。
池田 こうして平芳さんの本を読んでいくと、20世紀アメリカ美術の中で、いかにデュシャンが、それぞれの立場の反映として揺れ動きながら結像していったのかが見えてきます。そして、そうやって辿っていくからこそ、さきほど平芳さんが話されていたような《遺作》による裏切りというのは、極めて謎めいたものとして映るわけですね。あるときは日常性の指標として、あるときは複製性や世俗性のシンボルとして引き合いに出されていたその人が、非常にベタな芸術家的な振る舞いへと転向しているようにも見える。それはデュシャンを師と仰ぐ20世紀芸術に対する裏切りでもあるのかもしれないし、グリーンバーグ=コスース的なモダニズムのリミットを見据えた上で、それとは別の道を提示したように見えなくもない。
平芳 そうですね。《遺作》に関しては、すごくベタな芸術という言い方も当然できると思いますし、逆の見方をすると、極めて自然主義的な立体作品であったという意味で、当時最も芸術的でなかったものと言うこともできます。
池田 しかも手作りだし。
平芳 かつてレディメイドが非芸術的なものであったのと同様に、1960年代末のアメリカにおいて手作りの具象的な立体は極めて非芸術的だった。だから「芸術とは何か」ということが近代の問いだったとすると、デュシャンのノートの中では、ちょっと言葉は違いますが、「芸術でないものを作ることはできるか」という問いが常にある。つまり、やってしまえば何でも芸術になってしまうのであれば、それを逃れる可能性をどう考えられるか、ということを考えていたのだとすると、どうやって逆側にベクトルを伸ばしていけるかという可能性を常に探っていたのではないかと思います。
池田 ベタな芸術家と言いましたが、反芸術的なものが芸術の当然の前提となった時に、そこからの反転をする、いわば反-反芸術なわけで、一周回ってベタな芸術のように見えなくもない。少なくともその捻りが内在している。モナリザにヒゲを描いた《L.H.O.O.Q.》から、さらにそのヒゲを無くした《髭を剃られたL.H.O.O.Q.》なども、そうした内在的な捻りでもあるわけでしょう。デュシャンによるこうした裏切りは、作家による主体的な切断のようにも見えるのだけど、おそらくそれは周囲に築かれてきたデュシャン像に対してどのように振る舞うかという仕方で、相互作用によって成立してもいる。
平芳 正のベクトルが存在しないことには逆のベクトルも存在しないので、常に何らかの関係性の中で蓄積され形成されたものが前提にならないと、この裏切りというものは生まれ得ないでしょう。
池田 そうした前提があってこそ、初めに伺った《遺作》でのしっぺ返しが最大限に際立つわけですね。
造形・プロトタイプ・芸術係数
池田 これまでに世界中で様々な括弧つきの「デュシャン」像が出されていて、さらなる「デュシャン」像を提示してもしかたない、という話をされていました。平芳さんのような迂回的なアプローチを経た上で、ということだと思いますが、今年出版された中尾拓哉さんによる『マルセル・デュシャンとチェス』では、チェスという独特の切り口を通じて、やはりもう一度、デュシャン作品の分析をしようという姿勢が感じられます。デュシャンの沈黙ないし非制作を象徴するとも言えるチェスの中に造形の姿勢を読み込んでいく、トリッキーとも言えるでしょうけれど野心的な問題提起かなと思いました。デュシャン研究者としては、どのように読まれましたか。
平芳 中尾さんが提示されているのは、チェスによってデュシャンを包摂的に読むということで、つまり芸術がまずあってその後にチェスがあるということではなく、デュシャンにとっての大きなものとしてまずチェスがあると。チェスにおいて展開される造形的なありようを美術の中に実験として落とし込んでみようとしていたが、そこに挫折や限界を感じたためにチェスのほうへと戻り、本質的なところの内部でやろうとした、ということが言われているかと思いますし、その観点そのものは正しいだろう、と大枠では感じます。
ただ、すごく率直な感想を言えば、これは別にチェスで語らなくていいのではないかとも思います。つまり彼の思想の根本を探る試みであり、突き詰めていけばデュシャンの中で何が最も上位に来るか、といった問題でしょう。かつて70年代はそれが錬金術だと言われ、あるいはカバラだと言われたこともありましたが、それがこの本ではチェスだと言われている。そう言ってしまえば、すべてが終わってしまう部分はあるかなとは思います。それがいちばん消極的な読みかたでしょう。
そのように思うところもありますが、その上で面白いと感じるのは、先ほど池田さんもおっしゃったように、ある種の造形性のようなところに中尾さんが拘泥している点です。思想々々と言いながら、その背景にあるのは造形だろう、という観点がある。ではチェスにおける造形がどのようなものなのか、ということの言語化が難しいこともあるでしょうし、中尾さん自身がそれほどチェスをやりこんでいるわけではない、という問題もあるかもしれず、いまひとつ明瞭ではないものの、造形性を探ろうとする問題意識に関しては興味深く思います。
池田 デュシャンに関してはレディメイドに代表されるように、手を加えない、ということが言われますが、「造形」という言葉は、ある意味デュシャンの対極にあるように思えます。あえてそういうものをデュシャンのなかに見出していこうとする。
デュシャンのキーワードに「4次元」がありますよね。ここでの4次元とは、僕らが一般的に考えるような3次元+時間というようなものではない、ある種の概念的な空間であり、それはチェスの思考的な空間と比較的容易に結びつく。ある時期のデュシャンにはレディメイドや絵画といった3次元的な作品に対する4次元的チェスへの関心の高まりが見られるわけですが、中尾さんの議論のポイントは、ここで作品に対するチェスの優位を示して終わりということではなくて、チェスをひとつの折り返し地点としながら、もう一度、4次元の3次元化としての造形行為を読み込んでいくところにあると思います。
このあたりの問題意識は、このシリーズで何度か出てきている、エリー・デューリングのプロトタイプ論と、少し通底するところがある気もします。デューリングは、《大ガラス》やメモなどを、理念的空間としての4次元からの部分的切断によって生み出されたプロトタイプとして捉える、といった議論をしています。20世紀美術がおおよそデュシャンに対し、芸術なるもののアイロニカルな掘り崩しを見ていたのに対して、それとは別のアプローチが出てきているのかな、と。
平芳 デューリングのような広い視野での芸術のありかたもそうだし、その反映かもしれませんが、デュシャンをめぐる最近の研究や批評というのは、中尾さんに限ったことではなく、非芸術的な行為も含めてデュシャンの制作であるという観点から再検証して、いったいそこで何が行われ、どのように伝播していくのか、ということを考えようとする傾向があります。そして何をもってその基準とするかが、それぞれの研究者によって違うということになるのでしょう。そういう意味ではデューリングのプロトタイプという考えかたは、今日の話の最初で言っていた創造過程のような一連のプロセスの中で、プロセスの途中であるものが生み出され、生み出されたものがさらに過程を生み出してゆき、そうした動きの中で、作品が点々と存在している、という考え方を現代的に読み直すものとして位置づけできるかもしれません。
池田 創造過程というと単に完成なきプロセスのように聞こえるかもしれませんが、ここでもアクトとプロセスの二重性を強調すべきでしょう。プロセスの中に部分的な切断としてのアクトが具現化した作品があり、そうして生み出された作品が見る者を巻き込みながら、またプロセスを思わぬ方向に展開させることにもなる。まさに《遺作》がそうであったように。
平芳 その二重性で言うと、デュシャンは講演の中で、作家と作品との関係の中にもアクト的な部分とプロセス的な部分があると言っていて、彼はそれを「芸術係数」という言葉で表しています。作品には作者が意図して実現できなかったことと、作者が意図していないにもかかわらず実現してしまったことが必ず含まれています。となると作品と作者との間にもすでに一種の断絶のようなものがあり、そこにもひとつの過程があるという、単純に作者が作品に対して働きかけるのではないような複雑な状況が、この言葉の中に読み取ることができます。

芸術をめぐる制度と経験
池田 先ほどネオダダについて議論した際に言っていたような、芸術と日常との境界を無くしていくという話は、最近では、ボリス・グロイスが直接的に引き受けて展開しているポイントかと思います。
ポストモダン以降、新しいものなんてないと言われて久しいわけですが、でも同時に普通の意味では、新しさ=差異の消費が加速しているようにも見える。グロイスは差異と新しさとを区別した上で、差異には「認識できる差異」と「差異を超えた差異(認識できない差異)」があると言います。認識できる差異とは、例えばiPhone5が6になるように、iPhoneという同じ構造的なコードの中にあるからこそ、その差異がわかるというもの。他方で、差異を超えた差異についてグロイスはキリストの例を挙げています。キリストが現れたとき、人々は彼を普通の人と区別できず、神として認識できなかった。なぜか。それはキリストがこれまでの「神」と共通するコードを持っていなかったから。ゆえにキリストは単なるバージョンアップ版の神ではない、真に「新しい」神であったと。レディメイドの延長線上で、芸術と日常との境界を無くしていく現代美術は、このように認識できない差異を算出しており、そうした日常のものと識別できない差異を認識可能にすることで絶えず真の新しさを産出するのが美術館である、と。
これはデュシャンがもたらした衝撃の延長線上にある現代美術の状況を、その困難さも含めて正確に映し出しているし、グロイスの問い自体が極めてアイロニカルなものであることはわかるのですが、本当にそれでいいのかとも思うわけです。彼の議論では、我々は日常社会において、ひたすら企画書を書き、プレゼンばかりやっており、現代美術でも同様に、企画書を書き、プレゼンをし、その場限りのプロジェクトに従事しており、そしてそれでよいのだ、ということにもなる。
平芳 グロイスの問いに対して僕がどう答えられるかわからないですが、いまお聞きした範囲の中でお答えしたいと思います。そこでいちばん欠落しているのは、経験のフェイズではないでしょうか。決定的に新しいものは、日常の他のものとまったく区別がつかないので、新しいものとして経験しようがない。それを自覚的に共有できないし認知できない。ある制度の中に置けば、その認知が成立するかもしれないけれど、制度によって成立しているということは、それに対する経験が十全に開かれているとは言えないでしょう。
経験って、もっと無責任な部分が大きいと思います。美術館にあるから芸術経験が成立するということでもなくて、芸術的な経験、あるいは「気づき」みたいなものって、芸術と日常との境目とはそれほど関係なく、いろんなところで様々な刺激を受けて、多様な経験が開かれるというものだと思います。いままで芸術と呼ばれてきたものは、その経験の非常に特殊なかたちというか、他とは代えられない経験をもたらすものであったと思うので、それ自体は制度で支えられているものではあまりない。そちら側に立てば、議論はそんなに行き詰まらないのかもしれません。
池田 まったく同意なのですが、そのお話はやや意外にも感じます。平芳さんの本は、芸術が成立するのはそれが芸術と呼ばれるから、といった「芸術」という名指しをめぐる場として近代芸術を捉えるティエリー・ド・デューヴの議論をひとつのベースにしていますよね。芸術をめぐる制度こそが芸術を作る、という話にもつながる気がするのですが……。
平芳 デュシャンをめぐるこの研究では確かにド・デューヴの議論を下敷きにしていますが、私の立場というのは、それをそのまま引き受けるというのではなくて、「誰かが芸術と呼ぶから芸術だ」というような言説は、実は戦後アメリカ美術のコンテクストで成立してこなかった、というものなのです。つまりドナルド・ジャッドは「誰かが芸術だと言えばそれが芸術だ」と言うけれど、それが現実的なレベルで芸術として成立するためには、「誰が言ったか」が頭につくのであって、そこにデュシャンという名前が必要だった。だからデュシャンがいなければ、「誰かが芸術だと言えば芸術だ」という言説はジャッドとしても成立しなかっただろうし、認められてこなかっただろうと思います。「誰かが芸術だと言えば芸術だ」というのは、ある種の権威に寄りかかって成り立ってきただけで、論理的に成立したとしても、現実的には成立はしてこなかった。それは、この本の中で検証しようとしてきたことのひとつです。
池田 なるほど、つまり実際の芸術の現場は、ジャッドが言うような「芸術」という名指しをめぐるゲームというよりも、結局のところ誰がそのような認定を行うかという権威なり、複数の政治的な力のせめぎ合いによって、なかば場当たり的に形成されてきた、と。
平芳 そうです。先ほど言った無責任な経験というのは、そういった生々しい現場形成と完全に切り離されているわけではないでしょうが、個々の経験はもっと無責任に、日々誰しもがあまり自覚をせずにやっているレベルからスタートしていると思います。それを芸術と呼ぼうとしたのがジョン・ケージやフルクサスのやりかたでしょう。しかし、それを美術の中に持ち込もうとすると、やはり齟齬をきたすので成立が難しい。そういった困難さみたいなものがグロイスの議論にも相変わらず引き継がれているのかもしれません。
池田 そうした予想外な経験を無責任に引き起こしてしまう最たるものが、やはり作品なわけでしょう。最近のデュシャン研究は、深遠なる神秘の読解というよりも制作的な営為としてデュシャンを考えることが多いと言われましたが、やはりもう一度、作品という単位について考え直すことが必要な時期に来ているのかとも思います。
箱をめぐって
池田 デュシャンにおける作品という単位について考える上で、箱というのはひとつのヒントになりそうな気がします。京都国立近代美術館での展示シリーズ1回目の際に《三つの停止原器》が出品されていて、これは紐を床に落としてできた偶然の曲線に基づいて3つの定規を作る、というものですが、そのキャプションに「箱に入っている」と何気なく書かれてあるのが印象に残りました。デュシャンは偶然性や不確定性に関心を持っていますよね。先ほどのプロセスの話もそうですが、不確定に開かれていくものを重視していると考えられがちであるけれど、他方ではメモをボックスの中に入れたり、あるいは《トランクの箱》のように、一種のカタログとして作品をコンパクトに閉じたり、ということも同時にやっている。
平芳 1913年の《三つの停止原器》が箱入りだということは、あの展示をやったときに私も振り返ってみて気付いたことですが、実際に本格的に箱に取り組んだのは、その翌年の1914年あたりからです。そのときにノートやスケッチを箱に入れて友達にあげる、ということを実験的にやっていて、それが後の《グリーン・ボックス》につながっていく。
池田 初めて箱詰めが行われたのが《三つの停止原器》のときでしょうか。
平芳 箱の形状が初めて出てきたのは、そのときですね。彼のノートには、箱ではなく「偶然の缶詰」という言葉が出てくるので、それを箱にしてみた、ということから始まっているのかもしれません。つまり偶然を箱の中に入れておく、閉じ込めてしまうということだろうと思います。何かに密封するとか、箱に入れてしまうという欲求は、かなり反復的に出てきています。ここでのひとつのポイントは、彼は本にはしないということでしょう。始まりと終わりをリニアに整理せず、ぶちまけてしまえば散乱するという形状を必ず取る。
池田 本のように束ねられたものではない、断片的なものたちの寄る辺としての箱。
平芳 ノートのまとまりを見ていても、ある意味づけがなされそうなのだけど、他の可能性、つまりこのノートがすべてではなく、実は選ばれなかった大量のものがあって、でも選ばれなかったほうと選ばれたほうの違いがどこにあるかが明瞭ではなく、偶然と必然がないまぜになった一種のプロトタイプとして詰められている。それがまた別のかたちで繰り返されていくような、ある暫定的な形として箱が存在している。
池田 前回千葉さんと話していたときの言葉で言うと、「仮固定」のような作用を箱が持っている感じがします。断片的なメモであれノートであれ、バラバラに散在していて、外に開かれていく可能性を想起させるものでもあるけれど、ひとまずの仮固定として箱の中にまとまってある。
平芳 その意味で、デュシャンは美術館をひとつの「箱」として見ている可能性は大きいです。フィラデルフィア美術館でも、ある種の大きな箱の中に暫定的なまとまりとして自分の作品を入れよう、という欲求が強かったというのもわからなくはない。
池田 なるほど、断片的なメモをまとめた箱と作品の集まる美術館とを重ねて考えること。面白いですね。散り散りになって日用品の中に埋もれてしまいかねない作品群に、かろうじて寄る辺を与えるような仮固定の場としての美術館。グロイスの言うような、文脈の安全圏を長期的に保証する超越的な場とは異なる美術館=箱のあり方として捉えられるかもしれません。
荒川修作と赤瀬川原平
池田 ところで平芳さんは、いま特に日本でのデュシャン受容について研究されているということですが、特にこの作家にフォーカスしたいという存在はいますか。
平芳 いまあらためて取り組みたいと思っているのは荒川修作です。「ダイアグラム絵画」から「意味のメカニズム」に行くのが、彼のひとつのステップであり、そこにはデュシャンとマドリン・ギンズとの、ふたつの大きな出会いがあります。そのときはまだデュシャンと決別していないのですが、その後、建築や身体性のほうへと寄っていくときに、後づけ的に「デュシャンの限界を自分は超えた」という言い方をする。その転換のきっかけについて、メモやテクストも踏まえながら検証していきたい。ひとつには、日本人の作家で唯一と言っていいほど、デュシャンと非常に近く交友していた形跡があること。もうひとつには、いままでの荒川修作のバイオグラフィが、彼自身の法螺と嘘で固められている部分があって二重化しているので、そこを脱神話化する必要があると思っているからです。
池田 そうやって脱神話化しがいのある、少し山師的な対象に惹かれるのでしょうか(笑)。
平芳 それはあるかもしれないですね。
編集部 その場合に重要なのは、「デュシャンを超えた」=「アートを出る」ということではないでしょうか。つまりアーティストじゃなくなるわけですよね。そこをどう考えられますか。
平芳 第一に検証しないといけないのは、荒川が言うところの「アート」とは何か、ということでしょうね。彼は「コーデノロジスト」と名乗るのですが、建築家になったかというと、建築業界からは基本的にあれは建築ではないアートとして見なされている。残されている周りの人たちからするとアートとして考えないと判断の材料がほとんどなかったりするので。彼が「アートを超えた」というときの「アート」を突き止めるのが、いちばん重要なことだろうと思います。
池田 デュシャン-荒川の線はもちろん大きいと思うのですけど、個人的には荒川と同世代の赤瀬川原平とデュシャンの近さは気になります。デュシャンのチェスではないけれど、赤瀬川もある時期から、執筆活動や路上観察をはじめとしてアートの外に出るような活動に行ってしまい、アーティストとしての位置が見えづらいこともある。でも同時に赤瀬川は、匿名性や偶然性といった問題も含めて、デュシャンの持っていた要素をエッセンスの部分で引き継いでいるところがあると思います。しかも単にデュシャンを表面的に利用するというのではない次元で発展させていたりもする。
平芳 実は、そのとおりだと思っています。非常にデュシャン的なことを、デュシャンにはっきり言及しないでやりきった人として、赤瀬川原平はいちばん重要かもしれません。特にデュシャンのユーモアやダダ的な破壊性を、当時の政治的な文脈に引きつけて展開していた。では、なぜ私が赤瀬川原平を展覧会で扱ったり、研究対象にしたりしないかというと、赤瀬川原平はデュシャンのようになろうと思ったり、デュシャンとの距離をこうしようと思ったりした人ではないと考えているからです。かなり直感的にデュシャンに似てしまっているがために、デュシャンと自分との関係について考える必要があまりない。
だから例えば赤瀬川の《模型千円札》を《ツァンク・チェック》や《モンテカルロ債券》との関連で「マルセル・デュシャンと20世紀美術」展に出そうと思えば出せたのですが、それをすることは自分の中では許されない。あれは彼がデュシャンとの距離を考えたり、デュシャンを引用したりすることで作品となったものではない。結果論としてデュシャンの小切手のようなことを彼はやってしまっていて、それに対して真正面から取り組めないのですね。
池田 なるほど、よくわかります。ただ逆に言うと、必ずしもデュシャンに言及しようとしてないにもかかわらず非常に近いポイントを掴んだりしているわけで、いかにもデュシャンを引用しています、というものよりも興味深いと僕は思ってしまうわけですが……。
平芳 作家としては、そういう面白さはよくわかります。ただ研究対象にしてしまうと、あれもデュシャン的、これもデュシャン的というふうに、赤瀬川を矮小化しかねない。どちらかというと私は、もっとデュシャンを利用したかった人たちのドロドロした欲望のようなものが、状況論的には面白いと思うのですね。
池田 たしかに赤瀬川は、デュシャン利用みたいなこと自体から距離を置こうとしていて、例えば荒川の纏ったデュシャン的な神秘性に関して批判的に捉えていたりする。そういったものへの距離の置きかたという点に関しては、例えば『芸術原論』で赤瀬川自身が書いているように、かなり意識的だったと思いますけれど。

日本でのデュシャン受容と翻訳の問題
池田 ところで日本でのデュシャン受容というのは、アメリカ美術における言説的なダイナミズムともまた違うと思うのですが、いかがでしょうか。戦前の瀧口修造と山中散生それぞれによるデュシャン紹介や、あるいは戦後の東野芳明と中原佑介それぞれのデュシャン解釈について論文を書かれていますよね。
平芳 日本におけるデュシャンの歴史は、瀧口修造からはじまって、戦後、東野芳明に引き継がれる、という典型的なストーリーがある。この物語を、もう一度見直して相対化しよう、というのがひとつの動機です。戦前であれば山中散生の存在を、戦後だと中原佑介のテクストを見直すことによって、滝口・東野ラインとして必ずしもすべてが完結していたわけではなく様々な受容の可能性があったことが見えてきます。
戦後だと例えば宮川淳と針生一郎、それから藤枝晃雄が重要でしょう。最近ようやく藤枝晃雄の批評選集が出て、書評を書く必要もあって読んでいたのですけど、藤枝さんはもともと学部のときにデュシャンを研究して、ペンシルヴァニア大学へ行ってデュシャンにも会い、でもそこからグリーンバーグを知ってフォーマリストになってゆき、それに伴いデュシャンを否定していく、という道筋があります。この流れはきちんと押さえていく必要があり、60、70年代の批評言説の中でデュシャンがどう乱反射していくかも見ていかなければと思っています。
編集部 日本での受容ということでは、翻訳の問題はどうなるのでしょう。
平芳 翻訳の問題が大きいというのはありますよね。デュシャンの言葉にまつわることで言うと、藤本由紀夫さんと僕との間でも、ずっと折り合いがつかないまま進んでいる《泉》の翻訳の問題や、あるいは、通称《大ガラス》のタイトル、《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》という訳もおかしいと、しばしば議論になります。
池田 《泉》の翻訳の問題とは、どういったものですか?
平芳 《Fountain》という英語が長らく《泉》と翻訳されて定着しているのですが、藤本さんや篠原資明先生は、あれは《噴水》と訳さなければならない、という意見です。《噴水》と《泉》とでは与えるイメージがまったく違うので。私は《泉》派なんですよ。最近、非常に劣勢なんですけど(笑)。
間違っていると考えているわけではないのですが、噴水と書くと「噴く」水なので、水がそこから噴き出さなければならず、まるで便器から水が吹き出すような印象を与えてしまう。私があの作品を「泉」とする理由は、あれが男性のペニスから水が落ちる、水受けの役割だからです。
デュシャンのノートの中から、あれを男性の象徴ではなくて、実は女性の象徴だと解釈していて、これを「噴水」と訳すと、極めて男性的なものとして誤解してしまうので、だったら「泉」のほうがまだいい。
池田 なるほど。能動性のニュアンスを出したくない、と。
平芳 そうです。フランス語のfontaineは街角にある水飲み場のような、地下水からパイプで水があがってきて手を洗ったり水を飲んだりするようなものを指します。噴水は「ジェドー(jet d’eau)」。デュシャンには「シュドー(chute d’eau)=落下する水」というキーワードがあり、それの対立語で噴き上がる水は「ジェドー」だから、ファウンテンは噴き上がる水をイメージしたものではないと私は思っています。デュシャンのノートの中にはファウンテンに言及したものはないのですが、ジェドーを記したものは残されています。
池田 「落ちる水」を受け入れるイメージ。
平芳 私の場合はそうですね。ただ確かに、例えばブルース・ナウマンの《噴水としての私》のように、口から水を噴く作品があったりもするので、英語でファウンテンを受容してきた人たちの中でも、噴く人もいれば受けるほうだと思っている人もいる。そういうことも含めて、デュシャンを日本語にする問題というのは大きいですね。
デュシャン的なものの現在
編集部 ところで池田さんたちの世代の日本人アーティストにとって、デュシャンはどういう存在でしょうか。
池田 そうですね……例えば僕は毛利悠子さんとほぼ同世代で、彼女は直接《大ガラス》を扱ったりしていますが、ほかにはデュシャンに特別関心がある、という人はすぐには思いつきません。既製品を使う人は多いですが、もはや当たり前の前提になっていて、デュシャンの名の下に、という感じではないかと思います。
平芳 毛利さんの場合、かなり早い時期からデュシャンがらみで作品を作っていたそうですが、いろんな方から、君のデュシャン理解はなってないというようなことを言われて、その反発からいまは自分のデュシャン解釈でやっている、と聞きました。でも彼女のようにデュシャンを直接的に扱う人は、そんなに多くないですよね。
池田 僕自身も、そんなにどっぷりというタイプではなくて、それこそデュシャン的な神秘化から距離をとった赤瀬川にシンパシーがあるほうなので。でもやっぱり避けて通れない存在という感じはしていて、例えば2011年の「東京芸術発電所」では、車輪と「落ちる水」でマイクロ発電を行うということをやったりしています。
ただ美術に限らなければ、『宝石の国』がアニメ化されて話題ですが、例えば漫画家の市川春子は鉱物や植物といった非人間的なものへの感性が鋭く、人間が絶滅した後の世界を描いたりしています。あとそれで思い出しましたけど、音楽家の柴田聡子にも、私から私が消えて目玉だけになり、やがて多様な鉱物たちの輝く世界へと開かれる、といった脱人称的な作品(「ニューポニーテール」)があったりする。おおよそ震災以降、美術では重くてシリアス、総じて「人間的なもの」が増えている印象を持ちますが、毛利さんも含め、ある種デュシャンにも通じる軽さや、非人称的なものへの感性が女性の表現者に多く見られるというのは、どこか兆候的な気もします。
あといきなり世代は飛びますが、REALKYOTOで平芳さんとの対談が公開されている岡崎和郎さんも重要でしょう。日本ではネオダダ界隈をはじめとして反芸術的な理解が強かったと思いますが、今日話していたような造形的、職人的な面でのデュシャンとの関連がある。ネオダダと同世代でありながら岡崎さんのようなアプローチは特異的だと思います。
平芳 岡崎さんは本当に面白い作家で、もっと評価されるべきだと思いますが、やはり反芸術のほうへ行かなかったがゆえに、時流からは少し離れて活動されてきた。瀧口さんにはすごく評価されていましたし、非常に重要なアーティストですね。
池田 平芳さんが企画された2004年の『マルセル・デュシャンと20世紀美術』以降、しばらく日本では本格的なデュシャン展は開催されていません。その意味でも京都国立近代美術館での連続企画や今回の議論も含め、《泉》100周年をきっかけにしてデュシャンが生まれ直し、さらなる触発へと開かれていけば、と思います。今日は長時間、ありがとうございました。
(2017年10月17日、元新道小学校・HAPSスタジオにて/2017年12月25日公開)

ひらよし・ゆきひろ
美術史研究者。京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授。マルセル・デュシャン研究およびレディメイド以降の芸術を専門とする。国立国際美術館主任研究員時代の2004年に『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展を担当。著書に『マルセル・デュシャンとアメリカ 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』(ナカニシヤ出版)〈吉田秀和賞〉がある。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。
〈C O N T E N T S〉
芸術論の新たな転回 03 平芳幸浩(Interview series by 池田剛介)
・デュシャンはどのように受容された(される)か
――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって1
・デュシャンはどのように受容された(される)か
――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって2