朗読と講演 多和田葉子
聞き手:森山直人 構成:森山直人+編集部
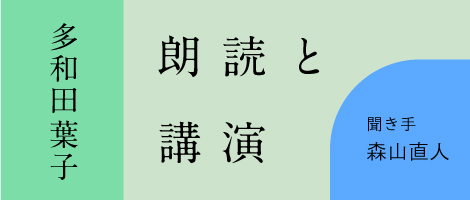

構成:森山直人+編集部
写真:水野正彦(京都造形芸術大学大学院)
編集協力:斉藤雅子
多和田 こんにちは。最初に、これは昔書いたものですけれども、京都に来ようとして、間違えてこだまに乗ってしまったときのことを書いた詩を読みます。
(朗読)
なんだかどうしても
こだま
に乗りたくなって
ふらっとホームで
東京という望みを捨て
首都圏の光をかえりみず
ひっそり静まりかえった木魂の車内に入った
数少ない情客たちは情念に満ちて
文庫本を片手に駅弁を食べていた
青帯をしめた人、黄色い帯をしめた人
いわなを食っている人
わたしは赤帯をしめて翻訳文学にかじりつく
「車内販売はありません」と放送の入った途端
後の人がわたしの肩を叩いて
どうですか、と哲学ビスケットを箱ごと差し出した
そんな風にしてわたしは首都圏をゆっくりと
抜け出すことができたのだった
小田原提灯をさげた狸が
わたしの席の脇を通り過ぎて
次の車両に消えていった
潮風が車内を吹き抜け
海水のしょっぱい味がした
去年、誰かが別荘の話をしていたっけ
熱海の酒を
袈裟
飲みたい
じりじりと砂を焼く海辺の太陽が
別荘の背後に沈んでいく
雑種犬がのんびりと窓から外を眺めているが
主人は在宅の気配がない
三年前、三島で降りて三つの美術館を訪れた
古い富士山
整形後の新しい富士山
富士山に登りたい
殺伐として埃っぽい希望
二年前、静岡大学へ行った帰りに
真っ青な空を背景に
日本でございます風の富士山が見えて
隣にすわっていた中国人観光客といっしょに
三十枚 写真をかしゃったっけ
外から眺めればまあまあの富士山
日焼けした手の甲みたいに愛おしい
ところで掛川ってどんなところ
降りたことのない駅名が未来図を引く
浜松にはコンサートホールがあって
ピアノの隣で鰻丼を食べたっけ
どっちが黒い、ピアノと鰻
鰻という字が自慢の慢に見えてタレが苦かった
豊橋で車掌さんがまわってくる
「すみません、京都に着くの何時ですか」
車掌さんはこだまに乗っているわたしを哀れむように
「名古屋でのぞみに乗り換えることもできますけど」
とやさしく教えてくれた
わたしが黙っていると
「同じ切符でのぞみも乗れます」
と付け加えた
「いいんです。のぞみは自分でつくります。でも、
あなたの声がこだましてくる、そのこだまの響きが
いつ到着するのか、それを教えてください。」
同じ料金なら、大玉ではなく
こだま
長く乗っていられるから
通る駅名の漢字の総画数が多いから
東海道が長く
京都が遠く
感じられるから

『穴あきエフの初恋祭り』
多和田葉子 著/2018年/文藝春秋
さて、いま紹介していただいた、先週出たばかりの私の短編集のお話から始めたいと思います。この短編集の題名は『穴あきエフの初恋祭り』というのですが、「穴あきエフ」というのは、一体何だろうか。もしも私がこの本の作者じゃなければ、「穴あきエフ」という言葉を聞くと、多分「F」――例えば「フョードル」とか、何か「F」の付く名前の登場人物が、穴のあいたズボンでもはいているのかな、というようなイメージなんかが浮かぶんじゃないかと思います。けれども、実は、これはウクライナの「キエフ」から取られています。「アナーキー」と「キエフ」がくっついて「穴あきエフ」になっているんです。
キエフという都市には、歴史的な、素敵な家がたくさんあります。ドイツでもそういう古い家々は非常に大切にされていて、世話をすれば家というものは何百年でも保つものだと考えられている。私がハンブルクで暮らしていたときに住んでいた家は150歳でしたけれども、私の隣の家は350歳でした。南ドイツに行くと、千年前から建っている石造りの家もあるくらいです。現代の日本で「家」というと、10年も経てばあっという間に中古になって値段が下がっちゃう、みたいなイメージがあるけれど、本当はそうではなくて、家も生き物であるという考え方ですね。キエフの家々もそういうものでした。
ところが、そういう古い家を取り壊して、新しいマンションビルを建てて、それを人々に売ろうと考えているマフィア的な会社が、ウクライナにもあるわけです。一方、そういう人たちに反対する住民たちがいる。そういう運動は、私が暮らしはじめた1980年代のドイツでもよくあったんですけれども、そういう人たちは、自分たちはこの住居を出ない、と主張し、一種の住居占拠をするんですね。若い人たちが退去を拒んで住み続けていると、やがて電気も水道も止められちゃう。でも、それでも暗い中で頑張るんです。そうしたら、あるとき「フェスティバルをやろう」という話になった。暗い、とげとげして、くそまじめに政治運動をしているんじゃなくて、非常に明るく、みんなでパーティーをやろう、と言うんです。で、そのパーティーに、私が行き合わせたときの話を、ちょっとだけ読んでみます。
(朗読)
集まってきた人たちが何列かに並べられた椅子に腰掛けると、申し合わせたように夕暮れという一枚のショールが全員の肩にかぶせられた。ナターシャは、タムタムを持った男性とギターを抱えた男性を従えて、自分もギターを抱えて舞台に上がり、よく透る声で前口上を始めた。「みなさん、すわる椅子、見つかりましたか? 立っている人は、ここにまだ三席くらいあいてます。お腹が空いている人は、あそこに食べものや飲み物があるので、自由に取ってください。今日は来てくれて本当にありがとう! 新曲をたくさん歌うつもりです、さっきプラハから帰ってきました。わたしたちと似たような問題を抱えた人たちは世界中にいると思うんですけど、でも正直言ってわたしたちの町は特にひどい状況にあるなあって外国に行く度に感じます。これからも毎週イベントを開いて、この建物を取り壊そうとしている顔のない怪物たちに負けないように頑張っていくつもりです。」ぱらぱらと起こった拍手に乗っかる形でナターシャはギターで和音をかきならしたのはよかったが、元気のいいのは出だしだけで、前奏が終わるとナターシャが急に失恋声で歌い始めたので、みんなしんみりしてしまった。ビクトルは鼻を前に突き出して、真剣な顔で舞台を睨んでいた。次の曲は思わず腰から踊りたくなるような祭りの歌で、その次は子供の頃遊んだブランコの歌で、コンサートはゆっくりと盛り上がっていった。振り返ると遅れて来て後ろの方に立っている人たちがかなりいるようだった。
気がつくと、闇がわたしたち全員を抱きしめていた。ナターシャは見えない一点から歌を送り届け続けてきた。こんなにたくさんの人たちといっしょに暗闇の中で歌に耳をすましているというのは不思議な気持ちだった。月のない夜だった。わたしたちの暮らす地上は電気をとめられてしまえば暗く、うすら寒い。町のあかりも少しずつ消えていくのか、夜空に見えた雲の気配さえ消えていった。すると、目を閉じても、目を開けても、世界がほとんど違わないのが不思議だった。時々煙草に火をつける人がいると、その顔だけが一瞬、黄色い光に輝らし出されて見えた。

こういう感じなんですけれども、いま朗読したのは「穴あきエフの初恋祭り」という短編小説の一節です。短編集『穴あきエフの初恋祭り』には、ほかにもいろんな小説が入っているのですが、その中に「てんてんはんそく」という小説があります。ここには「照子(=テルコ)」と「青江(=アオエ)」と「アリス」という登場人物が出てきます。テルコという名前は、実は「テレコム」というドイツの電話会社から来ているんです。アオエは「AOL」をドイツ語読みすると「アー・オー・エル」で、そこからアオエさんになった。「アリス」も、これはもう潰れちゃったんですけれども、テレコムを脇にのかして、自分のところと契約させようと、一時えげつないほどがんばっていた電話会社なんですね。
別にそのことを知らないでこの小説を読んでくださってもいいんですが、その3人の女性が出てきて、何となく欲望がうごめいていて、嫉妬であるとか、何かの取り合いのようなことが行われている。そんな雰囲気で書かれているんですけれども、その背景には、電話会社というものが私たちをつかまえようとしている、という現実があります。これは日本も同じだと思うんですけれども、なんとかして契約を取り付け、自分と結びつくようにしている。電話は、もともと人と人を結びつけるものであるので、ただの機械よりも深く人間の欲望を支配してしまう可能性があると思うんです。
こういう状況は、100年前とはもう違ってきています。電話というものが生まれ、普及しはじめたころの様子は、例えば、ヴァルター・ベンヤミンの『ベルリンの幼年時代』を読んでいてもわかりますが、そんなにべたべたと、しょっちゅうかけたりするものじゃなくて、暗い廊下のような場所にひっそりとあって、たまにベルが鳴る、というくらいのものだった。ベルが鳴ると、まるで神のお出ましみたいな、とても神秘的な雰囲気が漂う。どこか、この世の向こう側から声が聞こえてくる、というぐらい、私たちの日常から遠い存在だったんですね。1960年代になっても、家に電話が付きはじめたのは私が子供のころですけど、電話というのはしょっちゅうかけるものではないとされていました。そもそも家族に1台しかないし、親がいるし、用事を言ったらすぐ切りなさいと言われるし、そういう世界だったわけですね。その内にどういうわけか、やっぱり長電話をしたいという気持ちが、思春期に入ると特に女の子の間に生まれてくる。だから、わざわざ外に行って公衆電話の電話ボックスからするとか、家でも親がいないときにするとかいうことになり、だんだんだんだん時代の流れとともに、次第に私たちが電話線につながれていったという歴史があるんだと思います。そして今日ではもう、ひっきりなしに電話ではなくメールやLINEを送り合ったりして、もう離れられないですね。中毒のように人とつながっていなければ耐えられないというのが、いまの時代ではないかと思います。
それほど私たちがつながっていなきゃならない時代になると、電話会社の戦いというのがすさまじいんですね。それを私が体験したのは引っ越しをしたときでした。引っ越ししなければずっと同じ電話会社でいいんですけれども、引っ越しした途端に「うちにつながりなさい」「うちにつながりなさい」ということで電話会社のいけにえになっていくんですね。――「てんてんはんそく」という作品は、そういう話です。
現代のコミュニケーション
それから、これもやっぱり一種のコミュニケーションの話を描いている「文通」という小説も収録されています。「文通」というのは、主人公の男性が高校の同窓会に行く話です。彼には昔、彼とつき合いたいと思っていた女性がいたんだけれども、その女性に何通も手紙を書くことで、その人と直接会う時期を先へ先へと延ばしていったという経験があって、その回想をする。最近はインターネットがあるから、手紙というのもなかなか書かなくなってきたんじゃないかと思います。でも、昔は――なんて言うと年寄りみたいですけれども――、例えば私の高校時代には、友達と会って話をしても、その友達と別れてから家に帰ってその人に長い手紙を書くということがありました。メールなんかよりもずっとずっと長い手紙を書く。手紙を書かないと、毎日会っていても、どういうわけか友情は育たない。毎日会ってしゃべっているんだけど、会ってしゃべることというのは、「何食べる?」とか「これ、美味しかった」とか、現実に即した実用的なことが多い。それに対して、手紙というものはひとりになって書く。つまり、私は一体何を考え、何がしたいんだろうかということを、まずひとりである状態で相手に向かって書くので、大げさに言えば、書簡小説みたいな感じになってくるんですね。この書簡小説的な手紙のつき合いがないと、友情が育っていかなかった。書簡小説といえば、『若きウェルテルの悩み』や『あしながおじさん』もそうですね。あと、太宰治の「トカトントン」もそうかな。文学史には、たくさんあると思います。でも、そうじゃなくて、本当の手紙なんだけど、まるで小説を書いているかのように一生懸命書くわけです。毎日会っている人なのに、手紙を書くことで、口でしゃべっているだけでは生まれないコミュニケーションの空間をつくり上げていくというような作業、それが文通なんじゃないかなと思います。
でも、それから時代はずいぶん変わってしまった。それでは、いまコミュニケーションはどうなってきたんだろうかと考えてみます。そうすると最近では、昔は存在していなかった「コミュニケーションスタディーズ」とか「情報学」とか、そういう学問が大学の専攻科目として出てきたし、そういうものを勉強する人たちも増えてきた。これは、一体どういうことなんだろうかと思います。以前はコミュニケーションとは、例えば社会学の中で研究対象にされることはあっても、それ自体を大学で勉強するようなことはなかった。だから、それを「専攻する」というのは非常に不思議な感じがするわけですが、他方ではそれが人気学科にもなっていく。
「胡蝶、カリフォルニアに舞う」という短編では、そういう話が出てきます。主人公は非常に軽薄な男で、なんとなくアメリカに留学して、なんとなくコミュニケーションスタディーズを専攻する。ところが、そんな彼が人生の中で実際に行っている他人とのコミュニケーションをよく見てみると、ある意味で非常に多様なコミュニケーションを実践していることが見えてきます。それが、あるときには非常に滑稽にも見える。
で、結局いろいろなコミュニケーションの食い違いから、彼はアメリカにいられなくなって、日本に帰ることになります。再就職の目途が立っているわけではない。でも、とりあえず英会話はほかの人よりできる。単に英会話ができるというよりも、他人が英語で言ったことにうまく答えることができるという能力に、彼は秀でているんですね。もちろんそれは嘘をつくことだってできる、ということなんですけれども、最後には、これが取り柄だと認められて、アメリカのカスタマーサービス会社に就職できる、という物語です。
現代のカスタマーサービスというものは、これも電話コミュニケーションですけれども、非常にナンセンスなコミュニケーションのいい例だと思うんです。例えば、アメリカ人がアメリカで掃除機を買って、その掃除機が壊れたとする。そうすると、壊れたらここに電話してくださいというようなことが書いてあるので、その番号にかけると、そういう電話は実はインドとかフィリピンのような物価や人件費の安い英語圏の地域につながる仕組みになっていて、そこで働いている人たちが、そういうお客様の苦情に答えてくれることになるのです。彼らは、実際にはその掃除機を見たことがないにもかかわらず、そういう電話に答えるという仕事なんですね。
そういえば、『地球にちりばめられて』に出てくるエスキモーのナヌークのお父さんがそれと同じような仕事をしています。いまの地球は、グローバル化して、いろんなふうにつながっているというんですけど、そのつながり方は、斜めにつながっているというか、変なふうに、不思議なふうにつながっていたりする。そのつながり方には一体どんなものがあるんだろうかということも、少し気になっているテーマです。
「ポストトゥルース」の時代に
森山 「胡蝶、カリフォルニアに舞う」と「文通」というふたつの作品は、比較的最近、今年(2018年)発表されたものですね。この短編集『穴あきエフの初恋祭り』には2009年から2018年までの9年間に発表された7作品が収められていて、時間的な幅はかなり長いんですけれども、全体を通して読むと、やはり2018年に発表されたふたつの作品が、ちょっと色合いが違うというか、「今」の空気がすごく入ってくる感じがして印象に残りました。どうしてそういう感じがしたのか、私もまだあまりきちんと整理できていないんですけれど、ひとつ言えそうなのは、例えば「胡蝶」の主人公――アルファベットの「I」と表記されているのがその主人公なんですが、Iと結婚したいらしい優子という女性が出てくる。それからもうひとり、Iがカリフォルニアに留学しているときに、Iのルームメートという設定のベン君という人が出てきて、そのベン君が、とにかくこのIというのは軽薄な男で、日本から出ちゃえば、日本のことなんか平気でどんどん忘れていっちゃうという能力の持ち主なんですが、そんなI君に、「いや、でも、日本はいまこういうことになっているらしいよ」という大小さまざまな情報を、ネットでガンガン調べて教えてくれる。I君は「あれ、ホントかな?」なんて悩みながら、半信半疑のままで、とはいえ、確実にそういう情報に微妙に振り回されながら、久しぶりに日本に帰ってきて、久しぶりに東京の中央線に乗ったり、就職先で就職面接を受けたりするんですよね。
なんというか、I君の物事に対するその流され方が、とても現代的な感じがしたんです。「ほんとにこれでいいんだっけ?」と思いつつも、だからといって、そのことについて本格的に自分で調べてみるわけでもない。そういう主人公の行動パターンを読み進めていく内に、ふと、「ポストトゥルース」の時代って案外こういうことなのかもしれないと感じられてきたりしました。
「ポストトゥルース」や「フェイクニュース」といった言葉から普段ニュースで感じているイメージって、「あからさまな嘘」というか、もっと白黒はっきりしたものみたいに流通しているような気がするのですが、この小説を読んだときに、主人公の、ある種の曖昧さの原理に彩られた行動様式が、「ポストトゥルース」そのものというよりは、むしろ「ポストトゥルース」という言葉に敏感になったり、ときには過敏になったりしている私たちの時代の空気とどこかでつながっているというか、「同時代性」が感じられたようなところがあったんです。そういうことは、どこかで意識なさっていたりしたのでしょうか。
多和田 いろんなことが言えると思いますね。
まず私自身がドイツに行ってすぐのときは、最初の6ヶ月くらい、極端に言えばひとことも日本語をしゃべらなかったし、そもそも日本人と接触しなかった。これは、いまの時代には考えられないことかもしれないですね。いまなら、例えば甥がドイツに来たりしても、インターネットがあるし、すぐにメールでやり取りしてつながることができるのに、そのころだと、もう本当に切れてしまう。国際電話なんて、ダイヤル回しただけで4000円くらいかかるような時代だから、高くてとてもかけられない。通信手段は手紙だけ。でも、手紙は返事をもらうのに時間がかかりますからね。
つまり、そのとき私が体験していたのは、私の中で、私だけの日本語というものが、一種の断絶した状態としてあったということです。それはそれで、昔のよかった面だと思います。「旅」というものが、なれ合っている人々から離れて、たったひとりになるということだった。家族とも親しかった人ともつながっていないし、誰も周りにいない。周りの人はすべて他者であるという状態の中で、私は日本語で一生懸命何かを書くわけです。この短編集の中の「おと・どけ・もの」という作品には、まだそのときの傾向みたいなものが現れていて、最近発表したものよりもちょっと読みにくいかもしれないんですけれども、言葉そのものの中に入り込んでいくような日本語ですね。誰かに向かって言語を語っているというのがほとんどなくて、日本語と私がここに取り残されてしまった。――じゃあ、この日本語って何なんだろう、これを使っていた私って何なんだろうという、少し呆然とした感じで語っているわけです。
そのころは、日本はドイツから見たら非常に遠い国で、まったく知らないわけじゃないけれども、次々にニュースが入ってくるということもない。ところが情報機関がどんどん発達してくると、その機関そのものが独立して踊りはじめて、ありとあらゆる情報が入ってくるわけですね。インターネット自体は悪いとは思いませんが、インターネットのせいで情報源が曖昧になってくることがある。昔だったら、この情報は岩波書店のこういう本に書いてあったとか、NHKでこう言っていた、とか、情報源の権威のようなものがあった。必ずしも正しいかどうかわからないけれども、一応それを私たちは信用しようじゃないかというような共通の情報源がありましたよね。でも、いまはしっかり見ないと、インターネットに載っているニュースが本当か嘘かということが、なかなか判断しにくくなってきた。
下手をすると、フェイクニュースの一種の罠にかかって、その網の中だけで動くようになると、それ以外のことがすべて嘘になってしまう。そういえばドイツで、そういう運転手のタクシーに、たまたま乗り合わせたことがありました。彼が「フクシマ、大変だったね」と声をかけてくるから、「うん、大変だった」と答えたら、「あれって、イスラエルが爆弾仕掛けたんだよね」と言うんです。「えーっ、それは違うと思いますけど」と言っても全然効果がなく「表向きは『原発事故』ということにさせられているだけなんだって。そもそも、広島の原爆だって本当はなかったんだし」とか言うので、「それはどういう情報源ですか」と聞いたら、「だって、ネットに載っている」と言うので、家に帰って調べて見ると、《A-bomb does not exist》みたいなサイトに、そういうことが延々と書いてあるんです。すごく長いサイトで、あらゆる「実証例」があって、「広島の原爆は本当はなかった」「あれは左翼が戦争をやめさせるために発明したフェイクニュースである」みたいな内容がとうとうと書いてあって、非常にびっくりしました。でも、きっとその運転手さんは、このネットから出発して、その後いろんなところにアクセスしても、すべてそういうニュースしか手に入らない状態にあったんだと思う。網にかかった魚のような状態になってしまっているんだ、ということがわかったんです。
こういう例を見ると、現代の情報環境には、確かにそういう非常に危ない面もあります。でも、そういうところから来る面白さも、同時にあるんじゃないかとも思いますね。少し前に『地球にちりばめられて』という長編小説を発表したのですが、そこでは日本という国自体が消滅してしまった架空の世界が舞台になっています。日本の断片的なイメージや情報だけが世界中に広がって、そういうものがかえって人々を活性化させているところがあるという世界です。例えば、日本には「うまみ」というすばらしいものがあったらしいが、それは一体何なんだろう。曖昧な情報、中途半端な情報なんだけど、それを手がかりに、みんなが何かを探しはじめる。
森山 「旨味フェスティバル」というのが出てきますね。
多和田 そう。うまみや出汁は本当に流行っていて、「出汁の秘密」とか「出汁の魅力」とか、そういうものを特集する番組があったりするくらいです。そういう日本像みたいなものを、必ずしも外国で何か言っているよ、ということじゃなくて、それ自体に面白さを感じたりすることもあるんですね。
例えば、クロード・モネのような画家がそうです。フランスの印象派の画家たちは日本の浮世絵をたくさん見ていて、その中には当然富士山を描いたものもあるので、「富士山はすばらしい」と自分だけの富士山のイメージを頭の中でつくっていた。そういうイメージを抱いていたモネが、あるときノルウェーに行って、私の目にはどう見ても富士山に似ているようには思えないコルサース山という山を見て、「これが富士だ」と言ってその絵を描いたりしています。フェイクニュースと違って、こういう「誤解」は、面白いと思うんですよ。

『地球にちりばめられて』
多和田葉子 著/2018年/講談社
森山 そういう種類の面白さが、『地球にちりばめられて』という作品では、さまざまな形で描かれていますよね。いまお話しになったタクシーの運転手さんのエピソードとか、ある意味でそういう時代の絶望的な側面は確実にあるとして、けれども、それを徹底的にユーモアで笑いのめすことも可能なはずです。『地球にちりばめられて』からは、そういうやり方で先に進んでいく、とても前向きな励ましのようなものが伝わってくるような気がします。そういう面白さはあまりにもたくさんあって、とても全部は拾い切れないんですけれども、例えば、この長編小説の中心人物である、すでになくなってしまった国・日本出身のHirukoは「パンスカ」という不思議な言語を使っている。「パンスカ」は「汎スカンジナビア」の略で、祖国を失って欧州各地を渡り歩いて生活している彼女自身が、スカンジナビア半島の諸国語を自分でミックスしてつくった一種のクレオール語だということになっています。
《この言語はスカンジナビアならどの国に行っても通じる人工語で、自分では密かに「パンスカ」と呼んでいる。「汎」という意味の「パン」に「スカンジナビア」の「スカ」を付けた。(中略)わたしのパンスカは、実験室でつくったのでもコンピューターでつくったのでもなく、何となくしゃべっているうちに何となくできてしまった通じる言葉だ。》(同書、37-38頁)
私がとても印象に残っているHirukoの逸話のひとつは、あるとき、滞在先のデンマークのメルヘン・センターで、子供たちに紙芝居を語り聞かせる仕事に就いた彼女が、日本の民話である「鶴の恩返し」を紙芝居で、デンマーク人の子供たちに伝えようとするところです。そもそも「鶴の恩返し」の「恩返し」という言葉をどういうふうに訳したら伝わるのだろうか、と考えたあげく、ひとまず「鶴のありがとう」というふうに翻訳しておこう、という結論に達する。もちろん、明らかに「恩返し」と「ありがとう」というのは意味が違うわけなんですけれども、しかし、そのズレによって生まれる新しいコミュニケーションの空間が生まれてくるところが、すごく面白い。べつの童話で、「饅頭」という日本語は「マジパンチョコレート」と訳されたりする。そうなると、まるで饅頭の味まで変わって感じられてくるような気がして、もちろんほかにもいろいろあるんですけれども、そういうところに、この小説の大きな魅力が現れているように思いました。厳密にいえば、「誤訳」に分類されてしまうはずのこうした言葉のズレが、けっしてネガティブではなく、ユーモラスでポジティブな新しい回路を切り拓いてしまうと言ったらよいでしょうか。「母語の外に出る」ことが、必ずしも悲劇ばかりではなく、母語にとどまっているときには感じられなかったような言葉の別の感覚が見出されたりすることがありうる、ということですね。もちろんそういう面白さは、たぶん多和田さんの初期の作品からずっとあったんじゃないかと思うんですが、その辺、昔といまとで変わってきたことはありますか。
多和田 昔から関心はありましたね。「恩返し」に関していえば、そもそもこの言葉は文化的なニュアンスを強く帯びていて、そもそも何かをしてもらったから何かをお返しするということ自体が、別の文化から見れば、やり過ぎかもしれない。だから、本当は「ありがとう」で終わってしまって「恩返し」はないということでもいいかもしれませんよね。そういう異なる文化と文化の間の翻訳には関心があります。単にズレるだけではなく、当たり前だと思っている自分自身を見つめ直すきっかけにもなるんじゃないでしょうか。例えば「鶴の恩返し」の場合、みんながよく知っている物語の中では、主人公の鶴は自分の羽を抜いて、それで機を織ることになっています。でも、よく考えると、羽では機は折れないですよ。糸じゃないですからね。「鶴の恩返し」という話があまりにも有名すぎるので、生糸でもないし、木綿でもないのに、いったいどうやって機を織るのかという疑問を私たちは普段持たずにすませているわけです。でも、いざ日本の外でその話を考えると、どうやって羽から布をつくるの? ということになってしまう。
『地球にちりばめられて』の中で、Hirukoはそういう問題に突き当たることになります。そこで彼女は、「鶴は羽根でダウンジャケットをつくった」というふうにすればよいことを思いつくのです(笑)。考えてみれば、そのほうがずっと説得力がありますよね。
森山 とてもいいですね、それ(笑)。
多和田 そのこととも関連するのですが、私はエスキモーの神話や昔話をかなり調べているんですが、そのときに気がついたのは、昔話というものが、必ずしもすべて昔から伝わっているわけではないということです。よくよく調べてみると、中には、たったひとりの移民が間違えて話した言葉や、勝手につくった言葉が紛れこんでいる場合があるから、研究者は注意しなければいけないと言われているんです。例えば、アメリカ・インディアンの神話とエスキモーの神話で共通の要素があったので、これは歴史的にどう解釈すべきかいろいろ調べた人がいたんですけれども、実はそれはたったひとりアメリカに移り住んで、インディアンと一緒に結婚したエスキモーがその話をつくったということが実際にあったらしい。たったひとりが、こういう話はどうかな、と思いついてつくった話が、あまりにも説得力があって、後の時代から見ると、まるで昔からこの話が伝えられているように誤解されることだってあるというわけですね。
でも、私は学者じゃないので、学問的な正確さに縛られる必要はないと思うんです。むしろ、常に何かが混ざって、常に新しい物語がつくられているというのが、いまの世界だと思うんですよ。非常に危険な物語もあるし、私たちに新しいものを見せてくれる物語もある。どこで出来たかもわからない、どこから来たかもわからないものもたくさんあふれている。その中で、私たちはどうやって生きていったらいいんだろうかというのはひとつの課題ですね。そういうものを全部排除して、自閉的に暮らしていくということは無理ですから。
言葉がうつる、魂がのりうつる
森山 今日、この公開レクチャーの前に、多和田さんは本学の文芸表現学科で「詩のワークショップ」をなさっていました。テーマが事前に与えられていて、それに即して学生が詩をつくってきて合評するという内容だったのですが、ある学生が「言葉が歩く」という詩をつくってきて、その中に「ことばがあるいてうつる」という印象的な一節がありましたね。全部平仮名で表記されているので、「言葉がうつる」の「うつる」は「移ろう」の「うつる」にも聞こえるし、「伝染する」の「うつる」にも聞こえる。あるいは「水鏡に映る」みたいな「映り込む」という意味合いも感じられる。短いフレーズであるにもかかわらず、言葉のある種の本質をうまく言い表しているなと思ったのですが、そこで含意されていることは、まさにいま、多和田さんがおっしゃったようなこととも通じてくるように思いました。「恩返し」と「ありがとう」、「マジパンチョコレート」と「饅頭」のように、お互いがお互いを鏡のように写し合って、似ているところと違うところを探し合ったり、間違い探しをしたりするようなところもあれば、そういう映し合いみたいなことを通じて、言葉がじわじわ別の場所に移っていったり、移ろっていったりする。ものすごく説得力を持った言葉が伝染病のように広がっていったりする言葉の世界の営みですね。「フェイクニュース」というとネガティブな響きがするけれど、少し離れた眼で観察すると、案外、そういう言葉の移ろい方に近い部分もあるのかもしれない。
ともかく、そういう意味で「言葉がうつる」こと――言葉の「移動」や「感染」といったことは、多和田さんの作品を読んでいるととても強く感じられるし、今回の新作もそうだったんです。あくまでも一読者としての感想にすぎませんが、「鶴のありがとう」も「マジパンチョコレート」も、一度読んでしまうと忘れられなくなる。読んだ瞬間に、こっちにバッと感染してきてしまう。そういう感覚は、以前の多和田作品にもたくさんあったと思うのですが、ただ、時代の空気が変わると、そのうつり方の微妙な運動の仕方が、そのときどきで変わってきたり、読み手も変わってきたりするかもしれない。そんなことを、今度の短編集を読ませていただきながら、漠然と感じていました。
多和田 あと、霊が、魂が、のりうつると言いますね。私の初期の作品は、どちらかというと、一人称の「私」が私自身に非常に近い存在で、そこから世界を見て語るというものが多かったのですが、白熊を主人公にした『雪の練習生』(2011)という長編を書いてから変わってきたように思います。「私」は「白熊」にもうつることができる。だったら、誰にでもうつれるんじゃないか、ということです。
『地球にちりばめられて』という長編は、一人称の語り手が変化していく構成になっています。性や文化的バックグラウンドの異なる登場人物が、章によって次々に異なった視点から物事を語っていく。初期の私の作品では、一人称から三人称に移行することは、そんなに自然なことではなかったですね。「私」の場所はここ、「私」は「私」みたいな感じだったんですけれども、『雪の練習生』を書いてからは、とてもうつりやすくなりました。
森山 そうすると『雪の練習生』という作品は、多和田さんの中ではかなり大きな作品だったということですね。
多和田 はい。画期的だったと思います。動物は初期の『犬婿入り』にも出てきますけれども、その犬はあくまでも人間の女性から見た犬ということで描かれている。それに対して『雪の練習生』では、主人公の白熊は自分から語っています。とはいっても、それは「なり切る」というのともちょっと違っていて、何なんでしょうね。
文学の場合、演劇と違って、とりあえず語り手というのがあって、そのポジションから物語が語られていきますが、そのポジションが、果たしてひとつであるのかどうか。ひとつであることが前提のようによく思われがちなのですが、もしも、それがそうではなく、作家が俳優のようにいろいろな役をうつりながら舞台のような作品をつくっていく、というふうに想定したならば、語り手もどんどん変わっていくし、語る主体も複数になっていくわけですね。全体を統合して物語を語ることができるひとつの視点というのは、その場にはいないということになってくるんじゃないかと思いますね。
森山 そういえば『地球にちりばめられて』で「パンスカ」を話しているときのHirukoの言葉は、日本語の文法が微妙に破格な形で書かれていますよね。会話文なのに、例えば「でも今日は宿のシングルが予約されているので、腕時計を見る必要なし。」(18頁)とか、「移民が一つの国に永遠に滞在できるようになるのかどうか不明。」(20頁)とか、わざと滑らかではない日本語になっている……。
多和田 そうです。
森山 でも、あくまでもこういう言い方は、とりあえずこう書かれているだけで、登場人物たちの耳に直接響いている「パンスカ」そのものではないわけですよね。
多和田 ないです。
森山 だから、「パンスカ」そのものの言葉の姿を、私たちは直接的には知ることはできないし、聞くことができない。微妙に不自然な日本語を通じて、間接的に想像することしかできない仕組みになっています。こういう仕掛けが、やっぱり演劇といちばん違うというか、演劇ではできないなあ、と思うんですよ。演劇だったら、言葉を音声化しなければならないけれど、ここに書かれている「パンスカ」をそのまま発語したら、絶対に嘘っぽくなってしまうだろうと思うんです。もしかすると、最近のいわゆるポストドラマ的な現代演劇でときどきやるみたいに、わざと字幕を使うとか、何らかの映像的な仕掛けを使うとか、そういうことでもしないとこの感覚は表現できないなあ、と。この面白さは、オーソドックスな台詞劇の方法では絶対できないし、小説だからこその特権のような気がしました。

移民の言葉とロボットの言葉
多和田 たぶん「パンスカ」をドイツ語で書こうとしたら、すごく難しいんですよ。「パンスカ」を本当につくってみせるぐらいじゃないとだめだと思います。我が身を投じて、スカンジナビアに行って、恥ずかしい間違った言葉をしゃべって、みんなに、えっ、えっと言われながら、通じるぎりぎりの言葉を発見していくみたいなことですね。設定上「パンスカ」は、ここまでなら間違っても通じる言葉ということなので、実際には、精神的に必ずしも楽しいプロセスではないような気がします。
森山 タフじゃないと……。
多和田 タフじゃないとできない。でも、そういう実験をしなければヨーロッパ語でこの小説は書けない。日本語だと、「パンスカ」という言葉が仮にあったとして、それを日本語に訳すとこういう雰囲気ですよ、というふうにごまかせる。
森山 日本語とヨーロッパ語の距離があるからこそ、ということですね。
多和田 そう、遠いから。実際の生活の中では、例えばスカンジナビアのどこかで開催される文学祭なんかに出席すると、スウェーデンの人はスウェーデン語、ノルウェー人はノルウェー語、デンマーク人はデンマーク語をしゃべっていても、お互いに意味はわかっているんです。それなら「パンスカ」というものも不可能ではないんじゃないか、という私の仮説ですね。でも、Hirukoの話す「パンスカ」は固定された体系ではないんです。そうではなくて、例えばデンマークに行けばデンマーク語の要素が強くなるといった具合に、Hirukoの中で毎日変わっていくような言葉なんです。だから、ちょっとつかみようのない言葉という感じなんですが、「移民の言葉」ってそういう性質があると思うんですよ。移民にとっては大変な、日々戦いですけれども、でも、もうちょっとリラックスして眺めてみると、これは非常に面白いと考えることもできますよね。子供が言語を習得するプロセスも非常に面白いけれど、移民がある言葉を習得したり間違えたりする現象も、「言語とは何か」を考える上で、これほど参考になることはないんです。
先週、ドイツ人の友達に誘われて、私自身はまったく関心のない「World Robot Summit」というのに行ってきたんです。東京の国際展示場にいろいろなロボットがあったのですが、「黒柳徹子のアンドロイド」というロボットが展示されていて、そのロボットは彼女の声や話し方そっくりに話す。舞台にわざわざ「徹子の部屋」のセットが組んであって、そこへ行ってみると、徹子さんのアンドロイドが「お住まいは?」と聞いてくるんです。私の東京の実家は国立市なので、「クニタチです」と答えたら、徹子さんはしばらく考えて、「コクリツね」と言うんですね。こういう間違い方は、人間は絶対しない。アンドロイドをつくった人に尋ねると、「クニタチ」が漢字に変換されて、それをロボットが読み間違えるんだそうです。それから、「好きな動物は?」と聞かれたので、「ホッキョクグマです」と言ったら、「あっ、ホッキョクグマね。さようなら」って言われて、そこで会話が終わってしまった。でも、私の次に来た人が「パンダです」と答えたら、「パンダかわいいよね」って話が盛り上がっている。パンダに関する受け答えの情報はたくさん入っているのに、ホッキョクグマに関する情報がアンドロイドの中にほとんど存在しなかったということだった。
森山 そこが、ビッグデータの限界……。でも、これからディープラーニングしていく可能性もあるのかも。
多和田 そうですね。でも、ロボットに関してみんながよく心配しているのは、「ロボットが人間みたいになっちゃうことはありますか」みたいなことだと思うんですけれども、私はそれはどっちでもよくて、むしろ心配なのは「人間ってはたしてこれ以上の会話を本当にしているだろうか」ということなんです。ロボットはここまで来ている。私たちはそれと同じレベルじゃだめなんだということですね。
森山 なんかそういう話、先ほど話題になっていた「胡蝶、カリフォルニアに舞う」で描かれている世界も、そういう問いを思い起こさせるものがありますね。詳しくはネタバレになるので言えませんが。
多和田 はい。要するに、コミュニケーションの人工頭脳というのは非常に発達しているわけですね。そこで、ロボットが話せる程度のコミュニケーションしか私たちがしてないとしたら、そのことのほうが問題なのであって、ロボットがどれぐらい開発されるかされないかよりも、私たちの会話はこんな程度でいいんだろうかということが問題のような気がします。
森山 多和田作品における言葉のずれ方も、あるとき、唐突にポンと飛んだりすることがありますよね。あの飛び方というのは、結果だけ見るとマシーン的に見えなくもないですけれども、多和田さんの中で、そういうのがパッと出てくるときの体感って、どういう感じなんでしょうか。そこが、読んでいるだけだとなかなか解けない謎みたいな感じなんですけれども。
多和田 それは私もわからないですね。というか、小説的な頭でずっと集中して仕事をしていると、そういう瞬間が現れるんです。その集中の仕方というのは、いろんなことを同時に考えるということだと思うんですね。同時に考えると総合的なコンプレックスな思考が働いて、普通の分け方や考え方では現れないようなAからBへの道みたいなのが現れるんじゃないかな。
自然科学的な考え方とか、歴史的なものの見方とか、社会的、文化的とかいろいろありますけれども、だいたいそういう場合の考え方は、なるべく大きなものを分けていって、そのひとつひとつについて分析していくということになると思いますが、小説や詩を書いたりするときは、分けない。何かあるものがあったら、そっくりそのままを考えることができるかどうかというのが、詩を書くときの頭です。そうすると、飛躍に見えるような思考の動き方が出てくるんじゃないでしょうか。

森山 そういう、ある種類の集中というものが、そういう回路を拓くということですね。
多和田 はい。
小説のタイトルはどう付けるか
森山 ありがとうございました。予定時間が近づいてきましたので、このあたりでオーディエンスの方のご質問も受けたいと思います。それでは、ご質問いかがでしょうか。
質問者1 「穴あきエフの初恋祭り」を読んで、登場人物の名前が気になりました。例えば「ナターシャ」という人物には「那谷紗」という漢字が当てられていて、『献灯使』の「夜那谷」(よなたに)を思い出すような名前になっています。多和田さんはいつも、執筆されているときには声に出しながら書く、そのスピードで書くとおっしゃっているので、朗読を想定して書かれていることは皆さんご存じでしょうが、先ほどの朗読を聞いてはっとしたのは、「那谷紗」とか「魚籠透」という名前を声に出して言うと、文章を読んでいるときの漢字の印象よりも、その横にひっそりとついているルビの「ナターシャ」や「ビクトル」のほうが前面に出てきて、漢字が完全に消えてしまうという気がしました。質問ではなく、感想なんですけれども。
多和田 それは朗読のひとつの問題で、この前『
森山 『ひこん』は「飛ぶ魂」だから、やっぱり漢字で見ると印象が違いますね。『球形時間』も、「球・形」という漢字が効いていますし。
そういえば、多和田作品のタイトルは、いつもどういうタイミングで決まっていくのでしょうか。最初ですか、それとも……。
多和田 割と最初のほうから付いている場合もありますけれども、全然付かなくて困って、ずいぶん後のほうになってから付ける場合もあります。
森山 『穴あきエフ』の場合はどうだったでしょうか。
多和田 「穴あきエフの初恋祭り」か、「ミス転換の不思議な赤」かのどちらかということで、結局「穴あきエフ」になりました。
森山 『地球にちりばめられて』はどうですか。
多和田 これは結構最初のほうから、これであると。なかなか続きが難しいんですけれども、これは続編を想定していて、『地球にちりばめられて』の場合は「ち」の音が連続しますから、第2部は『星にほのめかされて』。でも、そうすると、第3部が『月につれさられて』となって、ちょっと悲しい感じになってしまうかもしれません。タイトルを最初に決めたがゆえに、悲しい終わり方になってしまうというのもあれなんですけれども、でも「地球にちりばめられて」は、音からも意味からも、自分が書きたいことはこの辺かなというのとぴったりと合ったので、そういうタイトルが最初にあれば、もちろんそれはうれしいですけれども、なかなかそうはいかないですね。
森山 ありがとうございます。いかがでしょうか。
質問者2 タイトルの話で、ずっと不思議に思っていたことがあります。昔の作品なんですけれども、「アルファベットの傷口」が「文字移植」になったことに特別な理由はあったのでしょうか。
多和田 あります。内面的な理由ではないんですけれども、あの中にアンネ・ドゥーデンの「アルファベットの傷口」という作品が出てきますよね。ドゥーデンの作品は、最初は雑誌に載っていただけで、あまり注目されない小品という感じだったんですけれども、その内にドゥーデンが短編集を出すことになって、その本の題名が『アルファベットの傷口』になったんですね。そうすると、同じタイトルだと失礼に当たると思ったので変えたんです。でも、「アルファベットの傷口」というタイトルが好きだった人がなぜか結構いて、その人たちから「何で変えたんだ」という問い合わせが来て、ちょっと困りました。
森山 確かに「アルファベットの傷口」、いいタイトルですよね。「かかとを失くして」というのも好きですけれど。
多和田 「かかとを失くして」はすばらしいタイトルだけど、あれは講談社の天才的な編集者が付けた題名で、残念ながら私じゃないんですよ。
森山 「かかとを失くして」は初期の作品ですよね。それについてのエッセイなんかもあって、まさにドイツに行って、母語である日本語をどんどん失っていく感覚を、かかとを失くすような体験だというふうに形容なさっているのが非常に印象的でした。
多和田 私がそのアイデアを得たのは、ドナルド・キーンさんの『日本人の西洋発見』に出てきた話なんです。ポルトガル人が日本に来たときに、彼らはかかとの高い靴を履いていた。でも、そういう靴は日本にはなくて、日本人はわらじとか、ぺったりとしたのを履いていたから、ポルトガル人が男もハイヒールを履くのはどうしてなんだろうかと日本人は一生懸命考えた。それはたぶん、ポルトガル人にはかかとがないから木のかかとを付けて補助しているんだろう、と日本人は解釈をしたという説が存在したこともあると、キーンさんの本に書いてあって、面白いなと思いました。もしも当時の日本人が外国から来た人を見て「あの人はかかとがない」と思ったとすると、今度は私が外国に行ったら、私のほうが「かかとがない」ということなんだというふうに考えたんですね。
森山 かかとが高い靴を履いてしゃべる言葉とわらじを履いてしゃべる言葉は、やっぱり何か変わってくるような気もしますね……。
今日はお集まりいただきまして、ありがとうございました。多和田さん、どうもありがとうございました。(拍手)
(2018年10月25日、京都造形芸術大学にて。2019年3月26日公開)
たわだ・ようこ
小説家、詩人。1960年、東京生まれ。早稲田大学文学部卒。ハンブルク大学大学院修士課程修了。チューリッヒ大学大学院博士課程修了。1982年、ドイツ・ハンブルクに移住する。1991年「かかとを失くして」で群像新人賞を、1993年「犬婿入り」で芥川賞を、2000年『ヒナギクのお茶の場合』で泉鏡花賞を、2002年『球形時間』でドゥマゴ文学賞を、2003年『容疑者の夜行列車』で谷崎潤一郎賞と伊藤整文学賞を、2011年『尼僧とキューピッドの弓』で紫式部文学賞を、『雪の練習生』で野間文芸賞を、2013年『雲をつかむ話』で読売文学賞と芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門)を受賞する。日独2ヶ国語で作品を発表し、1996年にドイツ語での作家活動によりシャミッソー文学賞、2016年にはドイツで最も権威のある文学賞のひとつクライスト賞を受賞。2018年、『献灯使』で全米図書賞(翻訳文学部門)を受賞。2006年よりベルリン在住。
もりやま・なおと
演劇批評家、京都造形芸術大学舞台芸術学科教授。1968年、東京生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学大学院修士課程修了。京都造形芸術大学大学舞台芸術研究センター主任研究員。
【多和田葉子 詩のワークショップ&朗読と講演】は2018年10月25日に京都造形芸術大学で行われました。
ご予約は以下のサイトで。
http://www.cottage-keibunsha.com/events/20190408/