芸術論の新たな転回 02 千葉雅也「洒落と仮固定の制作論——千葉雅也『勉強の哲学』をめぐって」(Interview series by 池田剛介)
2017.09.13
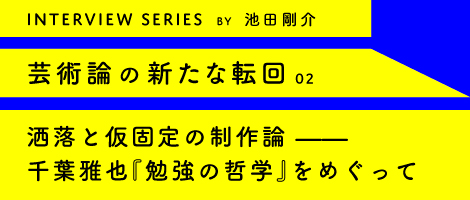
インタビュー:千葉雅也
聞き手:池田剛介

千葉雅也
池田 シリーズ「芸術論の新たな転回」の第二回目となる今回は、新刊『勉強の哲学』が大きな話題となっている千葉雅也さんにお越しいただきました。千葉さんは哲学がご専門で、同時に表象文化、つまりイメージの問題を広くカバーする活動もされています。僕が千葉さんと知り合ったのが2008年ごろなので、ちょうど10年ぐらいの付き合いになり、常にそのお仕事には刺激をもらい続けてきました。
今回上梓された『勉強の哲学』ですが、驚くほど読みやすく、一見よくある自己啓発書のようにも思えるわけですが、読み進めていくうちに勉強することそのものについて原理的に考えさせられるものになっています。販売部数もずいぶん伸びていると聞きます。理系のような実用的とされる知のあり方が重要視され、人文系は信頼を落としていると言われたりもする。その中で「何事かを学ぶ」ことについて根本的に問い直していく姿勢が新鮮に感じられたのではないでしょうか。
本書について、現在の状況に引きつけて聞いてみたいと思います。先日、2020年のオリンピック開催を見越すかたちで、いわゆる「共謀罪」が施行されました。日本では先行きの見えない経済的に不安定な状況が長く続いており、さらに東日本大震災を挟んで、若者の安定志向が言われたりもします。また一方では北朝鮮問題やテロリズムに対する危機感もある。総じて言うと、社会のなかで不安定さや偶然性に対する漠とした不安があり、たとえ自由を犠牲にしてでも安全・安心を求めるという傾向すら感じられます。こうしたなかで本書は、「自由」であることの意味を改めて問い直しているようにも見えました。
千葉 そうですね。社会順応的でない考えを胸に抱くことすら、前もって検閲したいかのような、安全な「一般人」たれという圧力がますます強まっている中で、今もう一度個人が「欲望の主体」として生きるためには、自分の欲望を客観的に捉えようと努めなければなりません。むろん現実的な社会運営のためには、共同体と折り合いをつける必要はあるわけですが、そこで僕としては「欲望の可塑性」を励ますような勉強論を書きたいと思ったんですね。
今、資本にせよ国家にせよ、決して楽観的になれない方向へと大きなうねりを見せている状況になすすべなく巻き込まれているという実感があります。個々人は、自分の人生を防衛しなければなりません。いわば護身術のような勉強法が必要だと思うのですよ。その「護身」というのは知でやるしかない。身を守るために勉強しろ、ということですね。
池田 なるほど、自分の欲望を守り、さらには可塑的に変化するための勉強。一般に勉強というものに人が何をイメージするかと言えば、例えば語学をして留学したり選択肢を広げたりといったように、勉強はなんらかの必要な手段として考えられると思うのですが、千葉さんのいう勉強はそういうものではない。
千葉 僕は『勉強の哲学』において、勉強とは自分の慣習を壊す「自己破壊」だと強調しました。それとは別の言い方ですが、今の状況下では、攻めに出るというよりは身を守る勉強というものに関心がある。世間はさまざまな意味で我々を拘束し、利用し、使える人材として「エンパワー」してくる。「エンパワー」は本来、マイノリティの力能を活性化するというプラスの意味で使われる言葉ですが、そこには二重性を読み取るべきでしょう。世を生き抜くためのエンパワーメントとは、順応化でもあるわけです。それに対して、個人としての時空間を楽しむといった、そういう面を支援するようなミクロなエンパワーメントを考えなければいけない。それが護身術としての勉強ということです。自分自身の時空間とは何かを積極的に考えなければ、私たちは巨大なシステムの歯車になってしまう。身を守るための勉強は、そもそも守るべき「身体」を作るための勉強と言い換えてもよいでしょう。あるいは、プライバシーを創造するための勉強が必要なのです。

『勉強の哲学 来たるべきバカのために』千葉雅也=著 2017年 文芸春秋
言語論と物質論
池田 身を守るための勉強ということを言われました。身体性や個体性の問題と言い換えることもできるかと思いますが、これは千葉さんの主著である『動きすぎてはいけない』でも強調されたテーマですね。僕はもともと千葉さんを、身体性や物質性を強調する人だと思っていたので、『勉強の哲学』は初めて読んだときは、やや意外にも思いました。というのは言語の問題にかなりフォーカスして書かれているからです。例えば國分功一郎さん『中動態の世界』や、あるいは前回のゲストである星野太さんの『崇高の修辞学』もそうですが、共通して言語への注目が見られます。千葉 みんな言語論ですね。
池田 千葉さんも深く関わられている思弁的実在論にしても、大まかに言えば言語的なものよりは存在の実在性といった問いを立てているように見えます。今回、言語の問題に注目しようとしたのは、どういったところからだったのでしょう。
千葉 思弁的実在論または思弁的転回について、かつては言語的次元にばかり注目していたことに飽き飽きしたからモノの次元に行ったのだという見方がありますが、人間の思考を考えるに、言語の次元と身体・物体的次元が両方大事であるのは自明なことです。僕はずっと両者の関係を考え続けています。僕が友人たちと思弁的実在論を翻訳紹介したからといって、言語の次元はもう時代遅れだなんて意味を込めた訳ではまったくありません。
『勉強の哲学』では、言語の物質性、言語の「かたち的次元」、「言語の身体」を問題にしていると言えます。言語を身体的に操作することが「詩」であると言っている。そういう次元は、コミュニケーションの論理性からは排除されがちな、無意味なものですが、言葉遊びをするときにはそれが浮上してくるのです。言語活動には、論理的な意味と同時に、形態-身体的で無意味な構築性がある。それが、詩や美術で取り扱われている。
無意味な形態のレベルで言語を操ることによって、自分独自の文体、言語に対する享楽的な結びつき(あるいは距離)を作り出すことになる。そのレベルで、自分の言語-身体の輪郭が確保される。それが、自分のプライバシーを造形する根本的な操作なのだと僕は考えているのです。脱コミュニケーション的に自分を造形する。
池田 言語と物質性の問題が重なり合うところにフォーカスしているわけですね。ところで、前々から千葉さんが自己啓発書をよく読んでいると聞いていたんですが、今回かなりこの啓発書スタイルに擬態しているように見えます(笑)。本書で言われるような「あるノリから別のノリへの引越し」を書き方のレベルで実践しており、そのことが本の構造そのものに及んでいる。『動きすぎてはいけない』は複雑なインスタレーションのように、様々な議論の間に複雑なリンクが張り巡らされていて、その繊細な網の目が一つの構造体を作るような空間的な作品であったのに対し、『勉強の哲学』では、かなり強くリニアな構造になってますね。
千葉 弁証法になっていますね。あるいは、僕は『勉強の哲学』によって時間、持続について考え始めた、とも言えるのかもしれない(笑)。持続の問題というのは、考えてみるとこれまでオミットしていたように思うので。
池田 途切れることを含み込んだ持続というような。
千葉 細かな切断が間に挟まれている持続、ということですね。中断を常に挟みながら作業を続けていく、ということを扱っているわけだし。
池田 そうした中断を挟んだ持続の中で、あるノリから別のノリへの引っ越しが起こるのだけど、それはどんなノリにでも自由自在に対応できるようになる、ということではない。
千葉 そうですね。
池田 同時にそれは全く周囲のノリから隔絶した、孤高の状態になるわけでもない、と。
千葉 それはまさにマラブーの図式なんですよ。つまり「フレキシブル」(流動的)で、なんでもかんでもに変身可能というわけでもなければ、逆に、完全に「硬直的」な一匹狼になればよい、という話でもない。フレキシブルでも硬直的でもない、「プラスティック」(可塑的)な状態があるというのがマラブーの三項図式なんだけど、そう考えれば僕の「ノリからノリへ」という議論もそれに当てはまる。重要なのは、ある二つのノリの間に言語の物質性が立ち上がることによって、我々が不器用に言語に向き合わざるを得なくなるということです。ノリからノリへ移動する、つまり複数の環世界を移動するときに、言語を使う我々が、まさに言語において物質的な何かに出会う。それが単なる流動性に向かわないためのバリアになるわけです。
池田 「あるノリから別のノリへ」という話で言うと、『動きすぎてはいけない』での「胡蝶の夢」についての言及を思い出します。荘周が夢を見ていて、夢の中では蝶になっているが、ふと目がさめるとまた荘周であると。中島隆博先生の議論を踏まえつつ、ある有限性から別の有限性への移動という議論をされています。
千葉 そうですね。「閉じられ」から「別の閉じられ」への移動といった話を僕は以前から展開してきたのだけど、それを最初にプッシュしてくれたのは中島先生の荘子読解ですね。そこでは、一つの世界への絶対的内在から別の世界への絶対的内在に生成変化するということが語られていて、僕はそれを「切り替わり」だとか「スイッチ」という風に表現して引き受けている。確かに今もそのテーマにこだわっています。そのとき二つの世界の間を媒介するようなもの、道(タオ)みたいなものを想定しないという話なんです。

ナンセンスな言葉遊びと作品制作
池田 アートと関連の深そうな論点についてお聞きしたい思います。『勉強の哲学』の第一章の中で、言葉をバラすことが語られています。言葉が何らかの目的のためのツールとして使われるのではなく、自己目的的に、つまり言葉を使うこと自体が目的となるような、遊戯のような言語使用。このとき言語は、現実から乖離した次元で扱われている。言語は日頃の僕たちの認識を規定してもいるわけですが、だからこそ言語を自由に操作することを通じて、この世界の別の可能性について考えることができる。こうした議論は『動きすぎてはいけない』の中で、フィクションや想像力の問題についてヒュームの議論をベースにしながら議論されている部分を思わせます。千葉 『動きすぎてはいけない』第二章の、連合説(アソシエーション)の問題を解離(ディソシエーション)として読み換えるという部分だね。まさにそうです。言葉は、ブロック遊びみたいに、パーツを交換したり、順序を変えたりできるわけです。例えば、「昨日トンカツ食べた」という文は、パーツを交換して「今日トンカツ食べた」に変えられる。あるいは、極端に音レベルでバラバラにして、「ノキウツカントベタタ」と言うならば、それは組み替えではあっても、もはや音楽みたいになってしまっている。それはリズムの形態ですよ。ノキウツカントベタタ、ノキウツカントベタタ、ノキウツカントベタタ…(笑)
「昨日トンカツ食べた」から「今日トンカツ食べた」への変化であれば意味的ですよね。「ノクツカントベタタ」はいかにもナンセンスです。しかし僕は、「ノキウツカントベタタ」と「今日トンカツ食べた」という二つの組み替えは同レベルだと思っている。それはスペクトル的に繋がっている。つまり、シーケンサーの上で音符のブロックをどんどんグチャグチャにすることで、元々は普通に聞こえるはずだったものをノイズミュージックあるいは無調音楽のように書き換えてしまうのと同じように、我々の言語の並び替え可能性は無調音楽の世界へ繋がっているわけです。
例えば「私はスキージャンプの選手になる」だとかいった、意味が通じるけど非現実的なフィクションを言うことで、自分自身の人生の課題が発生するということと、全くナンセンスな言葉の並びを作り出すということは繋がっている。意味操作を豊かにするということと、ナンセンスな文を作るということをスペクトル的に繋いでいるというのが『勉強の哲学』ではポイントです。実用的な言語操作可能性を上げることと文学的な言語操作可能性を上げることを同列で考えたいんです。それを試みた本というのは、おそらく無かったと思う。だから、この本では画期的な言語論的教育論をやっていると思いますよ。
池田 アートがもっている意味を、日常的な経験の中で位置づけしているとも言えそうです。
千葉 してると思いますよ。実用性に繋がるかたちで。ほとんどアート的で無意味な言語操作を行うことは、実用的な言語操作の能力に繋がるんだ、ということを僕は強く主張している。実用的な言語空間は文学的な言語空間の部分集合なんです。
池田 この本の中では、アート的、文学的な言語をナンセンスの極に位置づけている。このナンセンスの極まで行かずに引き返す、というのが勉強においては重要というわけですね。
千葉 そうです。始終無意味なこと言ってたらコミュニケーションとれないですから(笑)。しかしそれは「言おうと思えば言える」ということですね。そのあたりで僕が想定しているのは、タモリの言葉遊び、「ハナモゲラ語」ですね。僕は山下洋輔的な文化から影響を受けています。彼のピアノも、あれだけむちゃくちゃな演奏をしていても、他方ではすごくクラシカルな奏法もちゃんとできる。その二つがちゃんと繋がっているんじゃないかと思うんです。
『勉強の哲学』で述べた方法論というのは、ある意味で制作論です。既存のものに対し、自分なりの別案をどのように提出するのかということ。その二つの方法として、一つにはアイロニカルに「そもそも論」として、より抽象度の高い問題を扱うというパターンと、もう一つには既存のモデルの前提を疑うことはやめて別の様態に変換するというユーモアがある。ユーモアは隠喩的だとも言える。
この本ではナンセンスの手前で留まるように促していますが、芸術の制作論として応用するのなら、意識的に、ある操作可能性の範囲でナンセンスを繰り出す方法を示していることになると思います。
池田 美大なども含め、アートの実作の現場では自己分析が行われることが少ないように思いますね。自分がどんな傾向性を持っているのかを意識し、どのように実作に取り組むべきなのか、制作を継続していく上での実践的なヒントになるようにも思います。
千葉 似たようなことを村上隆さんがおっしゃっていたようにも思います。習慣化してしまっている形態とか色彩への固着になんらのメタ意識のメスも入れないまま、ずっと続けているというのは困りものだと思う。自己分析の刃を入れて自分の構成要素を解体する必要があると思うんだよね。それでも残ってしまう、どうしようもない「偶然性のクズ」みたいなもの、人間はそれを頼りに生きていく。
池田 村上隆さんはまさに自己分析型ですね。単なる自己享楽の反復に陥りがちな美大的な教育に対し、欧米型の現代美術のコンテクストを踏まえながらの戦略化を唱えています。千葉さんの話だと、こうしたアイロニカルな分析性に、もう一度ユーモアの横滑りが必要だということになる。
千葉 それだけだと、「市場を分析して株式投資しなさい」という話と同じですからね。それだけではアートではない。村上さんの作品にだって、彼自身の形態に対するこだわりがあり、その次元と現状分析を組み合わせてますよね。この組み合わせは、あらゆる分野において一般的な方法でしょう。当該分野の世界的規模の市場でどのような現状があるのかという分析と、自己分析を通して残った享楽的な「クズ」の部分というものを絡み合わせたときに何が起こるのか。これが一般的方法じゃないですかね。
享楽と自己内在性
池田 『動きすぎてはいけない』では、そうした享楽的なこだわりというものが、セルフエンジョイメント、自己目的的な楽しみとして扱われていました。千葉 そうですね。本書ではセルフエンジョイメントについて、後期ラカン的享楽論で言い直しているわけです。でも、まだ考察は十分ではなくて、「セルフエンジョイメント」よりは細かくなったとは思うけれど、ラカンの図式に乗っかっていますからね。その点は、今後も研究を深めていきたい。ともかく、非意味的切断を「孤独な享楽」との関係で生じるものとしたことは、『動きすぎてはいけない』からの展開です。「享楽的なこだわり」というのは自閉症的なモメントですよ。これについては、松本卓也との対話の中で理論的バックボーンを与えられました。
池田 少し強引につなげることになりますが、松本卓也さんが監修された『atプラス』の特集のなかで小倉拓也さんが「老いにおける仮構」という論文を書かれていて、示唆に富んでいると思いました。ここでドゥルーズの時間論をつうじて検討される老いや痴呆の問題は、いま話された享楽の議論と関連づけられるんじゃないかという気がします。
雑にまとめると次のようなものです。僕たちが過去-現在-未来といった経験の連続性を構成するときに、そもそも瞬間ごとに飛び込んでくる情報があり、こうしたバラバラな瞬間が「想像」によって総合されることで、一応の連続性を持った現在が立ち上がる。老いや痴呆において、こうした「想像」によって可能となるリニアな「現在」がままならなくなり、世界がバラバラの瞬間にほどけていく事態が前景化する、と。この時に痴呆老人の語る、他人からすると妄想にも見えかねない「作話」とは、こうしたカオスへと崩壊しかねない状況においてなお、その人なりの現在を、あるいは主体「のようなもの」を仮構するための、なけなしの方法でもある。
千葉 過去を喪失し、インプットされる知覚の断片を抱きとめるアルバムが存在しないなかで、つまり、アドホックな繋がりしか作られないという状況で、どう「つぎはぎの主体性」を立ち上げるのかという話ですね。『勉強の哲学』では、そこまでエクストリームな状況は想定していませんが、ユーモア的に目移りしながら、一つの主体性をギリギリ成立させることは可能なのか、という話は、まさにそういうことです。まあ今の話だと、ユーモア的に勉強する主体が、作話することでなんとかアイデンティティを繋ぎ止めている痴呆症者と同じですよということになるから、読者がビビっちゃうかもしれないけどね(笑)。なのでそこまで言ってしまって良いのかは迷うけど、理論的にはまさにその通りです。
池田 これをむりやりアートの話とつなげると、僕がここで想起するのはモネとセザンヌなんですよね。モネは印象派のエッセンスを高純度で精製したような人で、例えば移ろいゆく水面のイメージを、その瞬間的な印象をそのままに留めようとする。留めようとするけれども瞬間的な印象に対して描くことは遅れを伴うので、連作という形で、ある意味で作品がバラけていくこととなる。あるいは白内障を患った後のモネなどは、瞬間的に見ることすらままならず、ほとんど抽象表現主義のような非形態的カオスへと直面してしまう。
一方でセザンヌは、こういう瞬間的印象を追求することの臨界点にあるようなモネ的な事態に対して、即時的に印象が移り変わっていくなかでなお、いかに瞬間をつぎはぎしながら、かろうじて持続的な形態を仮構していくかというふうに時間の問題を立て直そうとしているようにも見える。この辺りは、千葉さんの言われる享楽の問題と関連して考えられそうな論点のようにも思います。

池田剛介
準-他者と人工知能時代の精神分析
池田 ともあれ一般的に言えば、アーティストの場合、モネやセザンヌのような主体のリミットが問題というよりも、そもそものアイロニカルな分析なしの決断主義にもなりがちなんですよね。出発点としては一つの自分のこだわりからスタートしていたとしても、美大を卒業して続けていくというなかで、ひたすら再生産のループになってしまうというパターン。延々と同じスタイルで続けていれば、そのうち誰かが拾ってくれるかもしれない、とか(笑)。『勉強の哲学』では、そのような状態を脱するための精神分析を自分で行うように促しています。これはとても面白い。精神分析は通常、精神分析家と向き合うことで自己の内なる欲望に光を当てるものと見なされていると思うので。千葉 もちろん「本物の」精神分析は、一人ではできません。しかし、多少の自己分析は、やらないよりはやったほうが良いと思うんです。例えばネトウヨの人が「なんで自分はこんなことにハマっているのだろう」と反省することでマジックが解けたりするケースはありうると思うんですよ。もちろんそれは精神分析「もどき」でしかありません。精神分析は、分析家という「他者」のプレッシャーのもとでやるからこそ意味があるのだ、という批判は当然あるでしょう。それはまったくその通りだと思う。
ただ僕は、一つの哲学的可能性として、十全なる「他者」ではないにしても「準-他者」あるいは「半-他者」との関わりによって精神分析的プロセスと似た効果を起こせないか、ということを考えているんです。自己啓発書でも、自分自身についての振り返りをよく求めますが、精神分析ほど強くは効かない。すぐ効果が薄れてしまうサプリみたいなものだから、何度も投与しないといけなくて、何冊も同じような本が出てくるわけです。このこととの関係で、例えばノートのようなツールのもっている他者性について考えてみたい。人間の十全な他者性には及ばない他者(例えばノート)との関わりの中で、自分自身をなんとかするという自己のテクノロジーに興味があるわけです。
これは強い意味での他者がいなくなっていくような時代における精神分析について考えているとも言えるでしょう。人工知能相手に精神分析は可能か、といった問いも考えられます。そんなのは問うまでもなく、精神分析ごっこにすぎないと批判されるかもしれないけれど、人工知能時代の精神分析を真剣に考えるという問題設定はおもしろいと思うんですよ。
池田 専門家を通じて行われるのではなく、むしろ中途半端であることによって、意識として「仮に」固定されるとも言えるのかもしれません。中途半端であるがゆえにそれは仮のものでしかないけれど、仮であるからこそ、さらなる自己分析へと開かれているとも言えそうです。
千葉 そうとも言えますね。よく誤解されがちですが、精神分析の実践は、必ずしも分析家が決定的な解釈を投げてくれるものではないんです。僕の知っている範囲ですが、ほとんどなにも言わない分析家もいます。分析家は、根本的には「プレッシャー装置」なんですよ。ラカン派精神分析では、自分=クライアントを「被分析者」とは呼びません。「分析者」と呼びます。分析するのはあくまでも自分なんですね。だから精神分析は、特殊な状況下における自己分析なのです。これは異論があるでしょうけど、ならば、精神分析家のいるところでカウチに座るという強く特殊な状況とまではいかなくとも、何らかの他者性が働いている状況で自己分析をすることの意義はあるんじゃないのか。しかし「効果が決定的に異なる」と分析家は言うと思いますが。
池田 AI時代の自己分析というのは、AIから精神分析を受けるということでしょうか?
千葉 AIが横にいる状態で精神分析をする、ということです。横にいるAIがなんらかのレスポンスをするでしょうけど、我々にとってそれが「人間の他者が隣にいる」というプレッシャーにどこまで近づきうるのか、ということ。すごく単純な話ですが、我々は一人では物事を決められませんよね。いろんな可能性を考えるのだけれど、一つ決定を下す時には、背中を押してくれる他者の審級が介在している。実際に誰かに相談するわけじゃなくても、心の中にそういう潜在的な他者がいて、背中を押してくれている。元を辿れば、子供が何かをするときに親がそれを許したり禁止したりするということが我々の中に刻み込まれていて、それを変形することで色々な判断をしているというのが精神分析の見方です。自分が何かを判断するという時には、自己の中にバーチャルな他者が発生している。ではそのバーチャルな他者を、自己の外にあるバーチャルな他者から調達できないか、ということですね。
池田 勉強の場合、そうしたバーチャルな他者がノートやアプリケーションであったりする。
千葉 そう。なぜ僕がああいったライフハックツールみたいなものに興味があるのかというと、他者論の問題だからですよ。そこまで穿って見ている人はなかなかいないと思うけれど(笑)。僕がEvernoteやWorkflowyなどにこだわっているのは、我々がある一定の範囲の思考を成立させ、それを作品化するときに働く他者性をどうマネジメントできるのか、という問題に関心があるからです。

「作品」という単位の再設定
千葉 池田くんは作品を作る上で、一定の仕上がりに到達する時に、どういう判断をしています?池田 仕上がり、あるいはどのように制作を区切るのか、ということですね。締め切りや支持体の大きさといった外在的な要素もあるわけですが、僕の場合、どのように制作を方法論化できるか、という問題がある気がします。方法論的な指針なしに自分の感覚で「自由に」制作するということができない。
保守的に聞こえることを承知で言うと、僕はもともと印象派や抽象表現主義といった近代絵画に関心があって、いまだにそういう問題がバックボーンになっているところがあります。さっきのモネとセザンヌの話の延長上で言うと、印象派から抽象表現主義へというラインを日本で最も批判的に引き継いでいるのは岡﨑乾二郎さんでしょう。一見すると抽象表現主義的に、カオス的にブラッシュストロークを散らせているように見せかけながら、じつは型紙を使って要素を反復させたり変形させたり、ということをやる。
僕のなかでのプロジェクト的な作品はまた少し別として、絵画的な作品はもともと岡﨑さんの仕事の延長上にあると思います。金魚や木の葉といったエレメントを型取りして作り、それをブラッシュストロークのように配置しながら平面作品にしたりしていますので。最近では、雨や結露のような日常的な自然現象を型紙を通じて平面化していたり。一見すると自然現象が発生しているようにも見えるけれど、そこに人為的な操作の次元を介入させていくという感じですね。こういう「型」的なものが、僕にとっての他者のようなものかもしれません。
もう少し一般化すると、今どのように「作品」という単位を成立させることができるのか、ということが美術においては難しくなっていると思います。リレーショナル・アートやソーシャリー・エンゲージド・アートなどと言われたりしますが、人々がコミュニケーションする場を作ったり、何らかの歴史的・社会的な事象をリサーチして資料を並べたり、まあなんでもありという状況なわけですね。そのなかで作品にどのような有限性を与えるのか、つまり作品としての「仕上がり」がどのように可能なのか、というのは大きな問題だと思います。
千葉 デューリングのプロトタイプ論はまさにそういう話ですね。あれも形態化の問題を扱っているのでしょう。
池田 そうですね。一方ではコンセプチュアル・アートやプロセス型アートのように理念や不完全なプロセスのみを提示することによって「作品」が霧散し、他方ではデュシャン的な非制作の身振りが特権化されるということが起こる。これらをひっくるめてデューリングは「ロマン主義」と呼ぶわけですね。こうした状況の中で、モダニズム的な自律したオブジェに戻るというものでもなく、単に理念を暗示するような不完全なプロジェクトとも異なる、これら両者を組み合わせるような作品化の次元をプロトタイプと表現しています。一定の理念的な連続性を持ちながら、かつ作品の単位をその都度「仮固定」していくもの、と言うこともできるでしょう。
千葉 僕の強調しているような、中断を挟みながら行う勉強というのは、プロトタイプの制作を続けるということに近いのでしょうね。例えばデュシャンの《泉》は、アイロニー的であって、作品とは何か、美とは何かという「そもそも論」の掘り崩しなわけですが、同時にオブジェの形状それ自体も提示されていて、それはユーモア的なアプローチでもある。かたちとして「仮固定」されているわけですから、あれを単にコンセプトあるいはプロジェクトと捉えるのは不十分で、アイロニーとユーモア、そしてユーモアの中に含まれている非意味的形態の面白さを両方読み取らないといけない。
池田 「そもそも論」的な側面だけで捉えるのではないデュシャンということで言えば、美術のコンテクストに対するアイロニカルな操作として理解されがちな《泉》に対し、例えばスティーグリッツの撮った有名な写真やそのトリミングを通して形態的な検討を行うといった議論も思い出します(マイケル・R・テイラー「ブラインド・マンの去勢」、『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展カタログ所収)。デューリングにしても、デュシャンの非制作を特権化するのではなく、ダイアグラムや各種のメモをプロトタイプとして捉えるという見方をしているので、中断を挟みながら作品として仮固定させていくということですね。加えて言うと、デュシャンは基本的に「洒落」の人なので、言葉遊びの問題も含め、『勉強の哲学』と響くところがありそうです。
千葉 僕は基本的に、すべてのことを洒落の次元で考えようとしたいんでしょうね(笑)。実用的な知性のあり方と、ダジャレ的な知性のあり方は繋がっている。これもまた精神分析の考え方ですが、ダジャレというのは形態と形態の類似性、あるいは形態と形態の変換で成立している。無意識というものはそういう成り立ちをしているというドライな見方がフロイト、ラカンにはある。
僕は人の個性の形成は、その人の中にある基本的な形態のパレットによって行われるのだと思っています。その形態のパレットの中で変換を起こすことで、ダジャレもできれば意味のある文もできる。個々人の公理系ならぬ「形態系」によって変更が行われるような、人生の芸術化を考えているんです。ここで僕は「形態」というものをすごく抽象的な意味で使っています。視覚的なかたち、聴覚的なパターン、味覚、嗅覚、触覚も、すべて僕は「形態」と呼ぶ。そういったもののパレットをどう操作していくかという観点で、ファッションや言語の問題を統一的に考えている。形態系の操作、それが、僕が様々な諸分野を横断して考えるときのメタゲームなのです。
池田 面白いですね。現代美術において「かたち」について考えるフォーマリズムは古い問題とされ、その後コンセプトやコンテクストの時代になったと言えるでしょう。特定の文脈をうまく巻き込みながら、期間限定の展示の場でのプレゼンテーションを考えることが求められる。特に芸術祭のような様々な状況にフレキシブルに対応するためには、作品の形態などむしろ邪魔とすら言える。そのなかで、もう一度作品が何らかの形態として帰着する点について考えることは、デュシャン以降の現代美術のありかたを根本的に問いなおす上でも重要だと思います。
千葉 そうですね。僕は「純粋な観念」というものがよく分からない。基本的に僕はフェティシスト的だと思っているし、そこにもう居直っていて、フェティシストの論理を普遍化しようとすら思っている。しかし例えば観念と言っても僕たちは言語を使わざるをえないし、言語は絶対に形態性を伴う。どんなに観念の次元を考えたとしても形態の次元がなくなることはない。「それを超える純粋な理念に向かっていくことが大事なんだ」と言われたとしても「それが好きな人もいるんでしょうねえ…」と思うしかない(笑)。
さらに言えば、純粋理念に向かっていくというのはサディストなわけですね。ドゥルーズのマゾッホ論でいえば、形態性が残っている限りは否定性は十分に働かないということになるので、徹底的に形態性を批判して純粋理論の状態を目指すと「いわく言い難いもの」にしかならない。ですが、もしそれが思考可能な理念だとするならば、それはなんらかの形態を持っているはずです。クロソウスキーが解釈するところのサドみたいに突き進んでいくと、いかなる区別もないような純粋な自然との合一が純粋理念の実現だということになってしまう。それがアナーキーだということなのだろうけれど、しかしそれは単に一つの極点でしかないので…
池田 そこから先に進みようがない。
千葉 そう、漸近的にその一点に極まっていくしかない。そうじゃなくて多様な作品、あるいは多様な個性が可能だとしたら、それは形態的な次元でしかあり得ない。複数性という概念と形態性という概念は不即不離であって、形態性の概念を捨てたら複数性の概念は成り立たないと思う。ここはまだ厳密に考えなければいけないけれど、直感としてはそう思っています。東浩紀における複数性の議論を、形態性の問題として引き受けているということでしょうか。
池田 重要なポイントですね。東さんの議論では、トラウマのように否定神学的に担保される超越性を複数的に開いていく、ということが言われる。この延長上で千葉さんは形態の問題を考えていると。しかしそれは、いわゆるフォーマリズムのように強い自律性をもった形態というのではなく、その都度に仮固定されながら変容にも開かれているし、しかし変容しすぎない程度に仮の形態化をし続けることでもある。
千葉 そう。だからここでいう形態性とは、フォーマリスト的な決定的で一回的なものではない。常にだらしない形態なわけです。だらしない形態から、だらしない形態へ移りゆく(笑)。
池田 そしてそれは言葉遊びのような、洒落的な形態でもある。
千葉 洒落から洒落への変換、それがユーモア的なアプローチということですね。ドゥルーズのマゾッホ論をそのように読み替え、実存論でもあるし芸術論でもあるものとして再利用する。
『動きすぎてはいけない』のマゾッホ論で重要なのは、形態概念に注目しているところです。僕の知る限り、そのような先行研究はない。サドは形態破壊的でマゾは形態的。これをフォーマリストと訳すのも形式主義と訳すのもニュアンスが違うと思う。僕はそれを「形態的」と呼ぶことでドゥルーズの議論のポテンシャルを引き出そうとしました。こうした形態の操作に関する議論で僕がイメージするのは「ブロック遊び」ですね。粘土ではなくてブロック。離散的なものの組み合わせだからね。
池田 『感覚の論理学』でのドゥルーズだと、フランシス・ベーコンの絵画をベースにしているので粘土的と言えそうです。千葉さんの場合、それぞれのエレメントが強く区別されていて、区別されながらもブロック的に組み合わされていく。
千葉 ベーコンが餅だとすると、僕が考えているのは米だね(笑)。
池田 粒に輪郭がある(笑)。

九鬼周造とグレアム・ハーマン
池田 REALKYOTOが京都のメディアということで言うと、洒落について想起するのは九鬼周造ですね。千葉さんも九鬼には注目されていると聞きます。九鬼は意固地のもつ張りと諦念的な緩みの緊張関係によって「いき」が現れると考えた。九鬼にも輪郭やストライプ状のもの、総じて線的なものの重視があります。千葉 九鬼周造において重要なのは、他人は他人に決して入り込めない、という感性ですね。そういう他者との間で「不完全に開かれる」のが、媚態的、エロス的関係なわけでしょう。相手のことを完全に説明可能に理解できてしまったら、そんな相手に恋するわけがない。そういう分からない他者が自閉的にあるからこそ開かれるコミュニケーションの可能性がある。日常生活においてそういうコミュニケーション可能性は、とくに恋愛において実感される。恋とは、相手が「閉じている」からこそ生じるようなコミュニケーションであり、そこに九鬼は照準を合わせた。彼は偶然性の問題として、これを「独立なる二元の邂逅」と述べているわけです。
あるいは、異なる因果系列の出会い。因果系列が別であるとはつまり、それぞれの因果系列が内在的に「閉じている」ということであり、そうした別の因果系列をもつ存在を他者と呼ぶことができます。だから僕は、九鬼の考えていたある種の夜遊び論を存在論的に一般化すれば、他者と他者が出会うことを一般に抽象的な意味での恋愛関係として捉えられると考えています。世界を走っている複数の因果系列がそれぞれに「自閉性」をもっていて、その間に恋愛的な惹きつけと分断がある。
池田 そう聞くと、グレアム・ハーマンによる世界観にも近いように聞こえます。
千葉 そうね、彼はそれを「魅惑」というように表現するわけでしょう。
池田 実在的な次元では個別の存在がそれぞれに引きこもっており、しかし感覚的な次元では「魅惑」を通じた交流のようなものが行われている、と。逆に言えばハーマンの魅惑論を九鬼のような恋愛論に引きつけることも可能かもしれませんね。
千葉 ただ僕が若干ハーマンに抵抗を覚えるのは、彼の考えているオブジェクトの引きこもりというのは、無限性と結びついているように思える点です。ハーマンが考えている個物というのは、端的に言えば神ですよ。ハーマンは、レヴィナス的な意味での「無限に遠い他者」を、アルフォンソ・リンギスなどを媒介としつつ脱人間中心化した上で、存在者一般に展開しているのだと思います。ペットボトルだろうがMacBookだろうが、全てがレヴィナス的な意味での「他者」だと。そこには何らかの神学性が残っているような気がする。
しかし九鬼の場合、二元が出会うという時に、それぞれの引きこもり性を「無限に遠い」と考えていたかといえば、そうではないと思う。僕はここが大事だと考えています。ハーマンにおいて個物は、無限のエネルギーの貯蔵庫であって、そこからありとあらゆる状況の変化が溢れ出てくる。そうした「エネルギー源」のようなものをハーマンは想定しているのだけど、九鬼はそれを考えていない。つまり「奥」を見ていない。
池田 なるほど、より徹底して表層的なわけですね。
千葉 僕はそこがとても重要だと思う。奥にある他者性のエネルギー源というものを想定しない引きこもり性というものに僕は興味があって、それは今後もっと展開したいですね。
池田 ハーマンは個別の存在の実在的な次元での引きこもりを前提とするのに対し、九鬼の議論では、表面的な魅惑の交換はあるが、実在的レベルでの深さを想定しない、と。
千葉 そう。控えめに言って、それを想定していたかどうかが分からないというところが解釈上のポイントなのです。彼はだんだんある種の日本論に入れ込んで、伝統を語るようになりますが、そこで、ナショナリズムがその「奥」を保証している可能性はあるでしょう。だけれど、九鬼はハーマンより軽やかで、表面的かつドライだった。このことは、趣味のレベルとして片付けるのではなく、存在論的に捉え返すべきではないでしょうか。
それに、なんというか……実在的オブジェクトがあり、実在性の源がありますよ、なんて言われると、ちょっと僕は興ざめしてしまうんですよね。野暮だと思う。続けて直感的に言うのだけれど、他者との距離がある中で「魅惑」されると言うときに、「なぜ近づけないか?」という問いを「無限に深いからだ!」と結論づけちゃったら、もうそれは野暮天だと思うんですよね(笑)。
池田 (笑)。
千葉 そこを言わないから「いき」なんですよ。これを言い換えると、「他者」が「他者」であることの根拠を語ってしまったら、「他者」の存在構造が安定化してしまう、ということです。「他者」が不安定な存在でいられなくなってしまう。他者が他者だからこそ距離があって恋をするのだけれど、でもその他者は実は他者じゃないのかもしれず、自分の分身かもしれない。そのあわいにある不確実さにまで鋭敏な感覚を届かせていたのが九鬼じゃないか、という気がするのです。
池田 確かに九鬼には、ある種のゆるさ、つまり互いが完全に切り離されておらず、偶然的に交差するのかもしれない「遊び」のような余地がある気がします。そもそも完全に区切られていて、そこに十全たる実在性があるというのではなく、むしろそれぞれの個体の実在性も「仮」の状態にある、と。
千葉 そう。だから、はっきり他者を無限の奥行きのある他者だとしてしまうのは、精神分析的に言い換えれば去勢成立以後の他者の捉え方なんですよね。ハーマンの世界はそこから出発している。しかし僕が考えたい他者性というのは、去勢が成立していく途上にあるのだと思う。去勢が成立する途上においては、去勢を可能にする他者性が十分に成立していない。そこでは、確かに他者らしいのだが、もしかすると自分かもしれないという「とりかへばや」的な曖昧な状況がある。ここで付言すれば、『君の名は。』みたいな作品がなぜ日本で作られるかというと、まさに去勢の成立途上というものが問題とされているからだと思うんです。その状態が発揮する独特のリリシズムというのを、あの作品はもっている。だから、あの作品を「他者を描けていない」と批判するのは、肝心なところが分かっていないと思う。
この点はまさに『勉強の哲学』での問題意識につながるところでしょう。なぜ僕がこの本で、擬似精神分析的なやり方をとったかといえば、他者が他者として十分に成立しないところでの精神分析は可能かという関心があったからなんです。他者が他者である保証がないところで、精神分析的思考は可能なのか。それは「日本的」問題なのかもしれません。
(2017年5月30日、元新道小学校・池田剛介アトリエにて/2017年9月20日公開)

(Photo: Kanamori Yuko)
ちば・まさや
1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。パリ第10大学および高等師範学校を経て、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。哲学/表象文化論を専攻。フランス現代思想の研究と、美術・文学・ファッションなどの批評を連関させて行う。立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。著書に『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生変化の哲学』、『別のしかたで――ツイッター哲学』、訳書にカンタン・メイヤスー『有限性の後で――偶然性の必然性についての試論』(共訳)がある。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。