見立てと想像力
小崎 哲哉
2017.10.12
『見立てと想像力——千利休とマルセル・デュシャンへのオマージュ』と題する展覧会をキュレーションした(10/22まで@下京区の元・淳風小学校)。ニュイ・ブランシュKYOTO2017のメイン企画のひとつで、アンスティチュ・フランセ関西に依頼されたものだ。今年は、デュシャンの名(悪名?)を世にとどろかせた「Fountain(泉)」がつくられてからちょうど100年目。それを機に、アートファンや若いアーティストに「現代アートとは何か」という根源的な問いについて熟考してもらおうと考えた次第である。

既に在るものを選び、名付け、新しい見方を示す。デュシャンが創出したレディメイドとは、詰まるところこういうことにほかならない。この手法は、魚籠や瓢箪を花入れに、釣瓶を水指に見立てた利休の茶の湯によく似ている。これに加え、東西の巨人に共通するのは、茶席のしつらいやアートの創作においては、連想や想起など、知性への刺激が最も重要だと考えていたことだ。展覧会のメインタイトルは、この2点を要約したもの。このお題に対して、日仏の参加アーティスト8名は十分に、そして見事に応えてくれた。

小松千倫は展示空間に保健室を選び、自らの体験と記憶に基づくインスタレーションをつくった。2歳になってすぐに小児がんの摘出手術を受け、後遺症として右半身と左半身に発育の差が現れたという。体力を維持するためにスイミングスクールに通わされ、いまも定期健診を受けるなどセルフセラピーを続けている。その事実を、術前術後の映像フッテージ、手術の痕を写したポートレート、かつて通っていたプールで泳ぐ自身を撮影したビデオ、左右素材が違う患者服などで淡々と表している。カーテンレールの陰に置かれたベッドは、例えばトレーシー・エミンのベッドとはまったく趣を異にする。重い主題と物語が、そこには不在の主人公を想わせて胸を打つ。

宮永愛子は、理科室に隣接した理科準備室を、過去と永遠に想いを馳せるための空間に変貌させた。特殊な釉薬をかけて焼いた器に耳を澄ますと、貫入のひそやかな音が聞こえる瞬間がある。かつては化石標本などが収められていた棚には、ナフタリンで象られた鍵やジグソーパズルの断片、そしてガラスに封じ込められた書物が陳列されている。少しだけ開けられた引き出しには本物の鍵が入っている……。まったく同じ会期で開催される個展の準備のため、作家は倉敷と京都を何往復もしてくれた。大原美術館の有隣荘での展示は、本展の対になるものとして、併せて観てもらいたい好企画である(10/22まで。「みちかけの透き間」)。
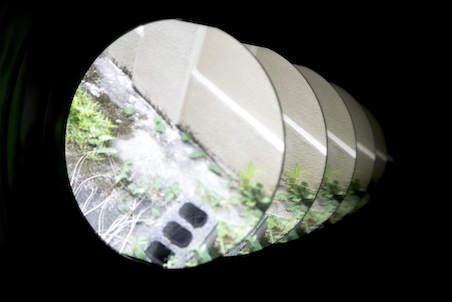
井村一登は、かつてはコンピュータ室だった部屋に、天体望遠鏡にも似た大がかりな装置を持ち込んだ。チューブ状の装置で、ひとつは天井に斜めに、もうひとつはその延長線上の床に設置されている。地球の内部に潜って移動するカプセルをイメージしたもので、チューブの断面にはチャールズ・イームズの「パワーズ・オブ・テン」を想わせる映像が映し出される。床から地面へ、地面から地中へ、地中でモグラのような生き物に行き当たり、その体内へ、体内の微生物へ、微生物のDNAへ、再び地中へ……。行き着く先はデュシャンの生まれ故郷ブランヴィル=クレヴォン。仮想のカプセルは何と、京都とフランスを往還するものだった! 雲に分け入り、空に飛び出す瞬間が快い。

セシル・アンドリュは、教室に200個の「苗帽子」を整然と並べてみせた。苗帽子とは、霜や雹、豪雨、冷気、強風、鳥害などから植物を守るための透明なカバーで、中には細かく裁断された紙片が詰められている。教室全体を200字詰めの原稿用紙に見立てたもので、教壇を囲む様子は、往時の授業を想わせる。座り込んで苗帽子の中をつぶさに見ると、紙片は各国語の辞典をシュレッダーにかけたものだった。子供たちは家庭で、社会で、学校で言葉を学び、脳味噌の中に放り込み、読み、話し、書くことによって知識と論理を身に付けてゆく。画一的に見えて、頭の中身はみな異なる。自らの子供時代、現代の教育の現場を、観客はこもごも頭に浮かべることだろう。

ジュスティーヌ・エマールは、教室前方の黒板にひとつ、後方の掲示板に7つ、小さな石を置いた。石はカットされ、切断面は色鮮やかな縞模様になっている。観客はスマートフォンやタブレットに特別なアプリをダウンロードし、柔らかな光のライトに照らされた石にかざすと、画面の石の断面に不思議な映像が浮かび上がり、耳に心地よい電子音が流れ出す(サウンドデザイン:原摩利彦)。作家曰く「これらの石は様々な時間のレイヤーとともに、ある記憶を体現しています。時の流れは直線的ではなく、中心部を囲むように形成されています。3Dのオブジェは、3種類の記憶を組み合わせたもの。オブジェの、人の、そしてコンピューターの記憶です」

世界でも有数のデュシャンピアン、すなわちデュシャン主義者、デュシャン信奉者である藤本由紀夫は(作家紹介にそう書いたら、本人に「恥ずかしいからやめてくれ」と言われて削除したが)、透明な樹脂でつくったベンチがひとつというミニマルな展示。ベンチには「LISTEN/SILENT」という文字が記され、室内には作家自らが演奏したコンピューター音楽が流れる。音楽はデュシャンが偶然性を用いて作曲した世界初のチャンスミュージック「音楽的誤植」(1913)。窓越しに西本願寺を眺めつつ、アナグラムの文字が刻まれたベンチに座って音楽に耳を傾けると、茶席や現代アートの意味に思いを凝らすことよりも、ただこうしていることの気持ちよさが体を浸してゆく。

漆の作家である染谷聡は、元・淳風小に残された机のほぼすべてを精査し、「景色のよい」天板のものを1ダースほど選んだ。作家は漆で生徒が刻んだり彫ったりした穴を埋めたり、落書きの筆跡をなぞったりして作品の台座とした。台座の上には、旧作新作取り混ぜて小さな作品が並べられている。中には、淳風小の校庭で拾った、なぜか家族のシール写真が貼り付けられた石もあり、作家はそれを覆う塗り物をつくって、写真の一部が見えるように穴を空けた。黒板や掲示板、さらに窓の一部は床の間に見立てられ、東寺の工事現場で手に入れたという番線が花のように飾られている。道具箱には判じ絵で「淳風小」の文字。教室には現在とは異なる時間が流れているように思えてくる。

八木良太は、理科準備室にあった実験・計測器具をいくつか選び、自作や、コレクションしている科学玩具と並べて展示。音楽室をサイエンスワンダーランドに生まれ変わらせた。LPレコードが宙に浮いている。「ニュートンのゆりかご」の名で知られる衝突球が、1列ではなく5個×5列吊り下げられている。驚かされるのは、コンパクト大の円い金属板が、鏡のような面の上で延々と回り続ける作品。板と面自体は「オイラーの円板」と呼ばれる科学玩具だが、作家は面の内部にマイクロフォンを仕込み、ヘッドフォンで回転音を聞かせる。その音がすごい! 認知科学的な関心に基づく作品が多いが、拡大鏡を並べたものは、デュシャンの「フレッシュ・ウィドウ」を連想させた。
アートに限った話ではないが、先人の思想やスタイルは、回り回って後世のつくり手に間接的な影響を与える。ギリシャ悲劇やシェイクスピアや世阿弥を知らなくても芝居は書けるし、グレゴリオ聖歌やバッハや黒人霊歌やパンソリやビートルズを知らなくても音楽はつくれる。とはいえ、現代アートに関しては、やはりデュシャンがどのような人物で、何を考えてあのような作品群を生み出したのかということを考えずに、創作したり鑑賞したりすることは不可能ではないにせよ不完全だろう。腕力で作品をつくる時代は終わった、と言われながら、いまだに腕力しか感じられない作品が目に付くのだから。
実は8作家には、利休とデュシャンへのオマージュ展であるということは伝えながらも、依頼としては「サイトスペシフィックなインスタレーションをつくってほしい」としかお願いしていない。昭和6(1931)年竣工の元小学校に、アーティストたちは申し分のない作品を創作してくれた。展示・サイン設計の岡田将充、展示設営のROCAも素晴らしい仕事をしてくれた。想像力を刺激されに、ぜひ会場を訪れていただきたい。

『見立てと想像力——千利休とマルセル・デュシャンへのオマージュ』展
会期=2017年10月6日(金)〜10月22日(日)
会場=元淳風小学校
トークイベント(入場無料 事前予約不要 先着30名):
10/ 7(土) 15:00–16:30 藤本由紀夫×セシル・アンドリュ(※終了しました)
10/15(日) 15:00–16:30 宮永愛子×八木良太
10/22(日) 15:00–16:30 朝吹真理子(小説家)

『見立てと想像力』展ポスター。AD&デザイン:岡田将充(OMD)
既に在るものを選び、名付け、新しい見方を示す。デュシャンが創出したレディメイドとは、詰まるところこういうことにほかならない。この手法は、魚籠や瓢箪を花入れに、釣瓶を水指に見立てた利休の茶の湯によく似ている。これに加え、東西の巨人に共通するのは、茶席のしつらいやアートの創作においては、連想や想起など、知性への刺激が最も重要だと考えていたことだ。展覧会のメインタイトルは、この2点を要約したもの。このお題に対して、日仏の参加アーティスト8名は十分に、そして見事に応えてくれた。

小松千倫(こまつ・かずみち)|Selpie(保健室) 写真:守屋友樹(以下すべて)
小松千倫は展示空間に保健室を選び、自らの体験と記憶に基づくインスタレーションをつくった。2歳になってすぐに小児がんの摘出手術を受け、後遺症として右半身と左半身に発育の差が現れたという。体力を維持するためにスイミングスクールに通わされ、いまも定期健診を受けるなどセルフセラピーを続けている。その事実を、術前術後の映像フッテージ、手術の痕を写したポートレート、かつて通っていたプールで泳ぐ自身を撮影したビデオ、左右素材が違う患者服などで淡々と表している。カーテンレールの陰に置かれたベッドは、例えばトレーシー・エミンのベッドとはまったく趣を異にする。重い主題と物語が、そこには不在の主人公を想わせて胸を打つ。

宮永愛子(みやなが・あいこ)|せかいのはかりかた(理科準備室)
宮永愛子は、理科室に隣接した理科準備室を、過去と永遠に想いを馳せるための空間に変貌させた。特殊な釉薬をかけて焼いた器に耳を澄ますと、貫入のひそやかな音が聞こえる瞬間がある。かつては化石標本などが収められていた棚には、ナフタリンで象られた鍵やジグソーパズルの断片、そしてガラスに封じ込められた書物が陳列されている。少しだけ開けられた引き出しには本物の鍵が入っている……。まったく同じ会期で開催される個展の準備のため、作家は倉敷と京都を何往復もしてくれた。大原美術館の有隣荘での展示は、本展の対になるものとして、併せて観てもらいたい好企画である(10/22まで。「みちかけの透き間」
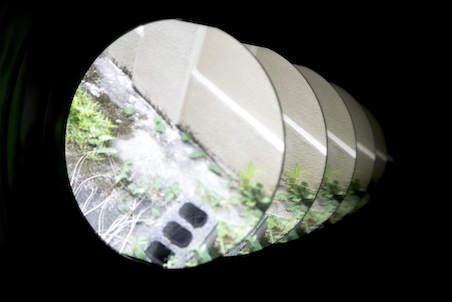
井村一登(いむら・かずと)|mirrorrim(コンピュータ室)
井村一登は、かつてはコンピュータ室だった部屋に、天体望遠鏡にも似た大がかりな装置を持ち込んだ。チューブ状の装置で、ひとつは天井に斜めに、もうひとつはその延長線上の床に設置されている。地球の内部に潜って移動するカプセルをイメージしたもので、チューブの断面にはチャールズ・イームズの「パワーズ・オブ・テン」を想わせる映像が映し出される。床から地面へ、地面から地中へ、地中でモグラのような生き物に行き当たり、その体内へ、体内の微生物へ、微生物のDNAへ、再び地中へ……。行き着く先はデュシャンの生まれ故郷ブランヴィル=クレヴォン。仮想のカプセルは何と、京都とフランスを往還するものだった! 雲に分け入り、空に飛び出す瞬間が快い。

セシル・アンドリュ(Cécile Andrieu)|Éclosion/孵化(1年い組)
セシル・アンドリュは、教室に200個の「苗帽子」を整然と並べてみせた。苗帽子とは、霜や雹、豪雨、冷気、強風、鳥害などから植物を守るための透明なカバーで、中には細かく裁断された紙片が詰められている。教室全体を200字詰めの原稿用紙に見立てたもので、教壇を囲む様子は、往時の授業を想わせる。座り込んで苗帽子の中をつぶさに見ると、紙片は各国語の辞典をシュレッダーにかけたものだった。子供たちは家庭で、社会で、学校で言葉を学び、脳味噌の中に放り込み、読み、話し、書くことによって知識と論理を身に付けてゆく。画一的に見えて、頭の中身はみな異なる。自らの子供時代、現代の教育の現場を、観客はこもごも頭に浮かべることだろう。

ジュスティーヌ・エマール(Justine Emard)|Exovisions(2年い組)
ジュスティーヌ・エマールは、教室前方の黒板にひとつ、後方の掲示板に7つ、小さな石を置いた。石はカットされ、切断面は色鮮やかな縞模様になっている。観客はスマートフォンやタブレットに特別なアプリをダウンロードし、柔らかな光のライトに照らされた石にかざすと、画面の石の断面に不思議な映像が浮かび上がり、耳に心地よい電子音が流れ出す(サウンドデザイン:原摩利彦)。作家曰く「これらの石は様々な時間のレイヤーとともに、ある記憶を体現しています。時の流れは直線的ではなく、中心部を囲むように形成されています。3Dのオブジェは、3種類の記憶を組み合わせたもの。オブジェの、人の、そしてコンピューターの記憶です」

藤本由紀夫(ふじもと・ゆきお)|Abode of Fancy(3年い組)
世界でも有数のデュシャンピアン、すなわちデュシャン主義者、デュシャン信奉者である藤本由紀夫は(作家紹介にそう書いたら、本人に「恥ずかしいからやめてくれ」と言われて削除したが)、透明な樹脂でつくったベンチがひとつというミニマルな展示。ベンチには「LISTEN/SILENT」という文字が記され、室内には作家自らが演奏したコンピューター音楽が流れる。音楽はデュシャンが偶然性を用いて作曲した世界初のチャンスミュージック「音楽的誤植」(1913)。窓越しに西本願寺を眺めつつ、アナグラムの文字が刻まれたベンチに座って音楽に耳を傾けると、茶席や現代アートの意味に思いを凝らすことよりも、ただこうしていることの気持ちよさが体を浸してゆく。

染谷 聡(そめや・さとし)|ディスプレイズム/淳風小加飾(ランチルーム)
漆の作家である染谷聡は、元・淳風小に残された机のほぼすべてを精査し、「景色のよい」天板のものを1ダースほど選んだ。作家は漆で生徒が刻んだり彫ったりした穴を埋めたり、落書きの筆跡をなぞったりして作品の台座とした。台座の上には、旧作新作取り混ぜて小さな作品が並べられている。中には、淳風小の校庭で拾った、なぜか家族のシール写真が貼り付けられた石もあり、作家はそれを覆う塗り物をつくって、写真の一部が見えるように穴を空けた。黒板や掲示板、さらに窓の一部は床の間に見立てられ、東寺の工事現場で手に入れたという番線が花のように飾られている。道具箱には判じ絵で「淳風小」の文字。教室には現在とは異なる時間が流れているように思えてくる。

八木良太(やぎ・りょうた)|確認するためのオブジェ(音楽室|1階階段下小倉庫)
八木良太は、理科準備室にあった実験・計測器具をいくつか選び、自作や、コレクションしている科学玩具と並べて展示。音楽室をサイエンスワンダーランドに生まれ変わらせた。LPレコードが宙に浮いている。「ニュートンのゆりかご」の名で知られる衝突球が、1列ではなく5個×5列吊り下げられている。驚かされるのは、コンパクト大の円い金属板が、鏡のような面の上で延々と回り続ける作品。板と面自体は「オイラーの円板」と呼ばれる科学玩具だが、作家は面の内部にマイクロフォンを仕込み、ヘッドフォンで回転音を聞かせる。その音がすごい! 認知科学的な関心に基づく作品が多いが、拡大鏡を並べたものは、デュシャンの「フレッシュ・ウィドウ」を連想させた。
アートに限った話ではないが、先人の思想やスタイルは、回り回って後世のつくり手に間接的な影響を与える。ギリシャ悲劇やシェイクスピアや世阿弥を知らなくても芝居は書けるし、グレゴリオ聖歌やバッハや黒人霊歌やパンソリやビートルズを知らなくても音楽はつくれる。とはいえ、現代アートに関しては、やはりデュシャンがどのような人物で、何を考えてあのような作品群を生み出したのかということを考えずに、創作したり鑑賞したりすることは不可能ではないにせよ不完全だろう。腕力で作品をつくる時代は終わった、と言われながら、いまだに腕力しか感じられない作品が目に付くのだから。
実は8作家には、利休とデュシャンへのオマージュ展であるということは伝えながらも、依頼としては「サイトスペシフィックなインスタレーションをつくってほしい」としかお願いしていない。昭和6(1931)年竣工の元小学校に、アーティストたちは申し分のない作品を創作してくれた。展示・サイン設計の岡田将充、展示設営のROCAも素晴らしい仕事をしてくれた。想像力を刺激されに、ぜひ会場を訪れていただきたい。

元・淳風小学校 1階廊下
『見立てと想像力——千利休とマルセル・デュシャンへのオマージュ』展
会期=2017年10月6日(金)〜10月22日(日)
会場=元淳風小学校
トークイベント(入場無料 事前予約不要 先着30名):
10/ 7(土) 15:00–16:30 藤本由紀夫×セシル・アンドリュ(※終了しました)
10/15(日) 15:00–16:30 宮永愛子×八木良太
10/22(日) 15:00–16:30 朝吹真理子(小説家)