1989年『Art & Critique』9号より転載
〈CROSSING〉森村泰昌展「マタに、手」
レビュー:建畠 晢、篠原資明
2016.04.15

森村泰昌展「マタに、手」
ON GALLERY(大阪)1988年11月14日〜11月26日
観念の官能性
建畠晢
写真の誕生は絵画に大きな影響をもたらしたといわれる。その検証は容易ではないが、ともかく写真のもつ機械的な再現性に絵画はおよぶべくもない。その分だけ絵画の富は奪われたともいえるだろうし、逆に自由になったともいえるだろう。極端な話、キュビスムや抽象は、写真が画家の想像力に与えた逆説的な浮力(機械的な再現性からの絵画の解放)によって初めて可能になった世界であるという見方も成り立つ。少なくともあの暗箱の中だけに限れば、写真とは精巧にして愚直な機械にすぎない。その偏見が稚拙にしてデタラメな絵画を可能にしたのである。あるいはゴテゴテと絵具を盛り上げた物質的な絵画(写真にまねはできまい)へと向かわせたのである。ときにはちょっとした反撃にでて、写真そっくりの絵(写真のまねはできる)をつくったりもする。かくして画家の被害者意識による珍説20世紀絵画史が展開されてきたのである。
しかしカメラではデタラメができないと考えられたとしたら、写真も見くびられたものである。そこである種の写真家たちは、デタラメへと逃げ込んだ画家たちを追撃すべく、カメラをもってこの聖域に押し入ってくるのである。つまり偏見がもう1つの偏見を生み出すという、因果応報である。カワイソウな画家の受難の時代はまだまだ続くというわけだ。しかしなかには心やさしい写真家もいないではない。そう、たとえば森村泰昌のように。彼ぐらいなものだろう。絵画への鎮魂歌を襟を正して荘重に歌うという、無慈悲きわまる思い遣りをもった若者は! 絵画の富、絵画の栄光に対する礼節をわきまえているという点で、この写真家の右にでるものはいない。いや実は彼は絵画などどうでもよく、虚構への虚構の意図を周知させるために、おなじみの美術史が少しばかり要り用だったに過ぎないのかもしれないが、西洋絵画を哀惜する私は偏見の偏見の偏見として、断固としてそれを“稀に見る礼節”と解釈する。余計なお世話だと言われれば、まだ死んでもいない(かもしれない、とトーン・ダウンしておくか)ものに手向けをするという余計な世話をやいてくれたのは誰だと言い返すまでである。
なにしろゴッホ、デュシャン、アングル、そして今回はマネである。奇しくも「笛を吹く少年」の実物は西洋美術館に招来されてもいる。この作品の森村の自らをモデルにしたパロディーは3点あって、中央の1点はほぼ原画に忠実であり、衣装や小道具も実に手がこんでいる。その左の1点はズボンが足もとまでずり落ち、下半身は裸、その脚の後ろから真っ黒な手が突き出して、股間を隠しており、右のものは同じポーズで後ろを向き、裸の下半身は黒く塗られ、逆に白い手が突き出ている。タイトルは「マタに、手」。おまけに(例の安物の複製印刷のように)写真の上から透明な塗料で見せ掛けの筆触がほどこされていたりする。ああ“稀に見る礼節”と言ったが、この酷薄なる精神にとってそれはやはり、“過激ないいかげんさ”と分かちがたいものだ。冒瀆し嘲笑しながら、聖なる絵画の中心に自分を置くことで、その光景は自己陶酔につながっている。しかも目は醒めており、冷静な演出にぬかりはない。ユーモアを観念自体の官能性として把握する資質に恵まれたこの若者は、たかが写真だというのに、まことに態度が不遜なのである。されど写真か。そんな切り返しもあったな。

会場風景(素材はいずれもカラー写真に透明メデューム他)
(掲載誌面より)
時間のエロティシズム
篠原資明
活人画という、いまはすたれてしまったジャンルがある。文字どおり、生きた人物が形づくる絵画的光景のこと。19世起前半の人、フーリエが、来たるべき時代に勝ち誇る芸術ジャンルと予言したにもかかわらず、活人画は時代からまったく忘れ去られたかのようだ。それでもバルトによれば、小さい頃まだ目にしたこともあるというから、少なくとも今世紀前半までは細々ながら命脈を保ってはいたわけだ。しかしこの活人画、ほんとうに消え去ってしまったのだろうか。
これは当然のことながら、あくまで仮説なのだが、活人画が歴史の表面から姿を消したのは、写真の出現と無縁ではないように思われる。カメラの前でポーズをとり続けるとき、われわれはすでにミクロなレベルで活人画を実践しているはずだからだ。そしてその活人画のシーンが移り住んだものとしての写真イマージュ。
このような話で始めたのは、森村の実践が活人画—写真をみごとなまでに地でいくもののように思われるからだ。彼の写真の場面設定は主に、美術史のコンテクストから借りられるものと、風俗から借りられるものとの、2つの系列に分かれるようだが、前者の系列に位置するもののほうが、より活人画的なのはいうまでもない。今回の個展のようにマネの作品から借りたものについても。
問題となるマネの作品は「オランピア」と「黒い帽子のベルト・モリゾ」、「笛吹き」の3点である。とはいっても、それらに対する処理は、それぞれ異なる。まず「オランピア」からは1点、「黒い帽子のベルト・モリゾ」からは2点、「笛吹き」からは3点が、それぞれワン・セットの作品として提示されているからだ。2点1組、3点1組といった一種の連作表現は、多くの連作がそうであるのと同様、プロセスを暗示するものともなっている。
展覧会のタイトルとなっている「マタに、手」は、一見ふざけただけのようでいて意外に意味深長である。それはひとつには、森村の作品を見た者がおそらく誰しも感じるエロティシズムの問題を、正面から提示していると思われるからだ。オランピアに扮した森村の手も「マタに、手」であれば、笛吹きの左右2点も「マタに、手」である。上半身だけのベルト・モリゾも、下半身が隠されていると取れば、一種の「マタに、手」だろう。とすれば、隠蔽する身振り(あるいは手振り?)のエロティシズムが、今回の作品全体をおおっているといってよい。各作品からのこれ以上の連想をエロティックに繰りひろげるのは控えるとしても。
活人画に話を戻すなら、画家のモデルも、画家の視線の前で一種の活人画を演じているといえる。それは苦痛を伴わずにはいられない作業だろう。それに、動くことを強制されるより、動かないこと強制されるほうが、ずっと苦痛を伴うのではないだろうか。それはおそらく、マネの気むずかしい視線の前で「笛吹き」のモデルを代わるがわるつとめた者たちが味わった苦痛でもあったろう。いまや、そのモデルたちの苦痛を、作者であるはずの森村自身がつとめるのである。しかも機械の眼の前で。
苦痛をとおしての喜び、それは美学的には崇高と呼ばれ、エロティシズムの用語ではマゾヒズムと呼ばれる。この2つは、一見無益なことに時間をかけるという点で結びつく。写真が短時間で達成するイマージュを、ことさら長時間かけて達成しようとするハイパーリアリストの身体について、リオタールが指摘したとおり。だが活人画的シーンに身を置く作者=モデルの身体についても、同じことがいえないだろうか。一方の身体は写真の後に位置し、他方の身体は写真の前に位置するとしても。ともあれ、活人画の演者にして、活人画写真の作者、森村は、こうして時間のエロティシズムを実践しているといえるだろう。

会場風景(素材はいずれもカラー写真に透明メデューム他)
(掲載誌面より)
『A&C』(Art & Critique) No.9
(1989年1月1日 京都芸術短期大学芸術文化研究所[編])
より再掲
—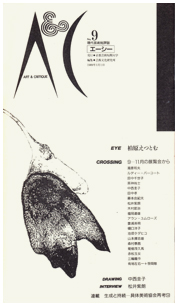
転載を許諾して下さった森村氏をはじめとする執筆者の方々と、『A & C』誌元編集担当の原久子氏、京都造形芸術大学のご協力とご厚意に感謝申し上げます。なお、記事はいずれも原文のママであることを申し添えます(明らかな誤字は訂正しました)。
(REALKYOTO編集部)
CONTENTS ▶『Art & Critique 5』〈DRAWING〉「美に至る病へ」へのプロローグ(文・森村泰昌)1988年
▶『Art & Critique 8』
〈TOPICS〉ベニス・ビエンナーレ——ベニス・コルデリア物語
(文・石原友明、森村泰昌)1988年
▶『Art & Critique 9』
〈CROSSING〉森村泰昌展「マタに、手」(レビュー・建畠晢/篠原資明)1989年
▶『Art & Critique 15』
〈CROSSING〉森村泰昌・近藤滋「ART OF ARTS, MAN AMONG MEN.」
(レビュー・山本和弘)1991年
▶『Art & Critique 15』
〈NOTES〉 森村泰昌[1990年 芸術のサバイバル](構成・原久子)1991年
小池一子 井上明彦 松井恒男 塚本豊子 飯沢耕太郎 長谷川祐子
横江文憲 山野真悟 南條史生 中井敦子 斎藤郁夫 岡田勉
藤本由紀夫 石原友明 山本和弘 尾崎信一郎 アイデアル・コピー
富田康明 近藤幸夫 篠原資明 一色與志子 南嶌宏
▶『Art & Critique 19』
〈INTERVIEW〉 森村泰昌(構成・原久子)1992年
(2016年5月3日公開)