ラウンドテーブル:21世紀のサミュエル・ベケット
金氏徹平+多木陽介+藤田康城+森山直人(司会:小崎哲哉)
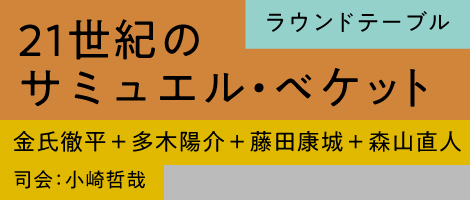
司会:小崎哲哉
写真:長澤慶太(京都造形芸術大学舞台芸術研究センター)
編集協力:竹宮華美+長澤慶太(同)
小崎 『没後30年——サミュエル・ベケット映画祭』は12月20日に始まりました。本日23日が最終日ということで、これがクロージングトークとなります。まず、この映画祭がどうして開催されるに至ったか、経緯について簡単に説明します。
京都造形芸術大学舞台芸術研究センターではさまざまな研究が行われているのですが、サミュエル・ベケット研究会は2017年に発足しました。本日のトークに参加するのは、そのメンバー全員です。当初は、ベケット研究者で、白水社から昨年より刊行されている『新訳ベケット戯曲全集』の監修者である早稲田大学演劇博物館の館長、岡室美奈子さんにも参加していただく予定でしたが、体調を崩されてしまい、残念ながら欠席となりました。
さて、ベケット研究会が発足した2017年の9月に、東京のシアターΧ(カイ)と、この大学にある京都芸術劇場春秋座に、アイルランドのマウス・オン・ファイアという劇団が来て、ベケットの作品を上演しました。その際に、同じタイミングでイベントを行おうということで、ベケットに影響を受けた現代アーティストの作品集の展示、研究会メンバーの多木陽介さんがつくったビデオの上映、シンポジウムなどを行いました。今回も展示を行っていますが、アートブックの冊数は増えたものの、全体の規模は前よりは小さいですね。前回は展示やビデオ上映のほかに、原田祐馬さんが率いるデザインオフィスUMAがつくった、ベケットのテキストを投影するインスタレーションもありました。
今年はベケットの没後30周年にあたります。ちょうど昨日の22日が命日だったわけですが、これは白水社が新訳全集を企画したひとつのきっかけだったかと思います。我々ベケット研究会もこのタイミングで何かやろうと考え、本来であれば実際に演劇作品を上演したいところですが、上演にはお金もかかるし準備も大変なので映画祭を開催することにしました。ここのところ日本ではベケット作品の上演が少なく、ことに若い世代が戯曲を観ていないことが背景にあります。

今回上映したのは全部で10作。その内6作品は『Beckett on Film』というプロジェクトによって撮り下ろされたものです。いまから18年前の2001年に、ダブリンのゲート・シアターの芸術監督、マイケル・コールガンらが企画したもので、ベケットのほとんどの戯曲、全19作品が映像化されました。最終的にはひとつのDVDボックスに収められましたが、監督にアンソニー・ミンゲラ、アトム・エゴヤン、ニール・ジョーダン、さらには現代アーティストのデミアン・ハーストら、俳優にジョン・ハートやジュリアン・ムーアらと、錚々たる面々を起用しています。
それ以外に、ベケット自身が演出に携わったものや、名優ジャン=ルイ・バローやマドレーヌ・ルノーが出演するものなど、過去にすでに撮られていた作品を選んで、台詞のない作品を除いてすべてに新訳の字幕を付けました。白水社と監修者・翻訳者の方々のご厚意によって『新訳ベケット戯曲全集』の訳文を使わせていただき、文部科学省の科学研究費補助金を用いて字幕を作成した次第です。
映画祭はそのような経緯で開催されたわけですけれども、サミュエル・ベケットその人について簡単にご説明しておきます。ベケットは1906年にアイルランドのダブリンで生まれました。亡くなったのは1989年で、人生の大半をパリで過ごしています。若いころに20世紀文学の巨人、ジェイムズ・ジョイスの助手を務め、同時に自分も作品を書くようになります。初期に「三部作」と総称される小説を書き——宇野邦一さんによる新訳が最近出版されましたが——その間に、本人が言うところでは「気晴らし」として戯曲を書いていた。それが最も有名な『ゴドーを待ちながら』という作品です。戦争の体験もあって、生と死をめぐる実存的な主題が多いといわれますが、特筆すべきは英語とフランス語の両方で書いたことでしょう。1969年にはノーベル文学賞を受賞しています。
今日は、前半は映画祭のクロージングということで、総括ではありませんが、ベケットはどのような人であり、作品にはどのような特徴があるかということを、5つのキーワードを使ってご説明しようと思います。キーワードのそれぞれを1名ずつが受け持って説明します。
後半は、ベケット受容の変遷について議論したいと思います。ベケットが亡くなった1989年は、ベルリンの壁が崩れ、東欧諸国でたくさんの革命が起こっていった、つまり冷戦構造が崩壊した年に当たります。実はその年を挟んで、言い換えればベケットの生前と没後とでは、ベケットの位置付けや受容のされ方が非常に異なっています。それは、ベケットが亡くなったからというよりも、世界の変容のほうが理由としては大きかったのではないか。これは、ここにいる5人のみならず、世界中のベケット愛好家、ベケット研究者の共通の見解でしょうが、それについて議論していこうと思います。
それでは、前半のトークを始めます。最初のキーワードは「待つ」。京都造形芸術大学舞台芸術研究センター主任研究員の森山直人さんに説明していただきます。
森山さんは研究者であり、演劇批評家であり、京都で毎年開催される『KYOTO EXPERIMENT』(京都国際舞台芸術祭)の実行委員長を務めていらっしゃいます。また、この大学の舞台芸術学科で教鞭を取っていて、教え子の中には現在活躍している方が何人もいます。よろしくお願いします。

森山直人
キーワード1:待つ
森山 最初ということもありますし、今回、こういう催しで初めてベケットに本格的に触れるという方もいらっしゃるかと思うので、差し当たって、ベーシックなことからお話しします。
まず『ゴドーを待ちながら』について。この戯曲作品は1953年の1月にパリで初演され、これが劇作家ベケットの出発点となります。なんと言ってもこの作品は、「待つ」という言葉がタイトルに付けられていますが、白水社から出版されている新訳書に収録された西村和泉さんの「草稿から読み解く『ゴドー』」によると、ベケットが最初に『ゴドーを待ちながら』を書いたときには、単に『待つ』というタイトルで書きはじめたそうです。今回の新訳以前には、定訳として安堂信也・高橋康也訳というバージョンがあって、日本での『ゴドー』の受容はそこから始まったと言っていいと思います。日本では、1960年に文学座が上演したのが本邦初演で、いいかえれば2020年は、日本でベケットが初めて上演されてちょうど60年目という節目ということになります。
1965年には劇団民藝が『ゴドー』を上演していますが、その後は、ベケットをそのまま上演するというよりは——先ほどのトークで安藤朋子さんの素晴らしい、唐十郎の作品をモチーフにしたパフォーマンスがあったばかりですが——1960年代以降のいわゆるアングラ演劇の小劇場の人たちの場合は、さまざまな形で自分なりの『ゴドー』およびベケット全体を、自分たちのやり方で消化していくという流れが主流だったと思います。そのなかで、「待つ」というキーワードは非常に大きなものでした。別役実の戯曲や、鈴木忠志、太田省吾の演出作品、津野海太郎の批評など、その影響は非常に広範なものだったと言っていいでしょう。
ところで、なぜ「待つ」というテーマが、世界演劇史的に、これほど大きなインパクトを持つことになったのか。それは、「ドラマトゥルギ―」をめぐる西洋的な、強固な歴史的文脈があったからです。すなわち、西洋演劇史の規範中の規範であったアリストテレスの『詩学』においては、劇とは、始めがあって、中があって、クライマックスがある、というモデルが称揚されました。日本的に言えば「起承転結」ですが、いずれにしても、「クライマックス」が、そしてそれに伴う観客の「カタルシス」が、劇の中心的な役割を占めてきた。
それに対して、ベケットの「待つ」という主題は、「クライマックス」という概念を、つまりは「ドラマ」の概念を根本から覆してしまう。登場人物と観客がクライマックスに至ることなく、ひたすら「待つ」だけの作品をベケットはつくった、ということです。もしもゴドーさんが現れたら、それがひとつのクライマックスになるはずだったのに、ゴドーさんはいつまで経っても現れない。そのことで、むしろ、誰かが誰かを待っているという状態を描く。その中に、現代の本質的な何かを見出そうとする。そのことが『ゴドーを待ちながら』の最大の特徴であることは間違いないでしょう。
では、いったい何を待つのか。『ゴドー』以外のベケットの作品から広く「待つ」ということを考えてみると、やはりベケットという作家にとって、さまざまな作品に登場する大きなモチーフとして「死」というものがある。すでに多くの人が指摘してきたように、「死」に向かって少しずつ時間が進んでいくということが、ベケットの作品には多く見られます。今回の映画祭で上映された『エンドゲーム』もまさにそうで、破滅に向かって進む時間は、それぞれの登場人物にとっての「死」かもしれないし、場合によっては世界そのものの「死」、「終わり」かもしれない。
同時にまた、ベケットの作品には、『わたしじゃないし』や『息』などのような、「ドラマティキュール=小さいドラマ」と呼ばれる作品群があります。たとえばその中の、『ロッカバイ』という作品を見てみると、これもまた、ひとりのおばあさんがロッキングチェアで、少しずつ「死」に近づいていく光景が、15分くらいの繰り返しの反ドラマを通じて描かれています。ちなみに、これは蛇足ですが、20年前くらいのスカパーにシアター・テレビジョンというチャンネルがあって、そこでベケットの小さい作品を3本上映していたんですけれども、そこで観た『ロッカバイ』が素晴らしかった。ビリー・ホワイトローという俳優が演じていましたが、ベケットの真髄はこういうものなんだ、と目を開かれた記憶があります。
最後にひとつ、「待つ」ということを可能にする状態についてなのですが、哲学者のジル・ドゥルーズは、『消尽したもの』という興味深いベケット論の中で、ベケットの作品には「可能性」というもの、いいかえれば、「何かを可能にすること」そのものが完全に不可能になる状況が描かれていて、その状態を「消尽」と名付けています。英語では「exhausted」ですが、もはや消耗しつくすだけ消耗してしまって、もう何もかも無理、みたいな状態ですね。それと比較すると、「待つ」ということの中には、「待つことができる」ということがあって、つまりそこにはまだ一縷の望みがあると言えるかもしれません。『ゴドー』は二幕の芝居ですが、一幕目の最後で少年が「ゴドーさんは今日は来ません」と告げに来る。そして二幕目の終わりで、また同じ少年が来て「ゴドーさんは今日は来ません」となるわけですが、かりに絶望が二度繰り返されたとしても、もしかしたらその次の日には来るかもしれない、という希望は、一応は持つことはできます。けれども、ある臨界点を超えると、もはや何も待つことができなくなる、という状態が、もしかしたらあるのかもしれない。「待つ」ことから出発したベケットは、「待つ」という主題をどんどん掘り下げていき、後期には「待つ」ということを超えた地点にまで到達してしまう。そこが、ベケット作品全体の非常に面白いところではないか。いずれにしても「待つ」ということが、劇作家ベケットの出発点であったということは、とても興味深いことだと思います。
小崎 ありがとうございました。では続けて、ふたつ目のキーワードの説明を藤田康城さんにお願いしたいと思います。
藤田さんは、高校生のころからベケットが好きで、ベケットとともに人生を歩んできたような演出家です。2001年に、詩人の倉石信乃さん、俳優の安藤朋子さんらとARICAという劇団を結成し、オリジナルの作品も発表しながら、ベケット作品そのものや、翻案したものを上演されています。私は2013年に、今年話題になった国際芸術祭のあいちトリエンナーレで舞台芸術の統括プロデューサーを務めまして、そのときにARICA版の『ハッピーデイズ』——そのときは『しあわせな日々』というタイトルでしたけれども——それを新作としてつくっていただきました。
「声」というキーワードです。では藤田さん、よろしくお願いします。
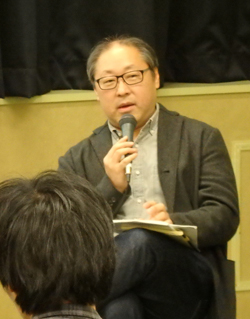
藤田康城
キーワード2:声
藤田 高校のときからベケットが好きだったとご紹介いただきましたが、私は研究者ではなく、ベケットについてずっと考え続けているわけではありません。
ベケットの話になる前に、まあいろいろと許される家庭の環境があったので、小学校の5、6年生から、新劇が中心ではありましたが、毎週のように演劇を観る機会がありました。最初は、俳優座とか文学座とかを観ていて面白かったんですけれども、あるとき、別役実の舞台を観て、なんだろうこれはと思い、これは不条理劇と言うらしいぞと聞いて。それが高校のときだったのですが、図書館に行くと『サミュエル・ベケット戯曲全集』というのが二巻出ていて、それを手に取ったんです。
僕は演劇よりもはるかに音楽のほうが好きなんです。聞くことが好きで演奏はできませんが。それで、いろいろな音楽が絶えず頭の中で流れているというようなことがあったのですが、当時、ビートルズの通称『ホワイト・アルバム』と呼ばれている真っ白いジャケットのレコードがありました。その中に「レボリューション9」というジョン・レノンとオノ・ヨーコがつくった曲があって、いろいろな声が聞こえてくる。すごく前衛的な作品なのですが、当時はそういうものに惹かれていたんですね。ほかにも現代音楽の中で、ピエール・アンリとピエール・シェフェールが1950年ごろにつくった、具体音を使ったミュジック・コンクレートという音楽にも興味を持っていました。そういうときにベケットを読んだのですが、例えば1957年にベケットがつくった『すべて倒れんとする者』というラジオドラマなどは、具体音を実際に指定している作品で、この戯曲、この作家は、音に対して非常に鋭敏な感覚があるんだろうと感じたんです。もちろん『ゴドー』や『エンドゲーム』など、すごくパワフルな、代表作と言われる作品も面白かったんですけれども。
中でも、ある意味いちばんわかりやすかった『ロッカバイ』という作品に惹かれました。先ほど森山さんも話されましたが、15分かそれくらいの作品で、揺り椅子に老婆が座っている。ずっと揺れているんですけれども、そこに声が聞こえてくる。作品は4つのセクションに分かれていて、どうも揺り椅子で動かされている女性について語っていると思えるような台詞なのですが、窓の外を見て、窓の外のほかの窓に誰かを探しているといった「外」のイメージから、結局は自分の家の中に戻ってきて、そこで死んでいく。自分の死んだ母親の様子と重ね合わせられ、最後はそこに自分も入り込んで死んでいくというようなイメージなのですが、この作品の台詞は、非常に繰り返しが多いんです。僕は英語が不得意でまともに読めないのですが、しかし僕でも読めるような非常に簡単な英語で書かれていて、その言葉が微妙に変化していくんですね。そして変化していく中で、イメージがはっきりと変わっていく。
まず「声」がある。具体的な声があって、それはつまり音なのですが、そこで「声」は「time she stopped」という、高橋康也さんの訳ではただ「もうそろそろやめていいころよ」となっていたかと思うのですが、舞台上の女性は、その言葉だけ「声」と一緒に言うんですね。それがだんだんと弱くなって、最後にはその言葉も言わなくなる。つまり声の変化と舞台上の進行の推移というものが、ぴったりと一致している。音楽も演劇も時間芸術ですが、そのふたつがここまで緊密に、繊細に、構造上ぴったりと合わさり、かつ非常に詩的なイメージが、簡単ではあるけれどポエティックな言葉の響きによってつくられている舞台というのを知らなかった。音ということ、声ということに関して、ここまで考えを持ってつくっている作家なのかとびっくりしたんですね。それ以来、僕にとってのベケットに対する興味というのは「声」と「音」です。
その例をお見せしたいと思います。『ロッカバイ』を自分で上演する機会はしばらくなかったのですが、今年の7月に、表象文化論学会の桒山智成先生に声をかけていただいて、京都大学の稲盛ホールという場所での上演を頼まれました。『ロッカバイ』を上演してほしいと頼まれたわけではないのですが、そういう機会をいただいたので、じゃあやってみようかと思って上演したんですね。その記録映像があるので、それを観ていただきながら話したいと思います。
いまお話しした通り、『ロッカバイ』は、揺り椅子が真ん中にあって、老婆がそこに座っていて、自分で動かしているわけではないのだけれど、揺り椅子が揺れているというような舞台です。けれども、それをそのままやりたくはなかった。そこで我々が上演したのは、小さい机があって、水の入ったカラフェとコップと手鏡と本といったものが置いてあって、そこに女性が突っ伏しているというものでした。そこに街のノイズ、街の音が聞こえてくるのですが、それが聞こえてくると、女性がふっと体を動かして起き上がり、水を飲んだり伸びをしたりといった行為を始め、それを繰り返す。原作では揺り椅子に揺られていて、それが止まりそうになると、「more(もう一回)」という声が聞こえてきて、それでもう一度動きはじめる。つまり、死にかけているんだけど、外の声でまた生き返って、また動くのだけれど、また死にかけてという繰り返しがあり、それがどんどん弱くなっていく。そういう舞台なのですが、我々はそうではなくて、ある種の日常的なことをただ繰り返します。
我々の舞台の特徴は、映像を使っていることです。先ほど話したとおり、原作では死んだ母親と、それに歳が近いであろう自分自身とのイメージが重ねられています。そして我々は途中から映像を入れることにしました。舞台上の女性をダイレクトにその場で撮りつつ、それが奥に投影される、つまり舞台上の行為がそのまま映っているのですが、最初は同期していますが、途中からその行為がズレていく。二番目に映すときには、行為が25秒遅れるんです。これが同じ女性だということははっきりわかるけれども、行為が遅れることによって、ある種の幽体離脱的に、そのイメージが、実在の女性からイメージの女性へと広がっていくことを意図していました。そして最後のほうになると、本人は椅子に座っているのですが、映像の女性が勝手に動きはじめる。それは、あらかじめ現場で撮っていた映像を再構成して投影しました。
ここで声を出しているのは、あらかじめ録音された声です。つまり、歩いている女性も映像の女性も声を発しているわけではない。しかし、外から声が聞こえてきて、これはベケットの原作の構造と同じなのですが、我々の場合はイメージの女性と現実の女性と声が、より離れていくような構造を採用しています。イメージの女性が母親のように、実在の女性を見下ろすようなシーンもあります。
また、ベケットの原作では最後に、衰弱したまま、もう死ぬんじゃないかというところで舞台を終えているのですが、我々の場合は、最後に死ぬ様子を見せませんでした。映像で撮られた女性が、最後のほうで後ろのほうに歩いていき、窓を開けるようにしたんです。『ロッカバイ』のテキストでは、「窓の外」というのがキーワードになっています。それで、この上演では最後に奥のスクリーンが上がっていきますが、稲盛ホールは大きな窓が後ろにあって、その窓の外が見えるんですね。つまり、上演中に繰り返される「窓の外を見る」という言葉に合わせ、最後に実際の空間にある窓が開き、外の光景が我々の視線に入るということになります。
古いベケットのイメージとしては、この舞台は、母親とある種の甘美な同化をし、いろいろと辛い人生だったけれど、それが死にかけていく、終わりかけていくという状態のまま終わっていく、ある種ロマンティックな作品でした。しかし、このときに倉石という、我々がいつも一緒にやっていて『ハッピーデイズ』の翻訳もしてくれた詩人が、このテキストにある「time she stopped」という台詞を――「そろそろやめていいころよ」でもなく、あるいは長島確さんの新訳「もうやめるころって」でもなく――「終わるときがきた」と訳してくれたんですね。
これに関して、あとでお話があるかもしれませんが、多木さんが私信で非常に示唆深い指摘をしてくださいました。「終わるときがきた」というのは、彼女の一生の終わりということではなくて、世界がうまくいっていないということではないか、と。僕も、多木さんの著書でも論じられているように、現代の機械文明がフーコーの言う生権力の、目に見えない権力構造の中で知らぬ間に抑圧されている状態のことではないかと思います。孤独死をする人もいるし、つい最近も、新幹線の中で、自分が終身刑になりたいがために人を殺した事件がありました。死刑は嫌だ、3人以上を殺すと死刑になってしまうからふたりまでにしようと思った、しかし刑務所から出たらまた同じ犯罪を犯すから終身刑にしてほしいと懇願して、実際、終身刑になったわけですよね。
つまり、自殺したくはないけれど、生きたくもない。けれど、そこには目に見えない生権力の抑圧みたいなものがあって、自分で死を選ぶことさえもできないという、非常にシビアな状況が現在あるのではないかと。そのように僕自身も感じ、そのような指摘を多木さんからも受けたのですが、「声」というもののあり方が、自分と対峙するような「声」ではなくて、いつの間にかいろいろな「声」によって、自分自身のあり方が抑圧されている。だから簡単に死ぬこともできないし、かといって何かをやることも難しいような状況が、いまベケットを再解釈しようとしたときに、結構重要なポイントとして出てくるのではないかと思います。我々がつくった舞台も、窓の外には誰もいないけれども、しかし人生は続く、そして死さえも選択できない、でもその中にある種の希望を見出していかなければいけないという状況を描いたのかなと思っています。
小崎 ありがとうございます。後半に話すべきこともだいぶ含まれていたような気がしましたが、それはベケットの全作品に通底している大きなテーマだと思います。
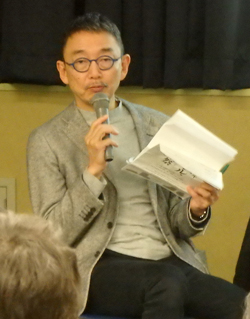
小崎哲哉
キーワード3:反復
小崎 それでは、三番目は私ですね。「反復」というキーワードです。
反復というのは、映像をご覧になれば、それだけでわかっていただけると思いますが、ベケットの大きな特徴のひとつです。いちばんわかりやすいのは、さまざまな作品において同じ状況が2回繰り返されることです。例えば『ゴドーを待ちながら』には第一幕と第二幕があり、ほとんど同じ状況で、同じような日常が繰り返される。しかし、細部はそれなりに異なっています。『ハッピーデイズ』も同様です。一幕目と二幕目で、同じ女優が山の中に埋められているわけですが、第一幕では腰までだったのが、第二幕では首まで埋まっています。
台詞が繰り返されることもあります。いま藤田さんが話してくれた『ロッカバイ』もそうですが、例えば『ゴドー』では、ゴゴが「行こうよ」と言うとディディが「だめだよ」と返し、「なんで?」と聞かれると「ゴドーを待つんだ」と答える。これが何度も繰り返されます。あるいは、『ハッピーデイズ』のウィニーが「すばらしいことだと思う」とか「昔っぽい!」と何度も言う。『エンドゲーム』ではハムが「いい感じでやれてるな」というフレーズを繰り返す。もっとすごいのは『プレイ』で、壺の中に体を入れられて拘束された3人の男女が、痴話喧嘩というか、不倫をめぐる状況を高速で喋り続けるわけですけれども、ひととおり喋り終わった後、もう一度同じことをやる。ベケットの原作には、まさに「反復(リプレイ)」とだけ書かれていますが、正確な複製でもバリエーションでもいいと指定されています。
こういった例はほかにもありますけれども、ちょっと違う例を挙げると、『クラップの最後の録音』ですね。原題は『Krapp’s Last Tape』ですから、以前は『クラップの最後のテープ』と訳されていました。ご覧になった方はおわかりでしょうが、オープンリールのテープレコーダーを使った作品です。ベケットは新しい機械、新しいテクノロジー、新しいメディアが大好きで、テープレコーダーが出たときに、新しいおもちゃみたいな感覚で「これだ!」と思ってこの戯曲を書いたんだと思います。
主人公クラップはひとり暮らしの老人男性で、69歳です。なぜわかるかというと、この老人は毎年、自分の誕生日にテープレコーダーを使って、その日に考えたことを日記代わりに録音しているんです。そして、30年前の自分の声を聞いてみようと言ってテープを再生すると、いまの自分よりもはるかに元気な若いころの声が聞こえてきて、それが、今日39歳になったと言っている。そこで年齢がわかるのですが、面白いのは、この戯曲が書かれたのは1958年で、その30年前には少なくとも民生用のテープレコーダーは存在していなかったことです。だから戯曲の設定は「未来」になっています。最初から近未来の、いわばSFとなっているわけですね。
で、ご想像が付くと思いますけれども、テープレコーダーを使って昔の自分の声を聞く。それ自体が反復であり、その声に対して「この若造め!」というようなことを録音するのですが、これも行為の反復です。さらに細かく言えば、テープレコーダーなので、若いころの声を何回か再生することもできる。そのような反復もあります。
シーンの反復では、喜劇俳優のバスター・キートンを起用した『フィルム』という映画が面白いと思います。他者の視線を避けて部屋に逃げ込んだキートンが、中にいるさまざまな目を思わせるものをしらみつぶしに排除していく。例えば外界とつながっている窓のカーテンを引き、鏡には布をかぶせる。大きな目の神像を描いた紙を破り捨て、金魚鉢や鳥かごにはカバーを掛ける。犬と猫は部屋の外に追い出すのですが、最初に猫を抱えて行ってドアから出し、次に犬を抱えていってドアを開けると、その隙に猫が入ってくる。それが何度か繰り返されるんですね。これは喜劇の演出の常套手段というか定番で、本当はあの場面は笑いどころだと思うのですが、映画祭では皆さん、ベケットということで構えてあまり笑っていなかったような気がします。ベケットは喜劇が好きで、若いころはキートンだけではなく、チャップリンやほかの喜劇映画にも耽溺していたということが伝記によって明らかになっていますが、喜劇が好きだったからこのテクニックを使ったのかもしれません。
では、なぜ反復するのか? ヘーゲルが言い、カール・マルクスが広めたと言われる「歴史は繰り返す。一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」という言葉がありますが、これと同じような世界観をベケットが持っていたということがひとつには言えるのではないかと思います。もうひとつは、「死」を想起させるために、あえて日常の中の繰り返し、反復を入れて、その都度思い起こさせるというところがあるのではないか。『ゴドー』のディディとゴゴもそうですが、生と死の間に宙吊りになった中で何かを待っている。最初に森山さんに説明していただいた「待つ」にも関係しますけれども、退屈な日常をまぎらわす、あるいは、待っているものが死であるとすれば、その死の恐怖をまぎらわすために行われる日常的でトリビアルな繰り返し。それを示しているのかもしれません。
キーワード4:ビジュアルインパクト
小崎 続いて金氏徹平さんです。金氏さんは現代アーティストで、彫刻を中心にさまざまな作品をつくっていらっしゃいます。また、いまから10年くらい前からですかね、チェルフィッチュの岡田利規さんに依頼されて舞台美術を担当され、最近ではご自身でも演劇作品をつくっています。私がARICAに『しあわせな日々』を上演してもらったときには、金氏さんにお願いして舞台美術をつくっていただきました。ベケットの原作では、舞台美術として焦土の中の小山みたいなものが指定されているのですが、それをアート用語で言うところのレディメイド、既成品の消費材や自然物を組み合わせてつくり、しかもそれが楽器にもなっているという、非常にユニークな面白い山でした。
キーワードは「ビジュアルインパクト」です。では金氏さん、よろしくお願いします。

金氏徹平
金氏 ベケットに触れている期間は僕がいちばん短くて、最初に触れたのは2013年に、ARICAと一緒に『しあわせな日々』の舞台美術をつくることになったときです。元々は、演劇そのものにそんなに興味がなく、ベケットのことは知っていて、少し読んだこともあったのですが、真剣に取り組むようになったのはその後ですね。
ベケットがなぜこんなに関心を持たれるのかというと、やっぱり、ビジュアルイメージをすごく喚起するからではないでしょうか。実際に舞台や映像に出てくるビジュアルには、ものすごくインパクトがある。そういうところで、現代美術のアーティストにもすごく影響を与えているんじゃないかなと思います。僕が『しあわせな日々』に取り組むときに、最初の問題点というか、課題としてぶつかったのが、原作の指示についてでした。ベケットにはかなり厳密な指示がいろいろとあって、舞台を上演するときには、台詞はもちろん、状況や物にも細かく指定がある。しかもそれを絶対に変えてはいけないと著作権継承者に厳しく言われるという話を聞いて、そこをどうするかということを結構考えました。とはいえ、やっぱり言葉ですべてが書かれたものであり、それをビジュアルに置き換えるときには、当然、誤訳というか誤解というものが含まれる可能性がある。だから意外と、ベケットの原作をビジュアルに置き換えることにはチャンスが含まれていて、そこにはかなりの面白さがあるんじゃないかと思います。
同じようなことは、言語についても言えるような気がします。ベケット自身も2ヶ国語で書いていたということがあって、言葉のズレというか、特に外国語になるときのズレはすごく意識していたんじゃないでしょうか。ARICAが取り組んでいることもそうですが、英語やフランス語以外を話す国で上演されるときも、ビジュアルに置き換えられることと同じような、いろいろなチャンスが含まれていて、誤訳みたいなことはすごく、重要なポイントとしてあるのではないかと思います。
ベケットがビジュアルとして喚起しているものや、実際にテキストの中に書かれているビジュアルの面白さがどういうものかというと、ひとつは身体のイメージですね。僕自身、コラージュという手法で作品をつくることが多いのですが、ベケットの場合も、身体を切り刻むというか、身体の部分だけを取り出したり、それをどこかに接続して不自由な状態をつくったりする。そういうイメージが特徴としてかなりあって、僕自身も面白く感じて、影響を受けているところです。
例えば『しあわせな日々』なら、先ほどから話が出てきていますけれども、何もない荒涼とした丘の上に身体が嵌っている。ある意味でそれは、身体が切断されて、別のものと接続されている状況だとも言えます。そういう状況を踏まえて、僕がやった舞台美術では、さらに多くの穴が丘の中に含まれていて、さらにいろいろなものが接続されていく可能性を感じさせるようなものをつくりました。
『わたしじゃないし』で口だけを切り出しているのもそうだし、『クワッド』でいろいろな制限というか、規則的な動きを繰り返すことや、全身を覆い隠す衣装とかもそうですね。そういうことによって、人間の人間性みたいなものを切り離してしまう。それもひとつの切断であり、新たなイメージを接続するチャンスを提示しているように思います。ビジュアルを伴ったものを考えるときに気になるポイントですね。
もうひとつは、現実空間とか現実の風景との関係性みたいなもので、濃密な、個人的で閉ざされた空間と同時に、膨大な途方もなく広い空間が対比的に出てくることが多い。しかも、すごく広い空間と小さい空間が接続されている状態というか、そういう状態が想起されるものが多いような気がしています。それがさらに、時代を超えて状況を超えて、いろいろな人が自分がいる空間とのつながりを感じてしまうチャンスがある。そこもひとつ特徴で、日常的に見た状況や見たものから、ベケット的な状況やベケット的なものを思ってしまうことが多々あると思うんです。あとでソンタグの話も出てくると思いますけれども、スーザン・ソンタグの上演は、現実空間の中で行われたんですよね。
小崎 戦時下のサラエヴォで上演された『ゴドーを待ちながら』ですね。
金氏 それも現実空間とのつながりなのかとも思いますし、昨日の田村友一郎さんとのトークでも話しましたけれども、映画版の『ゴドー』や『しあわせな日々』を見ると、すごくSF的な感じがします。広大な場所と小さな人間の営みとの対比というのもありますし、どこでもない場所を描いているみたいにも感じたんですね。あの感じっていうのは、昨日も話しましたけど、ランドアートのアーティストを想起させるものがすごくあって、両方とも、すごく大きなものと、すごく個人的な人間の営みみたいなものの接点が見えるものなのかなと思います。
小崎 ありがとうございました。あとで話し合うためのさまざまな問題が出たように思います。

多木陽介
キーワード5:風景の消滅
小崎 だいぶ面白い流れになったような気がしますけれども、最後は多木陽介さんです。多木さんはローマ在住の演出家であり、翻訳家であり、社会的なものをデザインするという意味ではデザイナーとも呼べるのではないかと思います。演劇に関しては、とりわけベケット作品の演出を多くされていて、特筆すべきこととしては刑務所演劇に関心を持たれています。日本ではほとんど聞いたことがないでしょうが、ベケット作品は、欧米では刑務所の中で囚人が上演することが多々あるということです。多木さんの著書『(不)可視の監獄―サミュエル・ベケットの芸術と歴史』の中にも刑務所演劇についての記述がありますので、ご関心のある方はぜひ読んでいただきたいと思います。
では、多木さんにお話しいただきます。金氏さんの話に「風景」という言葉が出てきましたが、5つ目のキーワードは「風景の消滅」です。
多木 はい、ちょうど金氏さんに風景についてのお話をしていただきましたが、実は『ゴドーを待ちながら』の木がたった1本だけ生えている風景と、これから僕が話をする風景が消えてしまう時代の話とは、非常につながっています。写真を見ながら話します。
普通、舞台には人物がいて、人物の後ろには、屋外にしろ屋内にしろ、風景がありますよね。ところが1962年以降のベケットの舞台からは、風景が消えて真っ暗になってしまうんです。いま金氏さんがおっしゃっていたように、『わたしじゃないし』では口だけがぽかっと真っ暗の中に浮かんでいる。『あのとき』という作品では頭だけ、『プレイ』では3人の俳優が壺の中に突っ込まれた状態になっているんですけれども、ベケットの指示に従ってつくると、顔だけが照明に照らされるという状態になります。今回上映した『わたしじゃないし』と『プレイ』では、両方とも演出家たちは周囲を真っ暗にはしないという形を取っていましたけれども、ベケットの本来のイメージとしてはこういうものだったんですね。

『わたしじゃないし』

『あのとき』

『プレイ』
こういう黒い、真っ暗に風景が消えちゃった世界について、これまではずっと死の世界だとか、あるいは無意識の世界だと言われてきたわけです。それと同時に『プレイ』や『わたしじゃないし』の声は無意識の声だという解釈もされてきました。それはそれで間違った解釈ではないし、僕自身もずいぶん前にこれらの作品を演出したときにはそういうふうに解釈しながらやっていました。でも、今度、本を書きながらいろいろなことを考えている内に、もうひとつ別の視点が見えてきたんです。
例えば『ゴドー』の風景というのは、いま金氏さんが、どこでもない風景、あるいはSF的な風景に見えるとおっしゃいましたが、『ゴドー』が上演されてからしばらく、20世紀の間、我々はそういう意識を持ってこの作品を観てきたわけです。どこでやっているのかわからない、と。ところが、ベケットはあれを書きながら、第二次大戦が終わったときの膨大な瓦礫の山を頭の中に描いていたんです。ベケットは、戦争が終わってすぐにサン=ローという場所に行って、これはノルマンディーの小さな街で、2400軒ある内の2000軒くらいがボロボロに爆撃されて壊れちゃった、そういう街なのですが、そこに赴任してアイルランドの赤十字のためにボランティアしていたわけです。そういう生活、経験のあった人が、その3、4年後に書いたのが『ゴドーを待ちながら』だった。『ゴドーを待ちながら』のいちばん最初のト書きは、「田舎道。木が一本。夕方」と、そのたった3行なんですけれども、それだけを読むといろいろなことが考えられます。たいていはあまりにもシンプルなので、形而上学的な風景かと思われてきたわけですが、実はベケットの心の奥にはサン=ローの瓦礫の風景があったんですね。
戦争が終わったときに、彼の作風はガラッと変わっていきます。20世紀の前半に若い文学青年として非常に前衛的なものを書いていたときには、言語を破壊していこうというダダ的なところがあった。けれども戦争が終わってからは、本当に人間を見つめて、人間を書くようになります。『ゴドー』のあの風景は、戦争のものすごいエネルギーによってすべてが吹き飛ばされたあとの風景なんです。自然にある田舎道ではなくて、本来だったらちゃんとした文明があった場所に、何もなくなるくらいのすごいエネルギーが通って、すべてがなぎ倒されてしまった。そういう場所だと思ったほうがよいと思います。その意味で僕はあの場所を「荒地」と呼んでいるんですが、ベケットの芝居の風景には、必ずそういうエネルギーが流れている。彼自身、最初はそこまで意識していなかったかもしれないけれども、このエネルギーがものすごい加速をしていったときに、人間は風景自体を見失うんです。
戦前にハイデガーが、「技術の世界がものすごく進歩していったときに、人間はついていけなくなる。でも、そのことに人間は気がついてもいない」というようなことを言っていましたけれども、まったく同じことをベケットはここで考えていて、この暗闇は世界を見失った人間が見ているものではないかと僕は思います。ベケットの作品はいろいろなレイヤーがあるので、もちろんそこに死が重なってきたり無意識が重なってきたりすることもあるのでしょうが、いちばん奥には、強大な技術がものすごい速度で人間の周りを走り出したときに我々が世界(風景)を見失ってしまうという状況がある。それが、ベケットにおける風景の消滅の言わんとするところではないかと思います。
小崎 ありがとうございました。なぜこのビジュアルなのか、ということを解き明かすための説得力ある考え方のひとつだと思います。
刑務所で『ゴドーを待ちながら』
小崎 ベケットのキーワードは、もちろんほかにもいっぱい挙げられるでしょう。それらも場合によっては議論の中に折り込みながら、いまの5つのキーワードと即いたり離れたりしながら、フリートークのような形で進めたいと思います。
最初の「待つ」から口火を切らせていただきます。私は映画が大好きなのですが、森山さんのお話を聞いて、映画作品を2本思い出しました。2本とも、ある意味で非常事態を背景にした映画で、それが実は『ゴドーを待ちながら』にすごく影響されているんじゃないかと。
ひとつは、2001年に公開された『キング・イズ・アライヴ』という、デンマークのクリスチャン・レヴリングという人が撮った作品です。レヴリングは、ラース・フォン・トリアーという有名な監督がいますが、彼が結成した「ドグマ95」という、スタジオでのセット撮影はしないとか、照明や効果音は使わないとか、厳格なルールのもとに映画をつくっている映画作家集団の一員です。簡単にあらすじを説明すると、バスツアーをしていた11人の観光客が、エンジントラブルか何かで、アフリカ・ナミビアの砂漠の中にあるゴーストタウンに取り残されてしまう。メールや電話はつながらないという設定で、最初は運転手だったかな、助けを求めに隣の街に行くんですけれども、その人がなかなか帰ってこない。つまり「助けを待つ」というシチュエーションなんですね。なぜこの映画が『キング・イズ・アライヴ』というタイトルなのかと言うと、やや無理やりな設定だという気がしなくもないのですが、その11人の中にひとり、演出家がいて、この男が呼びかけて、「待っている間、退屈だから何かしよう。実は俺はリア王の脚本を持っているんだ」と言って、素人みんなで芝居の練習をするんです。その中で面白かったエピソードが、ゴーストタウンでほぼ食物がないのですけれども、唯一ある食物が、雑貨屋に残っていた大量の缶詰で、中身がニンジン。これは明らかに『ゴドーを待ちながら』の引用だと思います。
もう1本は、我が敬愛する北野武監督が1993年に発表した『ソナチネ』という作品。寺島進や大杉漣が出演していましたが、北野監督ですから典型的なヤクザ・ストーリーです。大きな暴力団の傘下にある小さな組の組長であるビートたけしが、上部組織に抗争の手助けをしろと命じられて手下と一緒に沖縄に行く。ところが予想以上に抗争は深刻で、たけしたちは田舎の浜辺にある隠れ家に非難する。その内に抗争の背後事情がわかって最後にはドンパチになるんですが、それまでは沖縄の海岸でずっと待っているわけです。待っているシーンが延々とあって、海岸で花火や、紙相撲や、くだらない遊びをいっぱいやるんですけど、典型的な「待つ」状態でした。北野監督はものすごくインテリですし、お笑いの人たちは実は昔から『ゴドー』に関心が深いですよね。前に星セント・ルイスもやっていましたし、ラーメンズが『後藤を待ちながら』というパロディを上演したこともある。ディディとゴゴのやり取りは典型的な漫才と言ってよいようなものでしょうが、『ソナチネ』もあれに影響されていることは、おそらく間違いないのではないかと思います。
多木 「待つ」ということで言うと、ベケットをいちばん最初に、何の勉強もせず、何の苦労もなくあっという間に理解をしたのは囚人なんですね。ドイツの刑務所の囚人が、世界初演の1953年に『ゴドー』を上演しているんです。その年の1月に『ゴドー』がパリで上演されて、観客の半分がすごく喜び、半分がこんなの演劇じゃないと言って、その間で喧嘩が起こったりして、ものすごい騒ぎになりました。しかし、いずれにしても誰もよくわからなかったんですよ。喜んで観に行った人たちも皆、なんか難しい哲学が舞台化されているような感じで、どこか距離を感じて、うまく理解することができない霧の中のお話みたいなものと思っていた。61年に、マーティン・エスリンが『The Theatre of the Absurd』(不条理演劇)という本を書きますけれども、要するに彼も説明ができないから「不条理」という言葉を発明したわけです。ところが、53年の11月に、ドイツのリュットリングハウゼンという街の刑務所のある囚人が、なぜかフランス語の台本を手に入れて、翻訳して仲間の囚人たちを役者として使って『ゴドー』を演出し、大成功して15回くらい上演しているんです。
なぜそんなことになるかと言うと、実は囚人の生活というのは、毎日毎日「待つ」ことによって出来ているんです。食事の時間を待つ、面会の時間を待つ、あるいは出所の時間を待つ、場合によっては死刑の時間を待つ。「待つ」という動詞は、なんとなく能動的に自分で待っているような気がしますけれども、自分で待つということはありえなくて、誰かに待たされているわけですよね。そして、待っているときというのは、自分で主体的に何かを決めることができない時間です。完全に受動的で、何も自由がない。刑務所にいる時間というのは、そんな時間の典型であると言っていいかと思います。だから囚人はよくわかったんです。
1957年には、アメリカのサン・クエンティンという有名な刑務所で、外から来たプロが上演した『ゴドー』を観た囚人たちがやはり感動して、翌日にはすぐ刑務所長に、演劇ラボを開催させてくれと言った囚人がいたんですね。リック・クルーシーという人ですが、彼はその後、恩赦を受けて、死ぬまで外で芝居を続けます。ベケット自身に演出してもらったこともあるんです。では、この人がなんで『ゴドー』に感動したかというと、やはりこの芝居が「待つ」ことを主題にしてくれている、俺たちのことを書いてくれているんだと言っています。彼らにとってみれば不条理劇でもなんでもなくて、ものすごくリアルに自分たちのことを書いてくれている人がいた、そのことに感動したんですね。クルーシーは「俺は3年ゴドーを待っていたけど、そのことに気が付かなかった」と言っているんですが、刑務所の本質とは、鉄格子でもコンクリートの壁でもなくて、待たせるということなんです。待たせる中に人を放り込むのが実は刑務所の本質だということに、自分たちは気が付かないままずっとその中に置かれていたと。自分から何かしなくちゃいけないと。そう思って芝居を始めるわけです。
非常事態の演劇
森山 いまのお話と、さっき多木さんがお話しになった「風景の消滅」という話が、やはり重なるのではないかと思いました。「刑務所演劇」の話は、私も多木さんの本に詳細に書かれているのでずいぶん勉強させていただきましたが、面白いと思うんですよ。監獄とか囚人、あるいは待たされているという状態について言うと、現代では、それが割と誰にとっても身近に感じられるようになってきているのではないか。私はさきほど、「待つこと」と、「もはや待つこともできなくなること」という分け方をしてみたのですが、待つこともできなくなっている状態と、にもかかわらず「待つ」ということが、「風景の消滅」というところとつながっているように思いました。それは、例えば冷戦以後の状況全般もそうだし、あと数日で2020年代に一応入るわけですが、このまったくわくわくしない感じとか(笑)。
小崎 待ちたくもない(笑)。
森山 多木さんのお話を聞きながら、ある意味で、囚人的なある種の絶望のようなものを、皮膚感覚で私たちは体験しつつあるのではないかという気がしました。
多木 さっき小崎さんが非常事態というお話をされていましたが、非常事態に置かれると『ゴドー』という芝居は何の苦労もなくわかるようになります。刑務所はたぶんそのひとつだし、先ほどお話がちょっと出てきたけれども、スーザン・ソンタグが93年にサラエヴォで、まだ戦争が行われているときに乗り込んで行って『ゴドー』を向こうの役者さんたちとやるわけですね。そのとき、サラエヴォの人たちは、40年前に書かれた芝居が自分たちのために書かれた芝居だと、わざわざいまのために書いてもらった芝居のようだと、みんなが受け取って上演したわけです。というのは、彼らも延々と戦争が終わるのを待っている。ある役者さんが言っていたんですが、ずっと待っていると何を待っているのかわからなくなってくる。それはディディとゴゴの精神状態に近いと思うんですよ。
『ゴドー』には「なんにも起こらない、誰も来ない、誰も出て行かない、ひどいもんだ」という台詞があるのですが、サラエヴォのような歴史の状況の中でこの台詞を聞くと、これがものすごくリアルに聞こえるわけです。だからサラエヴォの人たちは、まさに小崎さんが言った非常事態に置かれていて、刑務所にいる人たちとまったく同じように、何の苦労もせずに理解することができたんでしょうね。3・11のときに誰かが福島に行って『ゴドー』を上演していればすごいインパクトがあっただろうし、いまのヨーロッパであれば、難民がものすごい数で来るわけですが、例えばシチリア島のさらに南にランペドゥーザという島があって、アフリカからのボートピープルの漂着先になっていますが、そこに漂着した難民たちの前で『ゴドー』を上演したら本当にリアルでしょうね。
小崎 サラエヴォについて少しだけ補足すると、戦争と行ってもいわゆる内戦ですね。それで、サラエヴォの市民が当時、どのような生活をしていたかというと、まず、補給がすべて絶たれているわけです。だから、食物も水もない。そして、サラエヴォは京都と同じ盆地なので、昼間は特にセルビア軍がその盆地のいろいろなところにいて、京都で言うと吉田山くらいの山の中腹くらいから、外を歩く奴が見えたら全部撃つというような、そういう状況です。だから昼間は相当な覚悟をしないと外に出られない。でも、水は汲みに行かないといけない、食糧を調達しなければいけない。当然、電気だって止まっている。だから稽古するときには、蝋燭の火でやって、みんなやせ衰えていて。それでも、どうしてもそういうことをやりたいという人たちがいるわけで、ソンタグがそれに応えたのですが、結局は一幕しかやらなかったんですよね。
多木 そうですね。ちょっと変わった演出で、そういう状況ですから、俳優さんもみんな仕事がないわけです。なので、なるべくたくさん雇ってあげようということで、本当はディディとゴゴはふたりなのですが、3ペア出して、それに加えてポッツォとラッキーと少年だから、全部で9人も出るという結構複雑な芝居に仕立てて、その代わりに一幕で上演したんですね。
小崎 別の例を挙げると、ポール・チャンという香港出身の、チャイニーズ・アメリカンの現代アーティストがいます。この人が、2005年に「カトリーナ」という超弩級のハリケーンがアメリカのニューオーリンズを襲った2年後に、現地で『ゴドー』を上演しました。人も大勢死にましたけれども、何よりも、金持ちは逃げられたけれども、貧しい人々は逃げられず、家を失い、どこに行くこともできず、その街が再建されるまで何年も待たされた。そのときに、当時ニューヨークにいたポール・チャンがニューヨークのハーレムを拠点とする劇団に呼びかけて実現したんですね。
多木 ハリケーンも多大な被害をもたらしましたけれども、当時のブッシュ政権が公共の資金を全部、自分の友達の企業に回しちゃったんです。ナオミ・クラインが『ショック・ドクトリン』という本の中で克明に説明していますけれども、そのおかげで、本来であればその人たちが復興しなくてはいけなかったんだけれども、お金だけもらってやらなかった。何ヶ月経っても死体がまだポコポコ浮かんでいるという状況が放置され、しかも市民たち自身は手を付けられない。それで途方もない時間が経っても、復興に何も手がつかない中に人々が残されるという状況があって、ポール・チャンが現地へ行ったときに瞬時に、ここに『ゴドー』を持って来なくてはいけないと思ったんです。彼自身は演出家ではないので、ハーレムを拠点とする黒人の劇団に声をかけて。ちょうどその劇団が、カトリーナのあとの廃墟の中で芝居をやっているという設定で、『ゴドー』をニューヨークで上演していたんですよ。それを持っていったわけです。

声と反復の関係
小崎 藤田さんに伺わせてください。藤田さんは「声」、私は「反復」というキーワードで話をしましたけれども、声と反復というのはかなり結びついているのではないかと思います。最初のお話でも反復に触れてくださいましたが、もう一度、二者を接続するような話をお願いしてもよいでしょうか。
藤田 先ほど少しお話をしましたけれども、僕は高校のときに『ロッカバイ』という舞台に関心を持ちました。同時に、ミニマルミュージックといわれる、スティーブ・ライヒだとか、フィリップ・グラスだとか——まあグラスは実際、ベケットの作品を上演していて、非常に密接な関係があったわけですが——そういう音楽も聞いていたということがあります。彼らの音楽は、同じフレーズが繰り返されながら少しずつ変化していくというものですけれども、『ロッカバイ』は4つのセクションに分かれていて、それぞれのセクションがほぼ同じ長さで少しずつ伸びていく。同じ言葉を使いながらそれが少しずつ変化していって、音の変化だけではなくてイメージも少しずつ変わっていく。それが暗闇というか、死に向かって少しずつ進んでいくというような構造があります。言葉を司るのは声ですが、声が同じ言葉をリフレインするのにすごく音楽的な処理がされているんですね。日本語で韻を踏みながら上演するのは非常に難しいですけれども、それを徹底してやっていて。小さい作品ですけれども、それがすごく面白かったですね。
それだけではなくて『ハッピーデイズ』にも、意識的に行為と声が交互に出るようなト書きが書かれているし、言葉・声と行為が厳密な関係を取るように書かれているものがほとんどと言ってもよい。とりわけ中期、後期の作品はそういうことがすごく意識されています。初期の『ゴドー』でさえ同じセリフが何回も繰り返されることで、進んだ時間がそこに戻ってくるということがある。反復されて、進んだかと思うとまた引き戻されるというような繰り返し。それが言葉、声によって形づくられていることは非常に面白いし、それはベケットの終生変わらぬ特徴であると思います。
小崎 ありがとうございます。金氏さんは先ほど、ご自分の舞台美術とベケットのモチーフとの共通点として、切断と接続のようなものがあるとおっしゃっていましたけれども、「反復」という要素も金氏さんの作品にはありますよね。
金氏 そうですね。いろいろなルールに従って反復していくということは、僕が作品をつくる上で考えていることのひとつなのですが、反復していくことによって、物のイメージが——言葉もそうかもしれませんが——意味を殺してしまうというか、抽象的に見えたり響いたりしてしまうということがあるのかなと思います。同じような意味で、ベケットの作品、『ゴドー』とかは戦争のことが背景にあって、戦争の後の何もない風景がベースになっているわけですが、同じような出来事が時代を超えてずっと続いていく。別に戦争が起こっているわけでも、災害があるわけでもないけれども、漠然と不安があって、物はいっぱいあるけど退屈な日常。現代のアーティストはそういうところに共感しているのかもしれません。ベケットの小説も今年、三部作が新訳で出て、そのうちのひとつに感想を書くという仕事をもらいました。それでがんばって読んだんですけど、小説もすごく変わっていますね。
小崎 『モロイ』『マロウン死す』『名づけられないもの』ですね。
金氏 映像で観た『エンドゲーム』もすごく似ていると思うんですけど、密室の中に物がいくつかあって、繰り返しそれとの関係を築いていく。あるいは、妄想をすることで、その場所ではないところやその時間ではないところにつながっていくようなことがありました。どういう流れで出てきたかは忘れちゃったんですけど、『マロウン死す』に「風のない夜は私にとってまた別の嵐」という一節があって、それがすごくベケットの見方を言い表しているなと思って。起こったことが、抽象化したり捉え方を変えたりすることによって、嵐とか非常事態とか、まったく別のものにも適応されていく。そういうことが、反復ということを使って実現されているのではないかと思います。
孤独に死んでいく「ごみ屋敷の女」
藤田 さっき、「非常事態の『ゴドー』」という話がありました。サラエヴォでやるにしろ、あるいは災害地でやるにしろ、それはそれでリアリティがあると思います。けれども一方、我々はいまの日本で、戦争で人が死んでいるわけではないという日常の中で生きているわけです。『ハッピーデイズ』の話を小崎さんからいただいたときに、その前から『ハッピーデイズ』に対する興味はずっとあったので「やりましょう」となった。小崎さんからは「金氏さんとやりませんか」とも言われて、金氏さんの横浜美術館の個展も観ていたので「じゃあ、ぜひ」という話にもなりました。
ただ、原作では戦争の後の焦土というか、焼け野原か砂漠のようなところにこんもりと丘があって、そこに埋まっているということになっています。そういうもののリアリティは日本にはない、あれはあのままやれないなと思ったんですね。そのときには「ごみ屋敷の女」というイメージを持っていました。消費社会の中に女がいて、買ったり拾ってきたりした物が、家の中にどんどん貯まっていく。その中で、女が孤独に死んでいくというイメージがあった。それを金氏さんに投げて、ああいう舞台になったんです。
僕が驚いたのは、それが単なるごみ屋敷ではなくて、ある種の神経系のように全部がつながっていたことです。金氏さんは「穴だ、あるけどない」という話をしていて、真ん中の頂点に女性がいるんだけど、全部の物がつながっていて、女性が衰弱してくると、あるシーンで物が崩れたりするんですね。それも彼と話しながらつくったのですが、老いた皮膚が剥がれていくようなイメージです。
そこで多木さんに伺いたいのですが、戦争を目の前にしているわけではない日本やヨーロッパの日常の中で、孤独に死んでいく人たちというイメージが僕の中にはあったのですけれども、そういうことについて多木さんも文章を書かれていると聞きました。そういう点からのベケットのリアリティや現代性について、もう少し聞かせていただければと思います。
多木 この秋に、孤独死についてイタリアのある文化的なサイトに寄稿したんです。それを書いているときに、先ほどの藤田さんの話にも出てきた『ロッカバイ』のことを思い出したんですね。7月にARICAがやった台本を送っていただいていたので、その倉石さんの訳を読み返してみて、初めてこの戯曲がわかった気がしたんです。僕も大昔に一度、割とオーソドックスに上演したことがあって、わかんねえなと思いながらやっていたくらいなので大したことはないのですが、これは、我々が生きている時代の技術文明が、すごい速度で我々に消費をさせて物をつくらせている資本主義社会が、この女性に対して「もういいよ。人間やめたら? 死んだら?」と言っている呼びかけなのではないかと思えたんですね。
まさにそういう声が、たったひとりでゴミ屋敷の中で死んでゆく孤独死の人たちの無意識の中に届いていると思うんですよ。孤独死をしていく人を分析していくと、どう見ても資本主義社会の負の産物なんですね。ほかの国でも始まりつつあるけれども、日本はやはりその圧力が強いから、引きこもりは出るし、年に3万人以上の孤独死がある。それを生み出す土壌として、社会的孤独に陥る可能性のある人たちが一千万人近くいるそうです。それはどう考えても、資本主義の社会が人間のつながりではなく、経済的な交換だけで社会をつくろうとしてきたことに原因があると思うんです。
いま我々が生きている社会は、藤田さんが暗示されていたように、戦争はなくても、あるいは監獄の中にいなくても、フーコーの言う生権力によって完全に、いい塩梅にデザインされている。それは、我々のためにではなく経済のためにデザインされているのであって、それ自体が一種、僕らにはよく見えない監獄のようなものなんです。ベケットが敵として戦ってきた相手は、むしろそれだったと思います。だから本人は別に囚人たちのために『ゴドー』を書いたわけではなくて、ただ囚人たちがあまりにも反応したので、自分の仕事の中に監獄という比喩があるということに、たぶん後で気がついたんだと思います。それに気がついた後で、『エンドゲーム』のようなまるで監獄みたいな芝居を書くのだけれども、社会自体が本当に監獄のようになってくる、当たり前に生きている我々の社会が見えない監獄になってきている、ベケットはそういう見えない檻をいちばん意識していた芸術家ではないでしょうか。
森山 そういうこととつながってくるのは、やはりベケットに、強烈な身体感覚があったからでしょう。囚人が『ゴドー』をわかるというのも、ベケットの身体感覚と囚人たちが持っている身体感覚が強烈につながったからだと思うんです。ベケットにはビジュアルイメージというものが非常に強くあって、金氏さんや藤田さんがおっしゃったように、それが「神経」のようなものとしてつながっているということが、非常に重要な気がします。それがベケットの多面性を構成していて、21世紀においてもなお通用する理由ではないかとも感じます。一方で大きい状況に対する身体感覚があって、同時に小さな身体感覚もたくさんある。『ゴドー』なら、たとえばウラジミールが前立腺肥大に悩まされていて、笑うとズキズキ痛むとか、『ハッピーデイズ』であれば、腰や首まで巨大な砂漠に埋まっているという感覚とか。そういう身体感覚は、「この身体」に作用しつつある身近な身体感覚だと思うのですが、それらは「小さい」けれど、その人にとっての非常事態であることに変わりはない。それが、もっと大きな何かの状況とつながって感じられる、というのが、ベケットの身体感覚として面白いところだし、見逃すことができないことではないでしょうか。
多木 そこで面白いのは、監禁されている身体感覚があるはずなのに、絶対に気がついていないように書くんですよね。だから『ハッピーデイズ』のウィニーは、砂漠みたいなところに半身生き埋めになりながら、特に一幕では楽しくてしょうがないという顔で出てくる。『エンドゲーム』も、笑える場面をずっとやっている。ピーター・ブルックは「ベケットは監獄にいるのにそのことが見えていない人物ばかりを書いている」というふうに言っていました。
バリエーションをつくる
小崎 僕は、先ほど多木さんがおっしゃった解釈を否定はしないのですが、もう少し保守的です。ベケットが描いた檻、監獄とは、「生権力によってデザインされた社会」以前に、誕生から死に至るまでの宙吊りにされた人間の生そのものではないか。つまり、初期に主流だった実存主義的な解釈ですが、ベケットを理解するためには、まずはその根本を押さえるべきではないか。昨今のベケット解釈には、ときにその根本を忘れて、枝葉にばかり目を向ける嫌いがあるように感じることがあります。
とはいえ、このふたつは相反するものではありません。「生」はそれが続く限りにおいて「生権力」に介入されざるを得ないのかもしれないし、だとすれば、ベケットの懐の深さというか、両方の解釈がどちらか一方を排することなく可能だというふうにも思います。
それに関連してひとつだけ言っておきたいのは、『カタストロフィー』という作品についてです。「ヴァーツラフ・ハヴェルのために」という副題が付けられていますが、ハヴェルは言うまでもなくチェコスロヴァキアの民主化運動に携わった詩人で、反体制派として何度も投獄されています。彼が何度目かに逮捕され、獄中にいたときに、ベケットはハヴェルを支援すべくこの作品を書いた。執筆の7年後の1989年に、ベケットは死の床にあったのですが、冷戦構造が崩壊してハヴェルがチェコスロヴァキアの大統領に就任するという報せを聞いて微笑んだと言われています。
ベケットは見るからに、そして実際に怖い人だったという話もあるけれども、その一方、困っている友人があると助力を惜しまなかった。あるいは、原作の改変をほとんど認めず、だから上演許可を取るのは難しかったけれども、多木さんが話してくれたように、囚人たちが芝居をやりたいと言うとすぐに許可を与えたと言われていますよね。実存主義的な人というと完全に人生を諦めちゃって虚無的な変人というふうに捉えられがちですが、ベケットは実は心やさしい人だったのだと思います。生きている以上は、ウィニーのように、笑いながら楽しんで、そして困っている友人がいたらできる限り手を差し伸べる。そういう姿勢の人であり、それが、ハヴェルのために戯曲を書き、死の床で大統領になったと聞いて微笑んだという挿話に表れているような気がします。
森山 ベケットのその厳しさ、厳格さというのも、少し神話化されすぎている感じもしなくもないですね。実際いま小崎さんがおっしゃったように、ベケットが生きていた時代にはかなり融通を利かせた部分もあり、伝記を読むと、非常に厳格になってきたのは、著作権周りのトラブルが実際に頻発していたからのようにも感じられます。かなり強く言わないと、自分の言う通りにならないという経験を何度もしていて、慎重になったのはその辺りから来ているのかもしれません。
今回のラウンドテーブルは「21世紀のサミュエル・ベケット」というテーマです。それは「21世紀のベケット」でもあるし「21世紀とベケット」かもしれないのですが、その観点から言うと、藤田さんがやってこられているベケットは、良い意味での「ベケット変奏」のような感じがしています。最初の主題があって、たとえばバッハの「ゴルトベルク変奏曲」もそうですが、いろいろな形で変奏していく。その変奏の自由が、ベケットの著作権継承者である財団とどのようにぶつかるかはともかくとして、「変奏」はもっと提唱され、そこに自由を見出すべきではないかと思います。
藤田 ベケットはずっと根源的なことをやり続けているので、演劇の構造そのものを変えたと思います。ビジュアルにしても、金氏さんがおっしゃるように、砂山に女が埋まっているというのは本当にランドアート的な風景なわけですよね。ベケットがオーソドックスにつくった装置やイメージも、それ自体がビジュアル的にインパクトがある。だから小崎さんがおっしゃるように、いろいろなコンテンポラリーアーティストがベケットの影響下にあって、これをいろいろと変容させている。
ビジュアル的にも、あるいは言語的にも、ベケット自身がそういうバリエーションを生むことにこだわり続けていて、ある種のバリエーション、暗闇のバリエーションをつくっていました。多木さんのおっしゃったように、単に戦争の焦土や戦争論的なものだけではなくて情報社会でテクノロジーが逆に見えなくしてしまっている人間の本質みたいなもの、それを見失っている上での暗闇ということを含めて、根源的なものに非常にこだわり続けてきた作家だと思います。ベケット自身が、バリエーションをつくらないと死んでしまうと思っているんですよ。
いまだに古典的なやり方で、いかにもベケット的に作品をやっているところもあって、僕もずっと見続けているけど、そういうものはたいていつまらない。だから自分でやろうとしたんですが、ベケットを指示通りに上演するつもりはあまりなかったんです。指示通りにやって素晴らしいものが出来たとしても、それはベケットの手の内でやっていることであって、古典的なものでしかなく、アクチュアリティはないんじゃないか。それよりも、アーティストたちが構造自体、あるいは言葉、あるいはビジュアルを自分なりに拡大していかないと、ベケットは死んでしまう。ベケットの名前を出さなくても、ヨーロッパのコンテンポラリーアーティストやパフォーミングアーツの作家たちは、それをやっていると思うんですよ。僕はベケットに対するある種の敬意があるので、彼のテキストを使ってもいますけれども、それとは別にARICAでやっていることも、ある意味ではベケットが根源的にやっていることのバリエーションというか、そこから発した、拡大した創作のつもりではいます。
まだ見えていないルール
小崎 森山さんと藤田さんから、ほとんど結論めいたお話をいただきました。時間もそろそろなので、森山さん追加が何かあれば。そして金氏さん、多木さんにも、とりあえずのということになりますが、このクロージングトークのクロージングコメントをひとことずつ伺えればと思います。
森山 さっき「どこでもない場所」という話がありましたけれども、それは「nowhere」というよりは「anywhere」という感じがします。つまり、「どこでもありうる場所」をベケットはつくっていた。ベケットは「引き算の美学」とざっくり言われますけれども、じゃあなぜあんなにまで苦労して、ほとんど死ぬ思いで引き算をし続けていたのか、ということを考えざるをえない。やっぱり、「どこでもありうる場所」をつくるというのは、大変なことだったんじゃないかと思うんですよ。「この場所でしか通用しないこと」(理想的にはそのことが結果として普遍性を照射する、ということですが)をつくるというのは、自然主義リアリズムが開拓した方法論だと思いますが、「どこでもありうる場所」、「誰にでもありうること」をつくるのはすごく難しい。そのひとつのきっかけに、先ほど多木さんがおっしゃったような「風景の消滅」や、あるいは絶望みたいなものがあったのかなと思います。
それから、同時にまた、ベケットの作品は、ある意味で軽薄に引用しても全然かまわないんじゃないかと思うんです。現代アーティストがそれを引用したり、あるいは藤田さんがおっしゃったようなバリエーションをやったりというのは全然かまわないと思う。けれども、なぜそれがかまわないと言えるのかと考えたときに、私はベケットの中に、絶望しているからこそ生じてくるユーモアのようなものがあるような気がしていています。かつてはそれを、「道化」という視点から高橋康也さんが指摘していましたが、「道化」と言ってしまうと、どうしても「中心と周縁」みたいな話に限定されかねない。もう少し広くとらえて、「絶望とユーモア」が裏表一体の形で出てくるベケットに、私は面白さや魅力を感じます。そういう魅力に、絶望とユーモアを抱えた人がどんどん積極的に飛びついちゃうことは、むしろ芸術にとって必要なことなのではないかと思います。
金氏 僕もさっき藤田さんの言ったことが結論かなと思うのですが、そうですね……。意味が変わってしまうとか、反転するとかいうことが、僕がベケットの作品を観ていて面白いと思うところですね。さっき、『ハッピーデイズ』の最初の舞台美術のイメージに、ごみ屋敷というのがあったという話がありました。その話を聞いて僕も面白いと思ったんです。僕の家がけっこう、近所から見るとごみ屋敷に見えるようなところがあって(笑)。実際にはごみではなくて、作品の材料をいっぱい家の中に置いていて、はみ出しちゃって外にも置いたりしているんですけど、もしかしたら本質的にごみ屋敷の人と——僕は違うと思っているんですけど——一緒なのかもと思うときもあるんです。なんでそうなっちゃうのかと言うと、買ってきたり持ってきたりした大量にある物の中で、ルールというか規則性が見えてしまうことがあって、それに基づいて組み合わせたり並置したりしていくと作品が出来る。つまり、自分のルールに当てはまる物を取り出して使うんですけど、使い終わったあとの物はごみのはずなのですが、いま僕に見えていないルールがそこに含まれている気がしたりするんです。自分では気がついていないけれども、きっと、このあとに自分がこの中に何かを見出すはずだと思うと、そのときは価値がないと思っていても、将来の自分に価値があるかもしれないと思うと、もう捨てられない。そう考えると何を見ても捨てられない(笑)。
小崎 アンチ断捨離(笑)。
金氏 でもそれって、ある意味でがんじがらめで苦しいと思うときもあるけれども、一方で、自分と関係している物、将来関係するであろう物が身の周りにあふれている世界ですよね。しかもそれが、目の前にある物だけじゃなくて、まだ見ない場所にもあると思うと、ものすごく広く感じるときもある。その、苦しさと自由な感じの両方があるというのが、僕の中ではベケットの世界とすごく近いかなと思うところです。
小崎 「anywhere」ですね。では、多木さん。
多木 まだ見えていないルールというのは、まさに僕がベケットについて考えていることです。1、2年前に、こんなに面白い『エンドゲーム』は観たことないなというものに出会ったんですね。さっきも少し話しましたけれども、イタリアの刑務所演劇は非常に盛んで、プロのそれなりに腕のある演劇人が刑務所に行って、囚人と芝居をつくる。その中に、フィレンツェのすぐそばのプラートという街の刑務所でやっている、リヴィア・ジョンフリーダという女性の演出家がいるんです。『エンドゲーム』は、この映画祭でご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、悲しい話ですよね。でも、彼女がつくった『エンドゲーム』は全然違う。ものすごく明るい。それでいながらベケットを裏切っていないという感じがはっきりするんです。それは、ある意味でまったく新しいベケットのルールだと思います。みんな、こんなもんだな、不条理劇だなと思って1980年くらいまでやってきて、ソンタグのあとは、まったく違う切り口を見つけたような気になってやってきた。でも、また2020年近くに来て、全然違うベケットの読み方がこれから可能になるのではないかという気がしています。
小崎 ありがとうございました。今回の映画祭は10作品を上映しましたが、これは無数にあるバリエーションのひとつでしかありません。ベケット本人がつくったものもあって、それはバリエーションというよりも最初につくられたオリジナルですが、それから派生したものが、当然のことながら、この10作品以外にもあります。もちろんARICAの作品もそうですし、まだ観ていなければ、ぜひご覧になることをおすすめします。
現代アートに関して言えば、現代アートに最も影響を与えた人物は誰かと聞くと、ほとんどのアート関係者がマルセル・デュシャンと答えると思います。その次は誰かと言えば——これは日本のアート界では驚かれることなのですが——それがほかならぬサミュエル・ベケットだと私は思っています。金氏さんは、まさにこのふたりに影響を受けつつ21世紀にふさわしいアート作品と舞台作品をこれからもつくってくれることでしょう。そういうアーティストが増えることを願っています。
その一方で待望されるのは、いま話に出た「まだ見えていないルール」ですね。これまでとまったく異なるベケット解釈、まったく新しいバリエーションの誕生に期待したいと思います。
ということで、今日のトーク、ならびに足掛け4日間に渡って上映してきたサミュエル・ベケット映像祭はこれでお開きとなります。どうもありがとうございました。

*このラウンドテーブルは、『没後30年―サミュエル・ベケット映画祭』の企画として、2019年12月23日に京都造形芸術大学映像ホールで開催されました。
かねうじ・てっぺい
現代アーティスト。物質とイメージの関係を顕在化する造形システムの考案を探求し、日常の事物によるコラージュ的手法を用いて作品を制作。舞台作品にも取り組み、2017年にロームシアター京都で『tower(THEATER)』を上演。ARICA『しあわせな日々』の美術も担当した。
https://www.kcua.ac.jp/professors/kaneuji-teppei/
たき・ようすけ
演出家、アーティスト、批評家。大きく歪んだ現代世界の「歴史の創造力」の修復を目指すエコロジカルな創造力を持つ人々の活動を研究するとともに、その成果を教育その他の分野での実践に活用する。著書に『(不)可視の監獄 − サミュエル・ベケットの芸術と歴史』など。
ふじた・やすき
多摩美術大学で現代美術、東京都立大学でフランス文学を学ぶ。2001年4月、詩人・批評家の倉石信乃、アクターの安藤朋子らとともにパフォーマンスグループのARICAを設立。ベケットの『しあわせな日々』(『ハッピーデイズ』)を含む全作品の演出を担当する。
https://www.aricatheatercompany.com/
もりやま・なおと
演劇批評家。京都造形芸術大学舞台芸術学科教授。京都造形芸術大学舞台芸術研究センター主任研究員。KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)実行委員長。著書に『舞台芸術の魅力』(共著、放送大学教育振興会、2011年)など。
おざき・てつや
ジャーナリスト。アートプロデューサー。京都造形芸術大学大学舞台芸術研究センター主任研究員。あいちトリエンナーレ2013パフォーミングアーツ統括プロデューサー。編著書・著書に、『百年の愚行』『続・百年の愚行』、『現代アートとは何か』など。
(2020年3月15日公開)
○ラウンドテーブル:21世紀のサミュエル・ベケット 金氏徹平+多木陽介+藤田康城+森山直人