芸術論の新たな転回 01 星野 太(3)(Interview series by 池田剛介)それでもなお、レトリックを――星野 太『崇高の修辞学』をめぐって3
2017.05.07
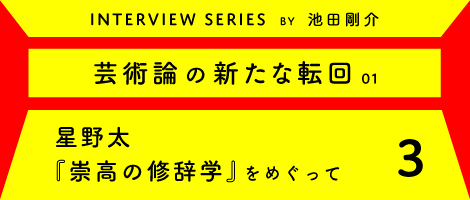
インタビュー:星野太
聞き手:池田剛介

『崇高の修辞学』星野太=著/2017年/月曜社
星野 本当にそうですね(笑)。京都的な「いけず」のように高度なレトリックが一般化した文化圏って、よく揶揄的に言われるじゃないですか。いわゆる「ぶぶ漬け」みたいな。つまりそれは端的に嫌味なものだと思われているんだけれども、この本に即して言うならば、僕はその「ぶぶ漬け」を擁護するスタンスを取っていると思うんですよ。最初に話していた同時代的な状況という話に戻ると、いま高度なレトリックというものはほとんど機能不全に陥っている。エッセイを書くにしても、講演をするにしても、ごく単純なメッセージを打ち出さなくてはいけなかったりする。
本来、きわめて複雑なテクスチュアを伴っていた言語というものが、いま急速に力を失いつつある。國分功一郎さんが最近「想像力」の問題を論じていますが、そこでジョルジョ・アガンベンの言語をめぐる議論を引き合いに出しています。アガンベンもやはり同じようなことを言っていて、つまり我々はもう言語を話していない。そのときの言語というのは、古代から近世において用いられていたような、高度にレトリカルな言語です。それに対して現代の我々は、Facebookのいいねだったり、LINEのスタンプだったり、ほとんど記号化された言語しか話していない、と。それに対して、僕の本は言語の修辞性をあくまでも強調する立場を取っているので、それはある意味で「ぶぶ漬け」的な言語環境を堅守していこうとする側に与しているんだろうな、とは思います。
少し話が逸れるかもしれませんが、古典ギリシア語ってやはり非常に高度な言語なわけですよね。だから学習が難しいんだけど、他方でそれによって可能になったことも沢山ある。いまのグローバルな言語といえばもちろん英語ですよね。英語は実は西欧語の中でも難しい言語だと言われたりもしますけど、表記法の面から言えば、英語って西欧の諸言語の中でもアクセント記号をすべて放棄した例外的な言語なんですよ。ドイツ語のようなウムラウトもないし、フランス語のようなアクサンテギュやアクサングラーブもない。グローバルな言語としての平準化された英語が、かつてのラテン語のように、我々のコミュニケーションの可能性を最低限担保するための言語として世界中で流通している。
池田 英語によって平準化された言語環境がグローバルに広がる中で、複雑なコンテクストをすっ飛ばして誰にでもわかる言葉遣いが力を持ってしまう。この本は、そうした言語の単純化に抗いつつ、なお言語の持つ表現の力を問い直すものであるわけですね。
星野 これも余談めいた話ですが、20世紀後半のフランスの思想家たちが、なぜああいう言語を使ったのか。すごく抽象的で難解な言い回しだと、よく批判されるじゃないですか。これは昔、内田樹さんが書いていたことなんですが、結局ああいう言語使用がどこから来ているかというと、実はナチスによる占領時代に遡るというわけです【『他者と死者――ラカンによるレヴィナス』海鳥社、2004年、152-156頁】。戦中期においては、あることを文字通りに言うことが死を意味する時代があったということでしょう。それはおそらく日本にも言えることだったと思いますが。
編集部 京都のような土地も似ていますよね。都だから常に権力者がいるわけで、町衆は自分たちの言動に常に気を配っていた。
星野 そうですね。それでもなお言うべきことがあるときに、それをどのように言うかといえば、比喩を駆使してレトリカルに言うしかない。僕の本で書いたことを現実の政治に即して考えてみると、比喩の問題というのは言葉遊びの問題ではまったくなくて、それが生死を分かつものになっていくという局面があると思うんです。今回の本ではそういうことは書かなかったけれど、本来的にはそういうことまで考えていく必要があると思っています。
池田 言語なり表現なりの方法的な次元を擁護するというのは、最近では見られなかった立場だと思うので、そこはすごく面白いと思いますね。
星野 思弁的実在論の話も先取りして言ってしまうと、僕のスタンスは昨今の流行りものであるところの思弁的実在論とは真っ向からぶつかるところがある。つまり、20世紀の哲学はウィトゲンシュタインあたりを境にして、言語をその中心に据えるという「言語論的転回」に支えられていたわけですが、現代ではそこからもう1回ターンしていて、言語から実在へ、という局面になっている。
池田 言葉に疲れたのでモノに帰れという。まあ僕もそれに近いのかもしれないけれど(笑)。
星野 その中で、僕はあくまでも言語が持つ修辞的な側面を強調するという立場を取っているから、おそらくその点においては思弁的実在論とか新しい唯物論という現象に対してブレーキをかけようとしている本だとみなされるかもしれない。
池田 なるほど。それは面白い配置になると思いますね。
パラボリック、プロトタイプ、パラマウンド 池田 思弁的実在論へのリンクも見据えつつ、少し修辞学的崇高の話に戻ると、パラボリックの議論はエリー・デューリングの言う「プロトタイプ」という議論ともどこかつながるんじゃないかなと思うんです。デューリングは現代アートにおけるコンセプチュアルアートや関係性の美学に代表されるプロセス主義のアートを批判していて、つまり作品そのものは存在しておらず、そのプロセスを提示したり、それをめぐる資料を展示したりするだけだ、と。現代美術の展示や芸術祭などでも散見されるタイプの提示の仕方なわけですが、こうした現代美術はその外見に反して、実のところロマン主義だろうというわけです。
プロセスを通じて到達しえない理念を暗示するに留まる現代美術の傾向をロマン主義と呼んで批判するわけですが、こうしたデューリングの指摘する傾向は、端的に美学的崇高であると言えるでしょう。それに対してどのように作品化する次元を再起動することができるのかというときに、オブジェのような完全なる自律性に戻るということではなく、しかし未決定的なプロジェクトに開くということでもない、オブジェの論理とプロジェクトの論理とを掛け合わせるのがプロトタイプである、と。このプロトタイプの典型的な例として挙げられるのが、パナマレンコの飛行船のプロジェクトです。ここではあくまでも実際に飛ばすことが大事である、と。やはりプロトタイプなので落ちて来ざるを得ないわけですが、しかしまた次なるプロトタイプとして飛行船を再上昇させる(笑)。
星野 デューリングのプロトタイプ論のポイントって、いま池田さんが整理されていたように「作品化する」という部分ですよね。プロトタイプというのは純然たるプロセスではない。あくまでも作品として仮固定され、一定の形を与えられるところに意義がある。しかし、同時にそれは決定的な作品の完成とも違う。それがまたプロジェクトを通じて、新たな未来に開かれているというところにポイントがあるのかなと思います。
池田 ええ。
星野 これも雑駁な言い方になりますが、デューリングの議論の中にはベルクソン主義があると思っていて、プロトタイプ論も潜勢態と現実態の議論を変奏したものだという印象を持っています。モダニズム的な作品概念が、ある決定的な固定、つまり崇高とも超越的とも言い換えうるようなある特異点を指向するのに対して、デューリングの場合は、プロトタイプという開かれた作品のあり方を擁護しているという点で、ドゥギーの「パラボリックな超越」のように、登りつめては再びやり直すという循環的なイメージを伴っているとも言えるかもしれない。
池田 そうですね。モダニズム的な決定性の崇高を外へ開くと同時に、ポストモダンなプロセス主義も実のところロマン主義だろう、とする点は強調していいと思うんですよ。つまりモダニズム的な決定性を相対化すると同時に、プロジェクト的な未決定性からも距離を取って、その中間に仮固定の状態としてある、いわば模型のようなものとしてのプロトタイプを重視する。パラボリックに戻って言えば、単に水平的に墜落すればよいということではなく、やはり高みを目指す必要もあるだろう、と(笑)。
編集部 そうした盛り上がりからの墜落ということで言うと、森村泰昌に《なにものかへのレクイエム》(2006〜)というシリーズがありますよね。ウラジーミル・レーニン、三島由紀夫、アドルフ・ヒトラー(を演ずるチャーリー・チャップリン)といった男たちに扮して、革命や政治演説など、彼らの人生における頂点に当たるシーンを再現する。大阪人である作家が彼らを模倣しながら、いわば滑稽に陥るわけですが、それは「カリカチュアとしての崇高」と言いえませんか。
池田 確かに森村泰昌のあのシリーズはわかりやすくパロディ的ではない。どこかアイロニーが決定不可能なところはありますね。
星野 そうですね(笑)。
池田 マジでやっているのかネタでやっているのか、よくわからない。それはあると思います。千葉雅也さんが森村泰昌論の中でパラマウンド(paramound)という概念を提起されています【「パラマウンド——森村泰昌の鼻」『ユリイカ』2010年3月号】。絶頂という意味でのパラマウント(paramount)、これは崇高的な垂直性と言っていいと思いますが、ファルス的な垂直性から横にズレたところで誇張的に膨らむマウンド(塚)のようなものとしてパラマウンドがあると。マウンドは盛り上がりであると同時に盛り下がりでもあるわけで、これはパラボリックのビジョンとも近い。
星野 千葉さんの「パラマウンド」は本当にすごい論文ですね。森村泰昌の作品の脱構築不可能なポイントは「鼻」であって、そこにはもちろん盛り上がりというイメージとの重ね合わせもあるわけですが、何者にでも化けられる森村さんの顔の中で、ただひとつ「森村泰昌」の表徴、シーニュというのが鼻であると。そこからラカンに接続しながら、盛り上がってズレるという思弁的な議論が展開される。いまおっしゃったアイロニーの問題、もしくは崇高から滑稽へという本書の議論とも、十分つながりうる論点だと思います。

修辞学と感性論、思弁的美学への通路 池田 先ほど出ていた表象不可能性の議論の延長上で、星野さんも論考などで扱われているジャック・ランシエールも含めてお聞きしたいと思います。例えばアウシュヴィッツのような悲惨な出来事について、表象不可能性の手前でひたすら倫理的な態度を要請する、倫理的に沈黙するしかない、という言説が一方にあり、これに対してランシエールが強く批判的な立場を取っている点に言及していただきました。まさに『ショア』が典型なわけですが、証言者にある種の無能力を強いる、証言の不可能を強いることになる。
美学というのはしばしば、なんというか政治・社会的な問題から乖離した、エリート主義的で現実に無関心な観照のようなものとして捉えられがちなわけですが、むしろランシエールは政治の根底の部分に美学=感性論を据えている。『解放された観客』の中でも言われるフランス二月革命の際の労働者新聞の記事からの例で言うと、板張り職人は普段、彼の仕事によって特定の時間と空間に結びつけられているわけですが、この職人がいままさに板張りをしている部屋の中で、眼差しを独占し、自分の部屋であるかのように空想をめぐらせる、と。こうしてある空間を眼差すことは本来権力者側に独占されてきたわけですが、ここで職人は所与の感性的な分配を逸脱しつつ別の感性、別の身体を手に入れており、政治とは絶えず、こうした感性的な所与の分配を再編成しなおすことなのだ、と。この意味で政治の根底に感性論がある、と言われます。今回の星野さんの本では、基本的に言語の問題を扱っているので、こうした感性論的な議論とは一定の距離を置いているかとも思うのですが、このあたりの議論とどのような接点が考えられるのかお聞きできますか。
星野 すごくありがたい補助線を引いて下さったと思います。おっしゃるように、僕はこの本で修辞学的崇高というものを強調するために、美学的=感性論的な議論とは完全に距離を取っている。いまのご指摘は、それでもなお両者になんらかの関係がありうるかというご指摘だと思うんですが、まさに池田さんが挙げられたランシエールの議論に即して、ひとつ例を示しておきたいと思います。これは『コンテンポラリー・アート・セオリー』所収の拙論【「ブリオー×ランシエール論争を読む」『コンテンポラリー・アート・セオリー』イオスアートブックス、2013年】で書いた話でもあるのですが、ティトゥス・リウィウスの『ローマ建国史』に、平民たちが貴族たちに迫害される場面がある。平民は貴族に対して交渉を試みるわけですが、貴族にとって平民は、自分たちと同じ言葉を話す対等な人間であるとは考えられていない。ではそこで自分たちの言葉をどのようにして聞かせるかと言えば、貴族たちと同じように神託を唱えるわけです。儀式が始まるときの祝詞のような、その神託の言葉を平民たちは口にする。それによって、貴族たちに自分たちが対等な人間であることを認めさせようとする。これはやはり政治とレトリックの問題に関わるポイントだと思うんですね。
ここから、なぜランシエールが「政治の根底には美学=感性論(エステティクス)がある」と考えたかといえば、そこには「声」の問題、すなわち貴族が平民の「声」をそれとして聞くか否かという問題があるからです。政治の根底にある美学=感性論というのは、ここでは「声」の問題として捉えられている。ある声を人間の言葉として聞くか、あるいは野蛮人や動物の雑音として聞くか、という判断の背後には政治的な決定がある。つまりある分節された音を、言語として聞くか雑音として聞くかという判断の背後には、そこで優位に立つ人間の恣意的な決定が存在するというわけです。『ローマ建国史』の平民たちは、自分たちのそれが貴族たちのそれと同じ「言語」であるということを認めさせるために神託を唱えた。この問題は、美学の問題と修辞学の問題を、再び結びつける重要なポイントだと思うんです。なので、『崇高の修辞学』の議論をランシエール的な政治の問題にもう一度接続するというのは面白いと思いますし、さしあたり僕の本では脇に置いていた政治の次元に、修辞学の問題を結びつけていくための重要なポイントになるのかなと思います。
池田 そうですね。さらに感性論的な問題ということで言うと、ランシエールのそれが人間的なレベルの政治に強く結びつくのに対して、思弁的美学はこうした感性論的な地平を人間のみならず、ほとんどすべてのオブジェクト、あらゆる存在へと開いていく方向性を持っていると思うんです。思弁的実在論は基本的に、カント以降の哲学の射程、つまり人間がどのように世界を認識するのかという問題設定そのものを相関主義として批判していると言われています。先ほど星野さんは、今回の著作の議論としては、こうした思弁的実在論の持つ方向性に対してブレーキをかける意味合いを持つのではないかと言われましたが、星野さん自身としてはこれらの動向と関わりのあるお仕事もされているわけで、この辺はどうお考えでしょうか。
星野 今回の本から離れて言うと、僕はカンタン・メイヤスーの『有限性の後で』【『有限性の後で――偶然性の必然性についての試論』千葉雅也・大橋完太郎・星野太訳、人文書院、2016年】の翻訳に関わっていたり、スティーヴン・シャヴィロの『モノたちの宇宙』【『モノたちの宇宙――思弁的実在論とは何か』上野俊哉訳、河出書房新社、2016年】の書評を書いていたり、いわゆる思弁的実在論に関わる仕事も少なからずしています。そこで、いわゆる思弁的実在論の美学、「思弁的美学」の問題を簡単に定式化しておくと、そこでの中心的な課題は、ひとことで言えば主体なき感性論、主体なき美学をいかに構想するかということです。つまり、彼らはカント以来の哲学が人間と世界との関係を第一原理とする「相関主義」であるとして批判しています。このことを美学の問題に適用するとすれば、そこでは主体なき経験、主体なき美は可能か、という話になってくる。スローガン的に言えば、「主体なき感性論は可能か」という問いになってくると思います。
しかし、これは誤った問いというか、語義矛盾であることは明らかです。主体なき感性論というのは、普通に考えればありえない。少なくとも、感性というものを人間に備わっている能力であると見なすならば、主体なき感性論などありえないと一刀両断する立場がありうる。しかし一方で、グレアム・ハーマンやシャヴィロが参照するアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドについて言えば、ホワイトヘッドが言う美というのは、どう読んでも人間(のみ)が感じる美ではないんですね。ハーマンもシャヴィロも、それぞれ美学を「第一哲学」として想定する哲学を構想しているわけですが、そこで重要な参照項となるホワイトヘッドの美というのは、主体が対象を通じて獲得する感情、あるいは性質ではない。だから、もしも思弁的美学に何らかの可能性を認めるとするならば、そもそも美や崇高というカテゴリーを人間からいったん切り離すということが最低限の前提になります。事実、そこでは美を存在論化し、この世界で起こっている現象一般に美を見出していくという、美という概念そのものの鋳直しが目論まれている。
思弁的実在論の人たちは、人間なしの世界ということをスローガン的に言うわけですね。メイヤスーだったら、「原化石」や「祖先以前性」という概念を手がかりに、人間がいまだ存在しなかった世界について思弁的に考える。レイ・ブラシエは、人間、さらには生物がいなくなった「絶滅」の世界について考えることをひとつのモチーフにしている。いずれの方向にせよ、それによって人間から切り離された世界そのものの実在を論じるという方向に向かうわけです。しかし、そこで忘れてはならないのは、それを論じている彼らは人間であり、言ってみればそれは人間の言語によるSF的な想定であるということです。そこで実質的に生じているのは、言語によって、それこそ崇高なもの、到達不可能なものを論じるという一種のナラティブにほかなりません。だから、思弁的実在論が主張している内容とは別の次元で、彼らの言語行為そのものの中に、ある種の崇高なレトリックの追求というものを指摘してもいいと思うんです。
池田 特にハーマンのテクストとか本当にレトリカルというか、もう比喩だらけ(笑)。むしろ比喩を使い過ぎというか、今回の議論的には、崇高であるためにはもうちょっと……
星野 テクネーを隠さないと(笑)。
池田 そう、もっと隠すべきなのではないかと(笑)。しかしあえて隠さずに、むしろ比喩を増殖的に繁茂させていく、そういうレトリックでもあると。
星野 そうですね。
池田 シャヴィロも『モノたちの宇宙』の中で美と崇高ということを言っていて、美を関係性に、崇高を実在性に対応させています。ホワイトヘッドによる関係的な美への志向に対して、ハーマンは実在性、つまりそれぞれの存在への自閉的な引きこもりという点を強調とするので崇高のほうに位置するんじゃないかと言っている。それは感じとしてはわかるんですよね。というのは要するにカント的崇高ってある種の暗示、アリュージョン(allusion)ですよね。見えないことを通じて暗示する。ハーマンの議論では、すべての存在は実在的なレベルでそれぞれに引きこもって隠れているけれども、同時にそれが感性的なレベルの魅惑(allure)によって引き合ったりすれ違ったり、なんらかの相互作用を持っている、と。その意味では超越的な一者へと向かう崇高と言うよりも、ほとんどすべてのオブジェクトが崇高を持っている。崇高を徹底して複数化することによって崇高を横にズラすような、そういう戦略かなという感じもしますね。
星野 おっしゃる通りですね。シャヴィロは、ホワイトヘッドとハーマンの違いというのは「美の美学」と「崇高の美学」の違いとして理解できると言っている。ホワイトヘッドは、この世界のあらゆる相互的な接触(=包握)に関わるものとして美を考えている。それに対してハーマンは、我々はそれぞれのオブジェクトが持っている深みには決して到達できないというわけです。つまり、我々は目の前のコップが持っている存在の深みには決して触れることができない。人間もまた、あくまでもその表面において、オブジェクトとして触れ合っているに過ぎないと。そのオブジェクト同士の内奥は互いに知りえないということを言うために、ハーマンは魅惑(allure)という言葉を使っている。これはある意味でカントが言う暗示(allusion)と同じ構造なんですよね。その真の姿はわからないけれど、その仄めかしの次元を我々は感受しているのだと。その構造だけを取り出してみれば、確かにこれはカントの崇高論に近いと思います。
池田 でもそれがカント的な主体-客体の構造ではなく、つまり人間が主体として一方的に対象から崇高を受け取るということではなく、人間もまたひとつのオブジェクトとして動植物や無機物も含めた諸存在と同一平面上にあり、ありとあらゆるオブジェクト間で、崇高の惹起が互いに起こりまくっている、と。
浅い質問になりますが関連するかもしれないのでお聞きすると、パンタシアーという言葉が「現れる」という動詞に由来していて、これが中動態であると書かれています。中動態は、能動か受動かという区別、つまりある行為の主体と客体とを判然と分けることのできない中間にあるものと考えられますよね。確かに「現れる」ことは、自分が見ることであると同時に向こう側からやって来ることでもあって、主体的に世界に関わることと世界の中に受動的に巻き込まれることとが絡み合っている状態として考えられる気もします。先ほど言及された國分功一郎さんも『中動態の世界』【『中動態の世界――意志と責任の考古学』医学書院、2017年】という本を出される予定だそうですが、パンタシアーの持つ中動態の含みは関連するかもしれませんね。
星野 パンタシアーという名詞が「パイネスタイ」という中動態の動詞から派生していることは、確かに重要なポイントだと思います。つまり、そこで言うパンタシアーというのは、先ほどの幻覚なり、錯覚なり、あるビジョンを見てしまうことだと思うんですが、そのビジョンが何に属しているのか、という問題と関わってくる。ロンギノスの場合、パンタシアーとは語り手から聞き手、書き手から読み手へと伝達されるイメージだから、確かに書き手、語り手の側から伝達されるイメージだと言えるかもしれないけど、一方でそれを受容する側が抱くビジョンでもあるから、結局イメージがどこにあるのかというのは宙吊りなわけですよね。そういう意味でも、パンタシアーの中間的な性格を強調する意義はあると思います。
超越的ではない、内在的な崇高とは何か 池田 星野さんの議論が持っている、日常性との地続きな感じといいますか白昼夢的な感じは、確かに主体と客体、受動と能動との区別が曖昧になる感じと通じているのかなという印象があります。
星野 個人的な話になりますが、崇高について考えはじめたときに持っていた感覚として、崇高がもっぱら超越性に結びつけられることに大きな違和感がありました。むしろ僕は、いま池田さんがおっしゃったような白昼夢的なものにこそ、ある種の内在的な裂け目としての崇高さを見たかったんですね。それは個人的な肌感覚に過ぎませんが、それがこの本には結果的に反映されていると思います。よりシンプルに言えば、超越的ではない、内在的な崇高とは何かということが、最も根本的な自分のモチーフとしてあります。
池田 もともと崇高を研究しようと思ったきっかけは、どういうものだったのでしょうか。
星野 僕は大学時代に美学芸術学研究室というところにいたんですが、近代以降の美学を勉強するときに崇高は必ず出てくるんですよ。特に、当時の指導教員は小田部胤久先生というドイツ・ロマン主義の専門家だったので、バークやカントのような教科書的な議論のほかにも、フリードリヒ・フォン・シラーやフリードリヒ・シェリングをはじめとするドイツ観念論における崇高論にはずっと興味を持っていました。修士から表象文化論研究室に移って、最初は20世紀における崇高の概念について、わりと手広い修論を書こうと思っていました。ただ結局、修論は誰かに関するモノグラフがいいだろうなと思って、リオタールをやろうと思いました。リオタールは日本ではろくに読まれてこなかった人だったので、自分がきちんとやろうと。特に面白いと思ったのは、リオタールが崇高についてかなり幅広く論じているだけでなく、それが資本主義という問題系に結びつけられていたことでした。その後、博士に上がってこれからどうしようかなと思っていて、はっきり方向性が定まらないまま、とりあえずフランスに行くことにしました。するとフランスでは、日本ではほとんど読めなかった修辞学関連の本がたくさんある。カント以前の崇高論というのはそれ以前にも知識としては知っていたのですが、向こうにいると、古代のロンギノスから初期近代のボワローまで、カント以外の様々な人の崇高論がどんどん目に入ってくる。ここにはすごい鉱脈があるぞ、という感覚を持ったんですね。
ちょうどそのころ、先輩に当たる宮﨑裕助さんの『判断と崇高』という本が出ました。それ以前からも宮﨑さんのお仕事はずっと追いかけていたんですが、この本は、ある意味、僕が美学的崇高と(事後的に)呼ぶものの決定版のような本だったんですね。カントとポスト・カント(とりわけフランス現代思想)を対象とする崇高論として、これ以上の仕事は今後も日本語ではありえないだろうと。では、反対にそこで論じられていないことは何かというと、まさに修辞学における崇高の問題だと思ったんです。だから自分の本は、宮﨑さんの『判断と崇高』を補完するために書かれたというのが、自分なりの認識です。もちろん、日本語で読みうるすぐれた論文や研究書はほかにも少なからずありますが、とりあえず哲学的な次元に絞って言えば、宮﨑さんと僕の本を読めば、西洋哲学における崇高の核心的な問題はほぼ遺漏なく理解できるはずです。
池田 ありがとうございます。今回は『崇高の修辞学』の持つ多様なポテンシャルを広範に提示していただけたように思います。いわゆる「内容」的にはかなり詳細にお話しできたかと思いますが、しかしこれは「修辞」や「表現」をめぐる言語的な作品でもあるわけで、その部分はぜひ実際に本を読みながら、それぞれの読者に経験してもらえればと思います。次回以降に引き継いでいくべき様々な論点を提示していただき非常に充実した時間となりました。言語的に平準化していく世界の中で、なお理論と実践とを架橋しながら言説を組み立て直していくという今回のシリーズにとっても、たいへん勇気づけられるお話が伺えたかと思います。長時間、ありがとうございました。
(2017年3月5日、元新道小学校・池田剛介アトリエにて/2017年5月9日公開)

ほしの・ふとし
1983年生まれ。美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。現在、金沢美術工芸大学講師。著書に『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)、共著に『コンテンポラリー・アート・セオリー』(イオスアートブックス、2013年)、共訳書にカンタン・メイヤスー『有限性の後で』(共訳、人文書院、2016年)などがある。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。
〈C O N T E N T S〉
芸術論の新たな転回 01 星野太(Interview series by 池田剛介)
・星野太『崇高の修辞学』をめぐって1
・星野太『崇高の修辞学』をめぐって2
・星野太『崇高の修辞学』をめぐって3